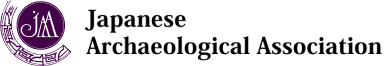歴史教科書問題検討小委員会について
歴史教科書を考える 第1号
2007.5.25 日本考古学協会 社会科教科書問題検討小委員会
1.歴史教科書問題検討小委員会について
平成10年の学習指導要領改定にともない、小学校の歴史教科書が弥生時代から始まることになりました。
「ゆとり教育」が謳われる昨今の趨勢の下、授業数・授業内容が大幅に削減されているとはいえ、旧石器・縄文時代を削除し、日本列島における人類史を農耕社会から始めるということは、子供達の歴史認識を不十分なものとし、わが国の歴史教育として不適切なあり方であるといわざるをえません。
わが国の歴史教育において、考古学の研究成果が適切に取り扱われるよう働きかけることも日本考古学協会の責務であるという認識から、昨年4月に「歴史教科書問題検討小委員会」が設置されました。
本委員会は、教科書を中心に、総合学習(体験学習).副読本も含めて、①現況の歴史教育の実態を検証し、より適切な内容となるよう提言する、②古代はもとより中・近世以降においても、歴史教育の素材として考古学の研究成果が有効であることを提示し提案する、の2点をめざしています。
わが国の将来を担う子供達に、よりよい形で考古学の成果を伝えていくために、多くの協会員がこの問題に関心をもち、積極的に議論に参加してくださることを願っています。
2.アンケート結果より
昨年の日本考古学協会愛媛大会において、本小委員会は小学校の歴史教科書に関するポスターセッションをおこない、その場でアンケート調査をおこないました。多くの方から、小学校の教科書に旧石器・縄文時代の記述のないことに驚きの声が寄せられました。以下、アンケートのご意見、感想の一部を紹介します。
《2.現行の小学校学習指導要領、小学校第6学年の社会科教科書、およびポスターセッションに対する意見・感想》
〇指導要領の「国を愛する心」の表現には違和感あり。自分を実感し愛することができずにリストカットなど
の行動をとる子どもたちが多いのが実情である。文化財を通して「愛する」ということはなにか、実感させることが急務と思う。教科書については発達段階に即して良くできていると思う。(協会員 教員 40代)
〇露骨に「国家形成」のみを取り上げているように感じました。現在の政府の思惑が反映されているように思われます。(非協会員 大学院生 20代)
〇殆ど同じような内容になっているのは指導要領と検定のせいだと思っていました。(協会員 教員 60代) 〇こうした実情を学校現場にアピールすることが必要だと思います。(非協会員 文化財保護関係 40代) 〇子供たちが気をひく工夫が増えているが、内容、教科書の薄さには驚きました。(協会員 教員 40代)
〇中学校の社会科教科書から世界史の記述も殆ど削除されました。こうした問題を考古学として絡めるのも結構ですが、他の学会等との連携も図るべきではないでしょうか。(協会員 教員 50代)
〇現在の教科書が弥生時代から始まっていることを全く知らなかったので驚きました。研究者の間では縄文から弥生の文化的連鎖性が常識になっているのに、不自然さを強く感じました。また、戦前の「稲穂の国日本」的考え方に戻っていくようで危惧を感じます。(協会員 教員 30代)
《3.学校教育現場・博物館等における学習指導要領、および社会科教科書改訂の影響》
〇調べ学習などが多くなったのは悪いことではないと思う。(協会員 教員 40代)
〇小学生だけでなく教員も興味を持たなくなる。(非協会員 文化財保護関係職員 40代)
〇改訂後数年という段階で流れを理解している先生方も多くいると思われるが、10年、20年後が怖い。(協会員 博物館関係 60代)
〇基礎の基礎的導入なくて博物館では学習できない大きな影響があると思う。(協会員 教職 40代)
〇遺跡を大事にする心が育たない。モアイ像等で世界 遺産を傷つけた日本人旅行者の話に以前心を痛めたが、これからはもっとひどいことになりかねない。都市成立後の歴史のみを重視することは地方軽視、無文字文化軽視に繋がり、国際感覚を育てる上で望ましくない。(協会員 教員 40代)
〇教員は教科書で教えていますので、創意工夫で切り抜けていると思いますが、こうした教育を受けた子供が教員になった時が大変です。高校で非常に右傾化した生徒が増えています。これも影響でしょうか。(協会員 教員 50代)
〇大学で、歴史・考古学専攻ではない学生(いくつかの学部がミックス)のクラスを教えていますが、稲作以前に日本で食べられていたものについて知識が殆どゼロ(“木の実"などの答えもない)だったので少しびっくりしました。(協会員 教員 80代)
《4.学校敷育における考古学的成果の活用について》
〇文化財の担当者は児童・生徒の発達段階について勉強して頂き、興味・関心を高めるような方向へ導いてほしい。(協会員 教員 40代)
〇社会科の授業だけでなく、都道府県の教育委員会や博物館が出前・出張事業をすることを提案します。(協会員 教員 60代)
〇文化財保護行政の現場では小学生に生の遺物に触れさせる学習等を行っているが、その時に縄文時代はもっとも効果が高い。環境問題や生命の尊厳等にも広げられる分野である。(非協会員 文化財関係 40代) 〇自国の歴史・人類の歴史の学習が未来を開く。古くて新しい命題を認識すべき。(協会員 無職 40代)
〇8月に大阪大学で高校日本史・世界史の教員研修会が開かれましたが、考古学の部門はありませんでした。教員にたいして、考古学的成果の授業への活用などの研修会を各地で開くべきでは?(協会員 教員 60代)
《5.社会科教科書問題小委員会の活動に対する提言》
〇センター試験や大学入試の改革にも取り組んでほしい。単位未修得問題は、永年にわたる根深い問題の現れであると思う。(協会員 教員 40代)
〇近現代における歴史認識を深めるために戦争遺跡を取り上げることは大事ではないでしょうか? (非協会員 大学院生 20代)
〇海外での事例も知りたい。シンポジウムを開くのは有意義では? (協会員 教員 40代)
〇もっと学校現場の教員の声を聞いてほしい。(協会員 教員 60代)
〇まず、研究者で教科書の実情を知らない人が殆どなので、より効果的な広報、また意見交換の場の提供(協会の一部としてシンポジウムをするなど)を推進していただいたらと思います。(協会員 教員 80代)
3.投稿 歴史敦科書間題を考える
近年では、埋蔵文化財センターの有効利用と歴史教育の充実ということで、学校の授業に関わることが多くなってきています。その中で、教科書の改訂が与えた影響は計り知れないものとなっています。
教科書が改訂されてから、数年が経ち、弥生時代から教えることが定着しつつあります。しかしながら、教育現場としては、「弥生時代の農耕の始まりを子供たちに理解させるには、縄文時代を取り扱うことは不可欠」との認識で一致しています。しかしながら、我々との打ち合わせにおいて、指導要領にない時代について、表だってやりづらい面も持ち合わせているように感じられます。
今回、歴史の授業を始めて受ける6年生を対象に、学校側の許可を得て、旧石器時代から弥生時代への流れを、実物を子供たちに見せながら授業を実施しました。その結果、事前に聞いていたことではありますが、縄文時代の人気の高さには驚かされました。旧石器から弥生時代への流れを追うことで、より理解を深められると共に、農耕民族や遊牧民など、歴史上、様々な民族がいることを知っていることは必要と考えて実施したことではありますが、効果はあったかと思います。
しかしながら、縄文時代の知識については、クラスの約8割が知っていると答えるものの、その始まりの年代となると、3割程度、学校によっては1割程度となってしまっています。さらに、縄文時代より前の時代については、答えられるのは1割弱と、極端に知識から抜け落ち始めています。農絣の始まりを理解させるために学校側の努力で、縄文時代については何とか触れられてはいるものの、内容としてはさわり程度であり、旧石器については、実際に取り上げられていないのが現状のようです。
それぞれの民族が歩んできた歴史を正しく理解することが、周辺国との相互の交流において不可欠であり、偏った時代からの教育は、今後の未来ある子供たちへの弊害といわざるをえません。このままでは、実物をみて目を輝やかせる子供たちの目が曇りかねないと憂慮するものであります。 (協会員 富山直人 兵庫県)
日本考古学協会 声明第61号
学習指導要領の改訂に対する声明
1989年以来の学習指導要領の改訂にともない、小学校第6学年の歴史学習は「指導内容の厳遷を図る観点から、歴史上の代表的な事象にとどめて学習するようにし、網羅的な学習にならないようにした。」に従い、「農耕の始まり、古墳について躙べ、大和朝廷による国土の統一の様子が分かること」と、その内容を弥生時代から取り扱うことに改められた。この改訂によって、現行の教科書の本文から旧石器・縄文時代の記述が削除されたが、日本列島における人類史のはじまりを削除し、その歴史を途中から教えるという不自然な教育は、歴史を系統的・総合的に学ぶことを妨げ、子ども達の歴史認識を不十分なものにするおそれがある。
考古学は、祖先の生きた証となる物質資料をもとに歴史を復元する学問である。列島全域に普遍的に存在する考古資料は、文字などの記録では知ることのできない人々の生活や地域の豊かな歴史と文化をいきいきと物語るものであり、その成り立ちを理解するうえで欠くことのできない貴重な資料である。また、掘り出された遺跡・遺物に触れる感動は、子ども達に自国の歴史や各地域の身近なふるさとの歴史を学ぶという知的好奇心を刺激し、祖先に対する畏敬の念や生きる力と知恵、そして、生命の尊厳等を学ぶ教材として重要な意味を持っている。
現行の歴史教科書から内容が削除された旧石器・縄文時代の歴史は、世界やアジアのなかにおける日本列島の地域性と、南北に連なる列島内部において複雑で多様な自然環境とその恵みのなかで育まれた極めて特徴的な地域文化を生み出したのである。それは、列島文化の基底をなすものでもあり、弥生時代に農耕を始めたことの意味を正しく理解するためには、この先行する原始時代における社会のしくみや生活の様子を明らかにしておく必要がある。また、日本列島は、一律に稲作社会へと移り変わったわけではない。“稲作から国士の統一へ"で始まる歴史教科書は、本州の弥生文化とは異なり、稲作が行われずに、それぞれ「続縄文文化」と「後期貝塚文化」と呼ばれる独自の文化を発展させた東北北部から北海道、そして、沖縄を含む南西諸島地域の歴史を無視したものであることも危惧される.
日本考古学協会は、歴史教育に考古学の成果が適切に活用されるよう望むとともに、次回の学習指導要領改訂にむけて、文部科学省と関連審議会に対し、小学校第6学年の歴史学習の内容に旧石器・縄文時代も取り扱うように改め、教科書の本文中に両時代の記述を復活させることを強く求めるものである.
以上、日本考古学協会は2006年度大会の場において、ここに声明する。
2006年11月3日
有限責任中間法人日本考古学協会
その他の掲載記事(省略)
・「小学校の歴史教科書から消えた旧石器時代・縄文時代―歴史を途中から教える不自然さへの日本考古学協会の提言―」『社会科研究 6月号』明治図書
・中日新聞2006年10月25日『小学校の社会科教科書 消えた旧石器、縄文時代 考古学協会改善求める』
・上毛新聞2007年3月13日『旧石器遺跡が語るもの 「岩宿」通じ 夢はぐくむ』
・朝日新聞2007年3月20日(夕刊)『旧石器・縄文 なぜ消えた 小学校の社会科教科書 学会として復活要望(西谷正)
・赤旗新聞2007年4月17日『小学校教科書 消えた旧石器・縄文時代 神話取り上げさせ 考古学を締め出す』