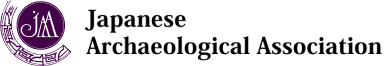第1回シンポジウム 「歴史教育と考古学」
歴史教科書を考える 第3号
2008.5.22 日本考古学協会 社会科・歴史教科書等検討委員会
1.第1回シンポジウム~歴史教育と考古学~の開催 社会科・歴史教科書等検討委員会
2008年2月4日に、教員養成課程を擁する東京学芸大学において、歴史教育における考古学のあり方を考えるシンポジウムを開催しました。このシンポジウムは、日本考古学協会の社会科教科書問題検討小委員会(現 社会科・歴史教科書等検討委員会:2008年4月の理事会において小委員会から常置委員会への移行が承認されました。)が企画し、東京学芸大学との合同主催として、また、日本歴史学協会歴史教育特別委員会、および、東京学芸大学の同窓会組織である会の後援を受けて実施したものです。
社会科教科書問題検討小委員会の発足経緯については、通信第1号でもお伝えしました。現在の小学校第6学年の歴史学習においては、1989年(平成元年)と1998年(平成10年)の学習指導要領の改訂による新教育過程の導入後、大幅に教育内容の削減が実施され、特に、考古学に大きな関わりのある分野では、現行の歴史教科書から列島の基層文化を形成した「旧石器・縄文時代」についての記述が削除され、歴史学習は「弥生時代」から取り扱うことに改められています。
日本考古学協会は、このような現状を改善し、わが国の歴史教育において、考古学の研究成果が適切に取り扱われるよう働きかけるために、国に対して声明文を提出し、学会の春と秋に開催される総・大会や、学会主催の公開講座等において、現状とその問題点を訴えるパネルディスカッションを開催してきました。
このパネルディスカッションでは、協会員を始め、一般の方々にも広く意見を求めるアンケート調査も実施してまいりました。その結果、多くの方々から、貴重な意見を頂きましたが、子ども達の教育現場におけるこのような実態を知らなかったという意見も、予想以上に多くお聞きしております。
シンポジウムの開催は、やはり、この現状を、より多くの学会の方々に知って頂くことが必要であり、また、歴史教育において考古学の特性や成果を十分に活かしていくためには、学校をはじめとする教育現場はもとより、他の学会との共同・連携が必要であると考たことによるものです。
第1回目のシンポジウムは、多くの教員を養成している東京学芸大学の理解と支持を得て、将来、日本の教育現場の最前線にたつ若い世代の皆さんからも広く意見を求めながら、活発な議論を重ねていきたいという主旨から、平日の開催となりました。
聴講された方々は、学生が半数で、教育関係者と考古学関係の方々、そして、報道関係の方々でした。平日にもかかわらず、また、午後1時から6時までという長時間に及ぶシンポジウムでしたが、会場となった講義室には常に200人に近い聴講の方々が訪れ、関心の高さを垣間見ることができました。
2.第1回シンポジウム~歴史教育と考古学~の記録
黒尾和久(社会科・歴史教科書等検討委員会委員)
第1回目として開催したシンポジウムのプログラムは、以下の通りである(全体司会:日本考古学協会 副会長 渡辺 誠:名古屋大学名誉教授、小委員会委員 佐古和枝:関西外国語大学教授)。
-プログラム構成-
■開会の挨拶(東京学芸大学 学長 鷲山恭彦・日本考古学協会 会長 西谷 正:九州大学名誉教授)
■基調報告
Ⅰ.歴史教育と考古学(社会科教科書問題検討小委員会委員長 岡内三眞:早稲田大学教授)
Ⅱ.小学校の教科書から消えた旧石器・縄文時代の記述(小委員会委員 釼持輝久:元横須賀市立長井小学校教諭)
Ⅲ.小学校学習指導要領と教科書の変遷(小委員会委員 黒尾和久:あきる野市前原遺跡調査会)
Ⅳ.学校教育と考古資料の活用(谷口 榮:葛飾区郷土と天文の博物館学芸員)
■パネルディスカッション『歴史教育と考古学』
司会:黒尾和久 パネラー:西谷 正・岡内三眞・釼持輝久・谷口 榮・木村茂光(東京学芸大学教授・日本中世史)・坂井俊樹(東京学芸大学教授・社会科教育学)・平田博嗣(東京学芸大学附属小金井中学校教諭)
■閉会の挨拶(日本考古学協会 副会長 木下正史:東京学芸大学教育学部特認教授)
(1)基調報告の概要
岡内三眞小委員長の「Ⅰ.歴史教育と考古学」では、「シンポジウムの趣旨説明」を踏まえて、小学校学習指導要領の改訂と歴史教科書、考古学の特質と歴史教育、社会科教科書問題検討小委員会の活動についての概要報告と、今後の活動方針について言及した。そして、旧石器・縄文時代が欠落している、歴史を途中から教えるという現行の歴史教育の不合理さを指摘しつつ、アジア史的視点に立った日本における歴史教育の必要性を主張した。また、より新しい時代に関しても、アジア社会との交流を意識した歴史教育、そこでの考古資料の積極的な活用の必要性を訴えた。
元横須賀市立長井小学校教諭で、本小委員会の発足のきっかけをつくった釼持輝久委員は、「Ⅱ.小学校の教科書から消えた旧石器・縄文時代の記述」という論題で、学校教育現場の現状を踏まえた歴史学習のあるべき姿について、問題提起を行った。釼持氏は、自らの縄文時代を中心とした授業実践例を紹介し、子ども達にとって身近な遺跡・遺物を教材とする歴史学習の意義を熱く聴衆に訴えた。特に歴史学習の入り口にたった小学生にとって、考古資料を用いた歴史学習が、正しい歴史認識の形勢のためにも非常に有効であることが強調され、小学校の歴史教育に考古資料を駆使した旧石器時代・縄文時代の学習は必須であることが述べられた。
小委員会委員、黒尾和久は、「Ⅲ.小学校学習指導要領と教科書の変遷」において、社会科教科書問題検討小委員会による小学校学習指導要領・社会科教科書の分析経過とその成果に関する中間報告を行った。報告の主な骨子としては、シンポジウム当日に配布した「資料集」を利用し、戦後の小学校歴史教育における旧石器・縄文時代を中心とした考古資料の取り扱いの流れを概観、学習指導要領の「改訂のねらい」とその方向性について批判的見地からの言及を行った。同時に、現行小学校教科書における縄文ムラの景観イメージの問題点を指摘し、あわせて、考古学者と歴史教育との関係性について主体性を確保するために、小委員会で作成を始めている「日本考古学界のあゆみと教科書の変遷」についても紹介した。
小委員会委員、谷口 榮は、「Ⅳ.学校教育と考古資料の活用」において、葛飾区郷土と天文の博物館の学芸員としての活動をもとに、博物館における考古資料を活かした「食育」「地域学習」をキーワードにした歴史教育の実践例についてスライドを用いて紹介した。この事例紹介と、その実践の意図するところについては、会場からも大きな反響があり、地域博物館と学校教育の連携について多くの共感の声が得られた。
(2)パネルディスカッションの記録(抄)
パネルディスカッション『歴史教育と考古学』では、基調報告の合間に、会場から意見や質問を頂き、それを受けて、パネラーに日本考古学協会から、西谷 正・岡内三眞・釼持輝久・谷口 榮、そして、ゲストコメンテーターに東京学芸大学側から歴史学・歴史教育の専門家として、木村茂光・坂井俊樹・平田博嗣の三氏に加わって頂き、歴史をなぜ学ぶのか、考古学の果たす役割、国が行っている歴史教育との関係性など、いくつかのキーワードをもとに率直な意見を述べて頂いた(進行・黒尾和久)。
紙数の関係で、すべては紹介できないが、ゲストの発言を主に報告しておきたい。なお、本記録は、一部途上ではあるが、小委員会委員:大竹幸恵が記録テープの書き起こしを行い、進行役であった黒尾の記録に基づいて、全体をまとめた。発言の意図と異なっている場合があれば、黒尾に責任がある。
【歴史をなぜ学ぶのか・考古学の果たす役割について】
木 村 日本歴史学協会(文献史学)では、毎年のように歴史教育・教科書に関するシンポジウムを開催している。今回は、考古学の立場から歴史教育を扱って頂けるということで、本シンポジウムが今後の歴史学と考古学の連携を考える良い機会となり、全体として歴史教育を考える大きな一歩になることを願っている。
シンポジウム開催の発端は、教科書から縄文時代が消えたことにあるようだが、その背景には、国が歴史をどう捉えていこうとしているのか、私たちがどう歴史を学び、教えていくのかという大きな問題が存在していると考えている。
歴史をなぜ学ぶのかという問いに対しては、会場に居られる多くの先生方でも、それぞれに微妙に違っており、絶対的な回答はないと思う。
私は授業で学生に、過去をどう認識するのか、その根本が歴史の問題に関わってくると話をしている。歴史というと、なんとなく古いことのように思われてしまうが、今日一日の時間の経過も過去であり、考古学が対象とする3万年も4万年も、また、同じく過去であり、そこから現在にいたる歴史に断絶はない。そういう意味で、現在を知るということは、一連の流れとしての長い歴史をしっかり押さえることでしかできないという捉え方で授業をしている。
考古学と文献史学との関係については、文献資料は時代を遡れば遡るほど、権力者・支配者側が残したものが多い。一方の考古資料には、権力を有する支配者が残したものもあるが、文献の歴史学に比べると、その影響の度合いは低いという性格の違いがある。歴史を学ぶためには、文献だけではだめで、考古資料をきちんと扱わなければ、歴史の全体像が見えないと学生にも話している。
「アジアに視点をおいて」という話もあったが、はじめから日本という国があったかのような錯覚に陥っている現状に対して、旧石器や縄文時代の学習が重要となってくる。子ども達は、日本列島といったときに、すでに日本という国があって、そこに完結した文化があったという認識を持ちやすい。その辺をどう打破していくかという視点に立ったときに、旧石器や縄文時代の学習が大事である。
韓国では、すでに、その問題を打破するために、一国史を教えるのではなく、東アジア史という教科プログラムを実際に施行している。そのような点を我々は、もっと学ばなければならない。考古学では、最初から対馬海峡や千島列島を線引きすることはしないはずである。また、我々はソウル市立大学と一緒に日韓交流歴史学会を立ち上げたが、方形周溝墓が両地域にあり、一時期問題となった前方後円墳の問題も含め、日本だけでない、アジア全体に広がった文化というものを認識する出発点になると思った。
坂 井 私は、民族紛争やホロコーストや虐殺、9.11テロの問題など、比較的、新しい時代の歴史を教えている。その時、古い時代の歴史学習はどういう意味を持つのか、いつも迷う。歴史は、15・6世紀から学べばよいという極端な考えもあり、現代史との接点について、どの様に考えるか大変、難しいと思う。
本日も、午前中に社会科の教師達の研究会に出席してきたが、そこでも古い時代のレポートは皆無であった。小・中・高の教師が参加する研究会なので、考古学のレポートが出ても良いはずだが、歴史教育の現場では概して考古学への関心は薄く、考古学が対象とする古い時代を学ぶ事の切実感が出てきにくい問題がある。
しかし、考古学は歴史教育において、非常に戦略的な問題に触れる領域でもあるといえる。日本には神話教育の問題があるが、考古学的知見は、それに対峙する性格をもつ。韓国・北朝鮮の歴史教育では、1960年代以降に旧石器・新石器時代の遺跡が発見され、歴史がより科学性を持ってきた過程がある。日帝植民地時代は、そうした半島の遺跡を破壊するのが、日本のやり方であった。その時代の日本考古学は、植民地支配の手先でもあったと言えるが、現在の韓国・朝鮮での考古学は、そうしたかつての植民地史観を具体的に覆す科学性を担保する積極的な意味を持っている。
考古学の有する性格は、歴史教育の戦略を考えるうえで、焦点になってくると考える。例えば、国境や紛争を乗り越えてくるという意味を持つ「渡来人」という言葉を良く使ってしまうが、古い時代に、そうした考え方が当てはまらない人間の往来・渡海が長くあったという認識を持つことが大切であろう。その際、国家とは何かを考え、国家を相対化するときに、本日のシンポジウムが対象としたような古い時代は、人間の生き方を考える意味で、非常に重要な時代である。
国家は、ある意味で為政者が意図的につくってきたものであり、しかも、日常生活とは直接結びつかない。国家は、領土問題や紛争といった国際関係の中で認識が高まってくるものである。それらを相対化するといったときに、考古学の成果が非常に重要な意味をもっていると考えている。
歴史教育からすると、小学生の歴史認識は、我々が考えるより進んでいるところもあるが、逆に、過剰に期待してしまっている点もある。例えば、時間の尺度がどのようにできてくるかについてであるが、小学校3年生になったばかりの子ども達は、テレビで見る武士のチャンバラ姿の直前が、いきなり原始時代というような頭の構造である。そこから適正な時間尺度を自分の相対的なものさしで認識していくためには、様々な歴史事象を学んでいき、その順序性など、頭の中での時間のスケールができる必要がある。
その正しいスケールをつくっていく上で、教室によく貼ってある年表の最も長い時間を占めている、考古学が対象とする時代の学習が大切である。文字や記録で残された時代だけが歴史ではない。それ以前に、もっと重要な長い歴史があるという時間尺度を正当につくってあげることが、歴史の思考力を育む意味で非常に大切なことになるのである。
平 田 国家というものを意識するようになるのは、近代のことであり、中国も日清戦争から国家の範囲を問題とするようになった。国家の認識について、日本といずれが早いかという話にもなるが、いずれにしても比較的新しいことである。
学校の先生を含めた世の大人達が、歴史が国家の枠の中で動いていると思いこんでいることこそ問題である。年表なども国家を単位として書かれている。歴史教育の実態は、それぞれの国がどうなったか、また、その国の以前がどうであったかというように、現代国家の枠組と、それ以前という形で授業が進められているため、国家という枠組みが、より強化されてしまっている。
授業では、人々の歴史とか、その生き様が変わっていく姿について、もっと多くの話をしていかなければならないと考えている。子ども達は、社会科や歴史学だけでなく、色々な勉強の中で発展していくわけで、先の博物館での実践例のように、多分野への発展性を持つ考古学は、そういう意味でも大切である。
中学生にわかる言葉で、なぜ歴史を学ぶかを話す場合、まず自分の好きなことを調べようという授業を行う。例えば、身近にある納豆の歴史。今ある納豆が、昨日は、一昨日はどうだったのか、そして、100年前、200年前はどうだったのかと遡って調べさせている。また、ものには必ず歴史があるという視点を意識させて、調べた歴史のことをレポートに書かせるようにしている。そして、もし歴史がなかったら、つまり昨日が無かったら今日がないし、明日を見るときにも、どこからどう進んできたのか、急に変えることは難しいなどと説明をしながら、今があることを考えさせ、明日を考えるためにも、昨日のことを勉強しなければならないという話をしている。
考古学で扱う歴史ということでは、刑事事件に例えて話をしている。物証があるかないか、自白だけでは捕まらないので、それがどれだけ正しいかを証明する方法や、記録は怪しいという話もして、物証で追いかけていかなければならないと説明している。
修学旅行で行く、飛鳥や奈良の話も、まさしく考古学的なアプローチで学習することができる。例えば、子ども達は、発見された蘇我氏の屋敷跡などについて調べているが、そうした学習に対しては、子ども達の関心も高く、発見された遺跡から何がいえるのか、夢を膨らませながら、色々な可能性について考えている。
【旧石器・縄文以外に教科書から抜けていて、考古学の視点から学んで欲しいことは?】
釼持 例えば、鎌倉時代のこと。最近の調査では、武士の屋敷のみならず、町屋やそこで使っていたハサミや食べたもの、おおくのカワラケなどが出土している。
今までは、「鎌倉の歴史」というと、頼朝をはじめとする政治体制が中心であった。しかし、調査で得られた豊富な出土資料をもとに、鎌倉政権や町をどんな人たちが支えていたのか、むしろ、そこに暮らしていた庶民の生き様が出てくるような歴史を子ども達に教えるべきではないかと思う。
岡 内 日本の歴史を考えるときに、対外的な問題が必ず出てくる。その場合、日本が加害をした、あるいは日本の被害という見方が多く、それを大きく取り扱う傾向がある。例えば、元寇の問題についても、その言葉は、元が日本に対して悪いことをしたという意味であり、適切な言葉ではない。蒙古襲来という言葉にすべきであろう。
一方的に良いとか悪いということではなく、各時代を通じて、互いにプラスになったことはたくさんある。そういうことをもっと取り上げ、強調する記述も考古資料からできることである。
谷 口 交流と地域性という点を、もっと打ち出すべきである。これは、考古学だけでなく、歴史一般について言えることである。また、ある時代だけを切り取って、その時代を説明するのだけではなく、時代を通して見えてくる様々な事象も教科書に入れていく必要がある。例えば、旧石器時代に大陸から動物や人々が来た、弥生時代に稲作が伝わってきたという一方通行だけではなく、全ての時代に大陸との相互の交流があったということがわかっている。最近では、縄文時代の様々な交流やネットワークづくりなども高校の教科書に書かれるようになったが、まだまだ不足している。
時代を通しての事例としては、火処の変化などがある。縄文・弥生時代は炉で、古墳時代になるとカマドに変わり、だんだん新しい時代になると西はカマド、東はイロリと地域差を生じる。その理由はなぜなのか。時代を切り取ってしまうと、その変化も見えてこない。
【「国」の歴史と考古学について】
西 谷 考古学という学問は、物質資料によって歴史を復元する学問である。何百万年前から現代までを含め、時代を問わない学問でもある。従って、「国」の歴史も考古学が対象として明らかにする歴史でもある。
そのような意味でも、近・現代の歴史がどの様に扱われているかにも注意したい。歴史的なものの考え方を子どもの頃から身に着けることが大切であり、その考え方を教えている、まさに近・現代がどの様に扱われているかも重要である。
九州国立博物館をつくるにあたっては近世までを対象とし、江戸東京博物館では終戦までを扱っているが、その1945年以降についてどの様になっているのか、その辺を子ども達に歴史的に理解させ、その現代につながる過去の歴史があることを教えるべきであると思う。
考古学の資料を教科書に活用する場合、近・現代の資料についても豊富な資料が得られており、それらをビジュアル的に示しながら活用すべきであると思う。
国際関係がややこしくなると、政治家は「未来志向」という言葉を使うが、賛成である。日本と中国・朝鮮半島の長い歴史の中には不幸なこともあれば、友好的な関係もある。その悪いことだけを必要以上に強調する必要は無く、事実は事実として、長い歴史の中で良かったことも、もっと示すべきである。例えば、日韓併合・植民地化という不幸の歴史は、二度と繰り返してはならないが、それ以前には徳川300年を超える友好の時代もあったことも示すべきであろう。長い歴史の中での位置づけの上に現代を理解し、友人としての東アジアの諸関係を構築していかなければならない。
将来的には、原始から現代までを通しての東アジア史の構築ということが課題になると考えている。
【日韓・日中の教科書について】
坂 井 教科書の更新ということでは、特に近・現代史について、今まで、考古学資料という視点が抜けていた。記述内容は文献等の記録によるところが大きいが、新しい事実に基づいて更新していく際に、考古学的な手法が新しいやり方と考えることができる。
東アジアの教科書、日韓の共通の教科書は5冊ほどつくられているが、それらを精査してみると、これでいいのかというのが正直なところにある。
日韓、日中の共通の教科書については、我々が国民国家史を背負っている限りつくることができない。歴史学は違うが、歴史教育というのは国家にとっては、じつに戦略的な教科であり、国民形成という明確な目的を持ち、学習指導要領もそうした体系を持っている。そこに挑戦していくことは難しいことであるが、あらゆる手段で考えていかざるをえない。
考古学の成果が日本の通史から抜けているから、あるいは、旧石器や縄文時代が必要であるという議論は、注意しなければならない。国民国家史の中に抜けているから入れるのではなくて、先に議論としてあったように、国民国家史とは別の、地域の総合的な歴史の基盤としてそれが必要であるという位置づけの発想法が重要である。
木 村 学術会議では、世界史の未履修の問題が議論されている。とりわけ地理の先生から社会科のあり方についての危機感が訴えられており、史学・地理などの委員会で研究会を開催し、地歴課基礎というような教科書ができないかを検討している。
日本の場合、世界史といいながら日本史が落ちている世界史であり、異なるところで日本史が教えられているという現状である。現在の教科書のスタイルでは、アジアという視点をいれた教科書はできない学習指導要領の構造になっている。
韓国が国策としてアジア史をつくっているということは、非常に大きな取り組みであり、それに比べて、日本側の史学や考古学の研究者においては、それほど明確なビジョンを持っているとはいえないと感じる。
日韓の教科書をつくる際、評価は別れるところでもあるが、交流があり、世界史ともいえる近・現代史は、むしろある程度、事実が復元でき、つくりやすい。それに反して、一国史であるそれ以前の歴史のほうがつくりにくい。一国史では、例えば、縄文時代、弥生時代といっても韓国では通じないというように、価値観が全く異なっている。隣接する韓半島に同じような文化があるにもかかわらず、国家もできていない、列島文化とも確定していないのに、列島内部だけで縄文・弥生文化としている。
頭の中ではアジア史をつくろうといいながらも、使っている概念は一国史であり、根本的に考え方を変えなければならない。例えば、推古朝といった場合、日本では、天皇の治世を「朝」と称しているが、韓国ではダイナスティであり、日本のいう「朝」に対して、それは何代続いたのかという質問が出る。英訳すると推古天皇の世代が何代も続いて、非常に大きな力を持ったという解釈になってしまう。
我々は、皇国史観という波を乗り越えて、戦後の歴史学はそれなりに民主的に進んできたともいえるが、実際に使われている概念や教科書の規定された認識の中では払拭しきれてない部分もある。アジア史やその交流に取り組むことによって、我々の中の一国史的な問題を問い直すことができると考えている。
概念を持っていないからやらないのではなく、やっていく中で、どこに共通する概念が持ちえるのかを考えていくことが大切であると思う。個人的な取り組みでよいから、できたら、アジア考古学というような本ができて、大学等の概説の授業などで使われ、学校の先生方もそれを目にするようになり、認識が広まるというような手法もあろう。
【会場との意見交換】
勅使河原彰 教科書における旧石器の記述に関して、より正確な分析が必要である。旧石器時代については、1970年代後半から文部省も認めてきており、1980年代から教科書に載るようになってきたということを確実に抑えておくべきだ。また、学習指導要領の改悪の問題点は、むしろ中学校の学習指導要領のほうが顕著に読み取ることができるので、分析対象を今後は、広げるべきであろう。
五十嵐彰 戦前の皇国史観に対して、なぜ、考古学・考古学者が立ち向かえなかったのかを、もっと明確にすべきである。それがない「未来志向」には意味がない。考古学は、過去のことばかりでなく、現代に通じる学問である。教科書に関する問題も、また近代から現代へと続いてきた問題であり、それに関して日本考古学協会が、このような取り組みをはじめたという意味では、記念すべきシンポジウムであったと思う。
松本富雄(小委員会委員) 「戦後を中心とした考古学や文化財保護の歩みと教育の変遷(作成途上)」を配布したのは、戦後史の中での考古学のあり方を考えることも、教科書委員会としての社会的な責任であると考えるからである。引き続き作業を継続したい。
渡辺 誠(小委員会委員) 考古学における編年研究偏重主義は、なにも皇国史観に覆われた戦前・戦中ばかりのことではない。それは戦後の体質としても、何ら変わっていない。だからこそ、教科書の問題を考えるうえにおいても、敵は文科省だけではなく、むしろ身内にいることを考古学者は肝に銘じるべきであろう。
戸沢充則 東京学芸大学の先生の立場から、とくに考古学と国史との関係を聞くことができて、非常に勉強になった。
何故、歴史を学ばなければならないのか、その動機は人様々であるだろう。私自身は15歳の敗戦のときに考古学を知った。それ以前は、神様の歴史しか知らなかったが、戦争が終わって、そうじゃない本当の歴史があることを知った。そして、それを知ることこそが歴史を知ることであり、自分達が生きていく基盤をつくると信じ、それ以来、60年間、考古学を続けてきた。歴史を学ぶということは、人類として本当の生き方をするのはどういうことかを考えることであると思う。そして、考古学は地域史をつくる基であり、そのことは、国家史を離れた人類史につながる歴史であると考える。
本シンポジウムにみられる新しい動きに感動した。
【最後に…】
西 谷 子ども達が歴史と対話し、創造していくという、その環境づくりを、私達大人の責任で行わなければならない。
学習指導要領や教科書の検討のみならず、考古学の立場からの独自の副読本の作成なども、教科書の委員会、あるいは日本考古学協会の仕事として、将来的に取り組むべきであろう。
坂 井 歴史教育の目的は、子ども達、一人一人の人生を豊かにすることである。その意味において、楽しい考古学、そのところを大切にすべきである。歴史教育は楽しく学ぶことが基底にあって、いろいろなことを学ぶことによって視野が広がるということが、忘れてはならない教育の論点である。
平 田 かつて、インカ帝国の土器を子ども達に見せたときに、それに比べて日本の縄文や弥生時代は遅れているという感想を聞いた。はたして、そうであろうか。
こうした反応の背景には、受験や学校で、一番が、一番良いという考えがある。しかし、上下水道の普及率を例にとれば、熊本県の普及率が一番低いのは、井戸から水が得られるからであり、けして、文化が低いというわけではない。
一番思考を打破することによって、より豊かなものが見えてくるのではないかと思う。また、そうした考古学ができれば、子ども達にも元気を与えることができるのではないかと考えている。
谷 口 文化財保護法では、文化財は国民共有の財産とされ、その保存と活用が謳われている。
遺跡の調査は、考古学者のためだけのものではなく、国民のためのものでもあり、どの様に活用するために、どう掘るのかという視点も必要であると考える。
また、そのためには、調査の環境や、資料がどの様に保管・保存・管理されているかという博物館に関わる問題が重要となってくる。指定管理者の問題等、博物館を取り巻く制度の問題などについても積極的に考えていかなければならない。
【閉会の言葉として】
木 下 5時間におよぶ熱のこもったシンポジウムであったが、学生にとっては、大学内では聞けない教育に関わる重要な課題を勉強することができた、意義のあるものであった。
本シンポジウムは、「歴史教育と考古学」という演題を通した様々な課題について、これからの教育を担う若い学生達に、知ってもらい、考えてもらう機会をつくりたいという思いから、企画提案したものである。
今日、学社連携という取り組みが盛んであるが、本シンポジウムは、学会と大学との連携という、未だ数少ない形態の取り組みであった。多様な立場や視点からの議論が交わされる中で、「歴史の学び方」、「国家史の中の歴史」、そして、「アジア史としての歴史」といった、大きな課題に向けての発展的な議論となったことは、非常に有意義なことであった。
(以上)
*
本シンポジウムでは、資料として、『小学校学習指導要領と歴史教科書の変遷―資料集―』(くにのあゆみ・教育出版・東京書籍・大阪書籍 A3版64頁)、『日本考古学会の歩みと教科書の変遷 学会の動向・文化財をめぐる社会的背景』(A3版8ページ)を作成・配布しました。
またシンポジウムに併行して、「1、教科書から消えた旧石器・縄文時代~現行の教科書から」「2、小学校学習指導要領と教科書の変遷~学習指導要領と教育出版発行教科書の変遷から」のポスター展示も行いました。
これらの資料やポスターの調査・作成に当たっては、東京学芸大学附属図書室と各教科書会社関連の多くの方々からご協力頂いております。日本考古学協会、および、社会科・歴史教科書等検討委員会は、それらを貴重な資料として、今後とも有効に活用させて頂くと共に、ここに感謝の意を述べさせていただきます。