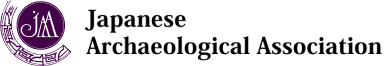2008年(平成20年)学習指導要領の改訂 ―改訂に向けてのこれまでの経緯と小委員会の活動―
歴史教科書を考える 第4号
2008.5.13 日本考古学協会 社会科・歴史教科書等検討委員会
1.2008年(平成20年)学習指導要領の改訂
○学習指導要領改訂に向けてのこれまでの経緯と小委員会の動向
2007年(平成19年)11月8日に、中央審議会初等中等教育分科会教育課程部会(以下、中教審)から、文科省に対し「教育課程部会におけるこれまでの審議のまとめ」が答申されました。この「…審議のまとめ」とは、文科省の諮問を受けて、2006年改正の教育基本法、2007年改正の学校教育法に対応する学習指導要領の方針をまとめたものです。答申内容については、一般にも文科省のホームページで公開され、1ヶ月間にわたってパブリックコメントが募集されました。
「…審議のまとめ」の中で特に注意されたのは、2007年9月12日の新聞報道で、-縄文?縄文以前?の復活-とあった改訂内容の確認でした。記述を確認したところ、教育基本法で「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」と謳われた第5号に対して、中教審では「我が国の伝統や文化についての理解を深め、尊重する態度は、我が国や郷土の発展に尽くした先人の働きや、伝統的な行事、芸能、文化遺産について調べるなど、社会科、とりわけ歴史に関する学習の中ではぐくまれるものであり、その充実を図ることが望まれる。具体的には、例えば、小学校においては、縄文時代の人々のくらしや、我が国の代表的な文化遺産を取り上げたりすることが考えられる。」としており、改訂の内容は、社会科教科書問題検討小委員会(以下、小委員会とする)が危惧したとおり、声明等で要望してきた列島の歴史の始まり=旧石器時代からを扱うものではありませんでした。小委員会では、この点について、委員単位で旧石器時代からの記述にすべきである旨の声明文に沿った意見をパブリックコメントに書き込みました。
中教審の答申を受けて文科省が作成する新しい『学習指導要領案』(以下、改訂案)は、明けて2008年の2月15日に公開され、中教審の答申書と同様に1ヶ月間にわたるパブリックコメントの募集が投げかけられました。
この改訂案では、「狩猟・採集の生活」とあり、先に指摘した縄文時代に限定する中教審の記述は表に出てこない表記法を取っています。1989年(平成元年)の学習指導要領以降に教科書からはずされた「漁猟」が、「狩猟・採集」という言葉に置き換わっているのは、文科省側ではけして時代を限定していない、つまり、旧石器を扱うか否かは受け手側の判断である…との対策であったのでしょうか。しかし、同じホームページ上で、小学校「社会科」改訂のポイントを解説したWebページをみると、そこには、「縄文時代の生活など」と示してあり、日本考古学協会が声明文の中で求めた本質的な改善には、至っていなかったことに気付かされました。
○新学習指導要領に対する要望書の提出
新学習指導要領の改訂案として示された内容については、伝統と文化を尊重することが強調され、縄文時代の復活が盛り込まれるなど、学会としての活動が一定の成果を導いたとする評価の声もあります。しかし、改訂案の基本的な立場については、先に指摘した旧石器時代の扱いを初めとして、本質的な改善を求めるべき点が多いといえます。学習指導要領の指導計画の作成と内容の取り扱いでは、「博物館や郷土資料館等の施設の活用を図るとともに、身近な地域及び国土の遺跡や文化財などの観察や調査を取り入れるようにすること。」とありながらも、授業での内容の取り扱いでは、あくまでも国を代表する資料を厳選するという立場が強調されている点も、その1例です。
小委員会では、この改訂案における問題点を整理し、3月16日を締め切りとするパブリックコメントに、『日本考古学協会社会科教科書問題検討小委員会』として意見を述べ、さらに、学会名で要望書(通信巻末参照)を文書で提出しました。これは、パブリックコメントの受付後、同3月末に内容を確定し公示するという国が示したスケジュールは、改訂案がほぼ決定案であることを暗示するものであり、パブリックコメントの書き込みだけでは、その効果が期待できないという判断によるものです。そして、今回の要望書については、要望の柱をなるべく短い単語・文章で盛り込み、より実現可能な修正の例文を加える形で作成しました。
まだ議論が不十分であるという意見も多い中、2006年には教育基本法が、そして、2007年には学校教育法が相次いで改正されてきました。その流れの中で、学習指導要領の改訂も、中教審の答申が公開され、具体的な改訂案の公開以後、余りにも短い期間で決定の公示がなされています。一ヶ月というパブリックコメントの募集期間は、関連する膨大な公開資料を十分に分析する間もなく、ましてや、決定とされた新学習指導要領は、このパブリックコメント締め切りから一ヶ月にも満たない期間での公示でした。公募方式とされるパブリックコメントはもちろんのこと、声明や要望の真意がどこまで伝わるか、大きな疑念を抱くところでもあります。
3月28日に公示された法的拘束力を有する、「学習指導要領」の内容は、その予測通りであったことは言うまでもありません。しかし、小委員会では、これまでの声明文や要望書に盛り込んだ改善点を継続的にアピールし、また、新たな学習指導要領を受け、3年後に誕生する新たな教科書をつくる側や、それらを使用する教育現場に対しても、内容の展開を具体的に提案する形で働きかけていく必要があると考えています。
2.社会科・歴史教科書等検討委員会として常置委員会へ
2006年から活動をしてきた「社会科教科書問題検討小委員会」が、本年の4月26日の理事会において常置委員会に移行することが承認され、理事会での検討の結果、「社会科・歴史教科書等検討委員会」として活動を継続することになりました。常置委員会とする理由は以下の通りです。
①小委員会発足の経緯となった、学習指導要領の改訂に伴い、旧石器時代の扱いや本質的な課題はあるとしても、「狩猟・採集」として縄文時代に関わる記述が復活することとなり、一定の成果と足がかりを得ることができた。
➁①により、委員会の活動としては、旧石器時代の位置づけや、考古学研究の成果を活かした本質的な改善に対する要望を継続的に主張する必要性がある。
③特に、新指導要領の早期実施という動向において、新たに編纂される教科書の発刊までは、旧石器時代も含め、縄文時代の扱いについても記述のない現行の教科書に基づいて授業が進められる。これに対し、学会としては、教育現場、そして、教科書の作成現場に対する具体的な情報提供や提言をしていくことが、早急な課題として求められる。
④小委員会では、旧石器・縄文時代に限らず、各時代についても、同様に考古学上の成果が十分に活用されるよう、教科書の実態を検証しながら課題の所在と有効な提言をしていくことを活動目標のなかに掲げてきた。また、小委員会の活動に対しては、会員から、戦争遺跡の取り扱いや、国際的な視野に基づいた取り組みに対する要望も投げかけられている。
⑤以上の動向により、本年度は、①の短期的課題に対する小委員会としての活動段階から、常置委員会として②~④の本質的な活動に移行する重要な時期にあると考えられる。
今後の具体的な活動としては、歴史教科書等の検討を基礎として、考古学と歴史教育とのあり方について考え、具体的な提言も含めた学会活動に努めたいと考えています。また、委員会の構成員は、まだ11名の小規模な委員会ですが、当面は限りある予算の範囲で、今後の活動の進め方や組織体制のあり方についても検討を重ねていきます。常置化の大きな意義としては、学会が教科書や歴史教育に関する問題を普遍的なテーマとして学会活動に位置づけ、社会的な責任を持つということにあります。そのためにも、先を見据えた息の長い活動にしていく必要があります。しかし、一方では、通信の冒頭で紹介しました新学習指導要領に関わる動向や、常置化の理由にもあるように、変動の激しい教育現場の実情に合わせた、迅速な行動も求められています。それらに対応していくためには、ワークショップ的な活動方法の展開も含め、広く専門分野を横断する学会員の協力が不可欠です。
未だ暗中模索の段階ではありますが、多くの皆さんに、忌憚のないご意見や、ご要望、そして今後の活動に対してのアドバイスを頂きたいと存じます。