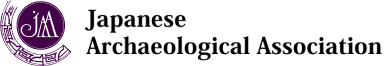小委員会から「社会科・歴史教科書等検討委員会」への移行と2008年の活動の経過
歴史教科書を考える 第5号
2008.11.8 日本考古学協会 社会科・歴史教科書等検討委員会
1.2008年の「委員会」活動の経過
~南山大学大会まで~
2006年から活動をしてきた「社会科教科書問題検討小委員会」は、2008年4月26日の理事会での承認によって、常置委員会「社会科・歴史教科書等検討委員会」に移行しました(「常置委員会とする理由」は「通信第4号」を参照してください)。
現在、委員会は当面の活動目標を、
①学習指導要領・同解説の改訂とその内容について動向を見まもり、必要があれば提言すること
②歴史教育において、考古学の研究・調査成果が適切に取り扱われるよう働きかけること
と掲げて、新旧学習指導要領(同解説を含む)および教科書について具体的な分析(小学校6年生社会上が中心)を鋭意継続しています。通信第5号では、本年の委員会活動についてご報告します。
2月4日に『第1回シンポジウム 歴史教育と考古学』を開催し、歴史教育における考古学のあり方について議論を深めました(通信第3号に概要を報告しました)。その直後、中央教育審議会の答申を受けて文部科学省が作成した『新学習指導要領(案)』が2月15日に公開されたため、委員会では、それを受けてのパブリックコメント(3月16日〆切)に意見を投稿し、あわせて3月22日付で、文部科学大臣・中央教育審議会会長宛に、日本考古学協会名で「学習指導要領の修正に関する要望書」(日考協第199号)を提出し、総会や協会のHP上でもその内容を広く周知しました(要望書の内容については、通信第3号に掲載しました)。
ついで日本考古学協会第74回総会(於東海大学)では、シンポジウムや委員会での議論・検討を踏まえて、第5会場「考古学をとりまく諸問題」において、3本の口頭発表(「小学校6年生の社会科教科書に旧石器・縄文時代の記述を」(剱持輝久)、「小学校学習指導要領案(文部科学省:2008年2月15日)の公表を受けて」(黒尾和久)、「学校教育と考古資料の活用」(谷口榮)を行い、ポスターセッション「学習指導要領と教科書の変遷」も併せて実施しました。
このようなシンポジウムの開催、パブリックコメントへの対応、「要望書」提出という作業の流れは、私たちの考え方を広く公にし、学習指導要領の改訂に際して、意見が反映されるように願ってのものでした。
確かに、新学習指導要領では、日本列島における人類活動の歴史を、「農耕の始まり」という途中から学習する不自然さが修正されて、「狩猟・採集の生活」が、学ぶべき「歴史的事象」として復活したことには一定の評価が与えられます。しかしながら、改訂案と同時に公開された「改訂のポイント」を参照することによって露わになった矛盾は、「狩猟・採集」の復活も、「縄文時代」の学習のみのが企図されたもので、必ずしも「旧石器時代」までが配慮されてはいない事実でした。
そこで、パブリックコメントや要望書では、「旧石器時代から始まる長い歴史」に十分配慮された歴史学習が行われるべきだという意見も強調しました。ところが、3月28日に告示された小学校学習指導要領の最終決定内容と、同時に公表されたパブリックコメントに寄せられた「意見」に対する「当省の考え方」という「回答」では、私たちの意見に対しての応答は全く確認できませんでした。また、「要望書」に対する回答も未だに頂けないままにあります。このことは、委員会や協会のアプローチと文部科学省側の考えとに大きな隔たりがあることを痛感させるものであり、議論の場に一歩でも近づくためには、尚、一層の粘り強い取り組みの継続が必要とされます。
この間、委員会は、定例会議の招集のみならず、1泊合宿研修を行って、旧学習指導要領に基づく現行の小学校社会科教科書6年上(5社)の内容について、考古学の調査研究成果がどのように取り入れられているのか、時代ごとに作業分担を決めて、さらに詳細に分析・検討を進めてきました。
今回、掲示したポスターは、①「学習指導要領案の修正に関する要望書」、②「学習指導要領および解説の新旧対比表」③「教科書にみる旧石器時代の取り扱い変遷(年表)」、④「旧石器時代の記述(変遷と現状)、⑤「縄文時代の記述(変遷と現状)」、⑥「弥生時代の記述(課題編)」、「⑦古墳時代の記述(課題編)」です。
スペースや作業の進捗状況もあり、通史的な検討結果全てを発表するには至りませんでしたが、③~⑦は、考古学調査・研究の成果と最も係わりの深い、旧石器から古墳時代に関する教科書の記述内容の変遷と現状、および、その課題となるところを抽出したものです。
新学習指導要領の告示に基づく教科書は、本年度から3年後を目指して編集、執筆が進められます。委員会としては、できるだけ早い段階に、日本考古学協会としての具体的な要望や提言を関係機関にアピールしていきたいと考えています。そのためにも、今後、考慮・修正されるべき課題について、ポスターセッション会場での多くの皆さんとの意見交換が行えることを期待しております。また、リニューアルしたポスターをもとに、具体的な意見を収集するためのアンケートも作成しました。忌憚なく、皆さんのご意見をお寄せ頂きたいと願っています。
2.「縄文復活!」で、何が変わったの?
~『小学校学習指導要領解説 社会編』1999年版と2008年版を比較する~
ポスター②の「学習指導要領および解説の新旧対比表」を、本紙裏面に資料として示しました。
新しい「学習指導要領」の内容が確定すると、しばらくして、その「解説」が文部科学省から公表されます。「解説」は、「大綱的な基準である学習指導要領の記述の意味や解釈などの詳細について説明するために、文部科学省が作成するもの」であり、各教科において、「その改善の趣旨や内容を解説」する役割があたえられています。各教科書会社では、2009年の教科書検定にむけて本格的に準備を進めていると思いますが、新編の教科書の中味を具体的に規定するのが「解説」の内容と言えるでしょう。
小学校社会科の「解説」は、2008年7月1日に文部科学省のwebページに掲載(9月18日に一部修正)、8月31日に一般刊行(東洋館出版社:頒価121円)がされています。今回はA4版となり、装丁が大きく変わりました。これも書店などで手にとってご覧下さい。
ちなみに文部科学省のwebページでは、7月17日付で、「6月末から7月にかけて開催した小学校新教育課程説明会(中央説明会)の各教科書部会の各教科書分会に、新学習指導要領及び解説について参加者の関心の高かった事項を一問一答形式で紹介」しています。ところが、不思議なことに私たちが注視する「社会科」に関しての記載が全くないのです。「社会科」については、「参加者の関心の高かった事項」がなかったということなのでしょうか。6年生に限っても、歴史学習のみならず、政治学習、象徴天皇制を含めた憲法学習や国際協調の問題など、いかなる学習内容が設定されるべきか、様々な立場からの発言があると考えるのが自然で、「参加者」のみならず国民的「関心」は、決して低くはないはずです。委員会のパブリックコメントや「要望書」についての対応と同様に、その結果として偏った情報公開がなされているのであれば、多くの意見に対する返答を示さないままに、「学習指導要領」そして「解説」の正当性を旦保していると懸念せずにはをえません。このような疑問を覚えるにあたって、公的な意見の募集とその結果の公開性についても、今後、その動向に注意を払う必要があるでしょう。
さて、「解説」の新旧比較ですが、今回はポスター③~⑦に対応する旧石器~古墳時代を対象とした「内容(1)ア」の規定範囲を対比してみました。その検討によって、「内容(1)ア」で、子どもたちが、何をどのように学習するのか、その構造がよく分かります。
それでは「調べる」歴史事象に「狩猟・採集」が加わったことで、いったい何が変わったのでしょうか?
結論は、残念ながら「ほぼ何も変わらない」と言えるでしょう。それは「解説」の新旧を対比すれば明白ですが、「内容(1)ア」の学習で、まず子どもたちに求められるのは、「大和朝廷による国土の統一の様子を分かるようにする」ことに尽きるのです。
確かに新「解説」には、「狩猟・採集や農耕の生活」という歴史事象を調べる「実際の指導に当たって」、「博物館や郷土資料館などを活用して遺物などを観察し、それらをもとに狩猟・採集や農耕の生活をしていたころの人々の生活や社会を考える学習」を行うと明記されました。地域の考古資料の利用・活用の必要性がうたわれたわけです。しかし、それも、あくまで「大和朝廷による国土統一」の前史学習としての位置付けに変わりないのです。日本考古学協会が提示した『学習指導要領の改訂に対する声明』に謳ってある、歴史学習の導入として「農耕の始まり」から列島の人類史を教えるのは不自然だという指摘が意図する、根本的な改善は図られていないというのが実態です。
一方で「神話・伝承」学習の必要性を説く、「内容の取り扱い(1)ウ」の「解説」には、「国が形成されていく過程に関する考え方をくみとることのできる、高天原神話、天孫降臨、出雲国譲り、神武天皇の東征の物語、九州の豪族や関東などを平定した日本武尊の物語」が変わらず具体的に例示されています。「神話・伝承」と考古学的事実との短絡的な援用がもたらした結果は、弥生・古墳時代のポスターでも明らかな様に、事実誤認や記述の不自然さを感じさせる部分に集約されていると思います。それ以前に「大和朝廷」という用語を利用することが本当に好適といえるのでしょうか。この点についても、皆さんはどの様にお考えでしょうか。是非、ご意見をお聞かせください。
(文責・黒尾和久)