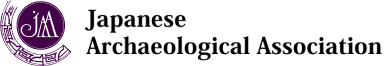『小学校学習指導要領』改訂を受けて
歴史教科書を考える 第6号
2009.5.26 日本考古学協会 社会科・歴史教科書等検討委員会
『小学校学習指導要領』改訂を受けて
社会科・歴史教科書等検討委員会
1.『小学校学習指導要領』改訂の課題とその後の動向
文部科学省から『小学校学習指導要領』の改訂が平成20(2008)年3月28日付で告示された。改訂内容の特徴については、『歴史教科書第4号』でも紹介したが、各教科ともに、1998年の改訂の際に消えた内容の復活が示された。また、「…の事項は扱わないものとする」とした、所謂「歯止め規定」が極めて少なくなっており、各学校における創意工夫や選択の枠を広げた形となっている。
日本考古学協会が問題としてきた小学校第6学年社会科についても、取り扱う「内容(1)ア」に「狩猟・採集や農耕の生活、…」が明記され、学習対象を弥生時代以降に限るという制限がはずされたが、取り扱う時代については、「我が国の代表的な文化遺産や縄文時代の生活など、我が国の伝統や文化についての学習を充実」するとしており、相変わらず、旧石器時代の取り扱いは明記されていない。
さらに、その後、文科省から発行された『学習指導要領解説・社会科』によれば、大和朝廷による国の統一を理解させるために、「狩猟・採集や農耕の生活について調べるとは、例えば、貝塚や集落跡などの遺跡、土器などの遺物を取り上げて調べ、日本列島では長い期間、豊かな自然の中で狩猟や採集の生活が営まれていたことが分かるようにするとともに、水田跡の遺跡や農具などの遺物を取り上げて調べ、農耕が始まったころの人々の生活や社会の様子が分かるようにすることである。」としている。つまり、復活した「狩猟・採集の生活」は、それ自体が日本列島の伝統や文化の基層として歴史的に位置づけられたものではない。あくまでも弥生時代の「前史」として、網羅的にならない範囲でふれる事象の一つに過ぎないことがうかがえる。
現在、各教科書会社では、学習指導要領の改訂を受けて、2011年度以降に使用する新しい教科書の編纂事業が進められている。こうした中で文科省は、昨年の12月に、教科書編纂への新たな方針を打ち出した。従来の教科書の記述に対する量的な制限を緩和し、参考となる事例を充実させるというものである。網羅的にならないように、厳選して…というこれまでの方針と比べ、大きな方向転換にもみえるが、具体的にどの程度の内容を補うことができるのか、なお動向を注意するとともに、この機に学会側からも、具体的な提言や情報の提供が必要と考えられる。
2.教科書改訂に向けての委員会の活動
常置委員会として新たなスタートを切った、社会科・歴史教科書等検討委員会では、この新たな教科書の編纂を念頭に、各時代を通して、子ども達に伝えたい内容や、現行の教科書の記述内容の分析と再検討を併せて行っている。
その経過については、昨年、南山大学で開催された日本考古学協会の秋季大会でも、ポスターセッションとして公開してきたが、旧石器・縄文時代の問題に限らず、弥生時代以降に関しても、今日の考古学的な成果が十分に活かされているとはいえず、事実の誤認が多いことも危惧された。
各時代を通しての分析作業や、具体的な提言内容については、まだまだ、検討・協議の途上ではある。しかし、長期的な取り組みを前提として、今後、近いうちに教科書出版社をはじめとする各関係機関に、委員会の中で問題となった現行教科書の現状と課題を整理し、今後の展望含めて改善要望を伝え、併せて、今後の協力関係を提言する予定である。
考古学の研究や調査成果が教科書ならびに学校教育の現場において適切に取り扱われるよう働きかけや発信を恒常的にしていくことは、『社会科・歴史教科書等検討委員会』の大きな目的のひとつである。しかし、教科書ならびに学校教育の現場において適切に取り扱われるよう働きかけは、委員会だけでは成し得ないことも多い。全国に4,000人を超す日本考古学会員の方々に、自らの地域資料の情報提供と活用方法の提案を学校現場にして頂きたいというのが、委員会の願いである。
新学習指導要領の改訂に伴う中高校現場の
取り組み現状について
社会科・歴史教科書等検討委員会 委員 山岸良二
(東邦大学付属東邦中高等学校教諭)
本校の沿革と紹介
東邦大学付属東邦中高等学校は1952年(昭和27年)に習志野市泉町に開校された。校地は戦前まで、習志野騎兵旅団の駐屯地として「軍都習志野」といわれた日本陸軍中枢地の1つであった。中でも、本校地
はかつては「騎兵第15旅団」、終戦間際は「陸軍中央研究所」が置かれていた場所にあたる。戦後、これらの軍用地が学校用地として払い下げされ、西から東邦大学、日本大学、本校、千葉大学と「文教都市習志野」へと変身した。
本校の設立趣旨は法人本部のある東京大森に戦前より設置されていた医学部(帝国女子医科専門学校)、戦後習志野に設置された薬学部関係の師弟を対象に、その後継者を育成するための附属高校としての創立であった。そのため、開校初期の段階から多くの生徒が「医学部、薬学部、歯学部」方面を志望する傾向が強い特色をもつ学校であった。この傾向は、現在でも継続され今でも高校三年生の約3割が同様の志望指向性をもつ学校となっている。
現行の社会科カリキュラム
現在の本校は中学1学年定員約270名、高校1学年定員350名で構成されている。つまり、高校で新たに80名を募集する形態(一般に鏡餅型6ケ年一貫私立中高校)である。また、県内の進学高校の一翼を担っていることもあり、週6日制35時限体制を堅持している。このため、中学での社会科時間配当は〔中1歴史分野2時間、地理分野2時間、中2歴史分野2時間、地理分野2時間、中3公民分野3時間〕となっている。いわゆる標準時間数でみると、公民分野が1時間少ない形である。一方、高等学校は先に挙げた本校生徒の志望動向から〔高1世界史B3時間、倫理3時間共に必修、高2日本史Bか地理のどちらかを選択しての必修3時間、政治経済2時間必修、高3文系は世界史B、日本史B、地理b、政治経済、倫理から最高2科目を選択しての必修6時間、理系は先の5科目から完全に選択で1科目3時間、さらに文系では自分の志望大学受験科目を考慮してさらに自由選択で6時間まで〕というカリキュラムとなっている。
公表されている新教育課程の内容
現在まで文部科学省から公表されている「新教育課程」中学社会科、高等学校地歴・公民科に関係する変更点の主なる点は次の通りである。
中学では平成21年度入学生から「移行期間」に入り、平成22年度入学生から「新学習指導要項」に定める授業時間数を漸次実施していくことになる。平成21年度入学生は中学で「地理105時間、歴史105時間、公民85時間」を履修、これが平成22年度入学生以降になると「地理120時間、歴史130時間、公民100時間」となる。ここで問題となるのが、歴史分野は一部中学3年生での展開が認められているのに、地理分野は15時間増加にもかかわらず現行と同じ2年間での履修となっているため、どのように指導計画をたてるかが現場にとって重要な問題点となっている。
一方、高等学校では標準単位数の大きな変更が予定されていないが、改善事項の中に「必履修科目である世界史Bにおいて地理や日本史の内容も充実」させるようにとの指摘がある。また、旧来必要がある場合には「その標準単位数の一部を減ずることが可能」であったものがなくなるとの指摘もある。
現時点での本校の対応状況
本年3月に「新教育課程への対応協議」が進路指導部(部長山岸)から提案された。その背景には、センター試験科目で地歴・公民科目の一部に変更が予定されている旨の情報が入ったためである。4月には教務部からも各教科に対応策の検討に入るようにとの指示があり、本教科では既に3回(5月2日現在)教科所属教員全員で検討議論を進めている。