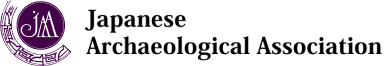新学習指導要領に基づく教科書の改訂と教科書委員会の取り組み
歴史教科書を考える 第7号
2010.5.23 日本考古学協会 社会科・歴史教科書等検討委員
新学習指導要領に基づく教科書の改訂と教科書委員会の取り組み
社会科・歴史教科書等検討委員会
平成20年度「小学校学習指導要領」改正とその後の動向
文部科学省から「小学校学習指導要領」の改訂が平成20(2008)年3月28日付で告示され、日本考古学協会が問題としてきた小学校第6学年社会科についても、取り扱う「内容(1)ア」に「狩猟・採集や農耕の生活、…」が明記され、学習対象を弥生時代以降に限るという制限がはずされた。しかし、取り扱う時代は、その後、文科省から発行された『学習指導要領解説・社会科』に、大和朝廷による国の統一を理解させるため、「狩猟・採集や農耕の生活について調べるとは、例えば、貝塚や集落跡などの遺跡、土器などの遺物を取り上げて調べ、日本列島では長い期間、豊かな自然の中で狩猟や採集の生活が営まれていたことが分かるようにするとともに、水田跡の遺跡や農具などの遺物を取り上げて調べ、農耕が始まったころの人々の生活や社会の様子が分かるようにすることである。」と明示され、あくまでも復活した「狩猟・採集の生活」は、日本列島の伝統や文化の基層として歴史的に位置づけるものではなく、弥生時代や古墳時代を理解させるためのコントラストとして扱うに過ぎない内容にとどめられていることが判明した。一方、1998年改定の際に厳格に「…の事項は扱わないものとする」とした、所謂「歯止め規定」が極めて少なくなっていることと、各学年における創意工夫や選択の枠を広げた形となっていることは、少しの救いと受け止められた。
また、文科省は、2009年の12月に、教科書編纂への新たな方針を打ち出した。従来の教科書の記述に対する量的な制限を緩和し、「網羅的にならないように、厳選して…」という前提条件を付し参考となる事例を充実させることを教科書編纂の新方針として打ち出した。これまでの方針と比べ、大きな方向転換にもみえる。具体的にどの程度の内容を補うことができるのか、動向を注意するとともに、この機に学会側からも、具体的な提言や情報の提供が必要と考えられた。
2009年度(平成21年度)「社会科・歴史教科書等検討委員会」活動
こうした状況を受け、社会科・歴史教科書等検討委員会(以下、「委員会」とする。)では、2001年度以降に使用する新しい教科書の編纂事業に対して、考古学の側からの提案を進めることとし、2009年度の活動を行ってきた。
a)75回総会時「小学校6年社会科(歴史)教科書を考える―教科書改訂への提言」
2009年度段階において、委員会では、各時代を通し、子ども達に伝えたい内容や、現行教科書の記述内容分析と再検討を行った。その結果、旧石器・縄文時代問題に限らず、弥生時代以降に関しても、今日の考古学的成果が十分に生かされているとはいえず、事実誤認も多く危惧された。
そうした状況を鑑み、第75回総会時の研究発表においては、検討・協議の途上の段階ではあったが、これまでの各時代を通しての分析作業を踏まえて具体的な提言を試みた。
研究発表の全体テーマは「小学校6年社会科(歴史)教科書を考える―教科書改訂への提言」とし、「学習指導要領の改訂とその後の動向」(松本)、「教科書改訂への提言 旧石器時代」(佐藤)、「教科書改訂への提言 縄文時代」(大竹)、「教科書改訂への提言 弥生時代」(岡山)、「教科書改訂への提言 古墳時代」(富山)、により、現行の教科書への提言と、新学習指導要領に基づいた教科書編纂に対するアピールを行った。小学校社会科教科書を発行する教科書会社にも開催の旨を通知し、出席を要請した。会場には、考古学協会会員の他にも、教科書や学校教育に関心のある方々の参加を多く得た。「列島の歴史をはじめから教えられない」という学校現場からの不安、「考古学的な成果が生かされていない不自然さや、身近な地域教材こそ児童にとっては馴染みやすい教材で社会科ひいては歴史に興味を持つきっかけになるはず」、旧石器・縄文時代の遺跡を多く持つ博物館関係者や自治体文化財保護担当者からは、「地域教材が活用されにくい状況への不安」などが意見やアンケートに寄せられた。残念ながら、教科書会社の方々からの見解やコメントはなかった。
また、総会2日目に行われたポスターセッションにおいても「小学校6学年 社会科(歴史)教科書を考える―現状と課題」をテーマに、これまでの経緯と現行の教科書の不自然さを指摘した。
b)2009年山形工科大学大会ポスターセッション
2009年10月17日・18日に開催された「日本考古学協会2009年度大会」ポスターセッションで、総会時に実施した内容を紹介した。大会の研究発表分科会では「分科会1:石器製作技術と石材」、「分科会Ⅱ:東北縄文社会と生態系史―押出遺跡をめぐる縄文前期研究の新たな枠組み」というテーマを持つほどに、山形をはじめ東北地域は、旧石器・縄文時代の遺跡が多く、研究も進んでいる地域であるが、現行教科書では、そうした成果すら児童に伝えることが困難である。こうした不自然な状況を、我々委員もあらためて痛感したが、会場を訪れポスターを読まれた方々の中には、「東北の文化の大事な部分をないがしろにした教育の在り方」と憤りを覚えるという方もあった。
c)岩宿博物館企画展「岩宿遺跡を学ぶ」
―日本考古学協会後援と展示解説講座への講師派遣―
詳細は、別稿に譲るが、群馬県の岩宿博物館が開催した企画展「岩宿遺跡を学ぶ」では、岩宿遺跡の歴史的役割と共に、明治から現在に至る教科書が展示された。この企画展開催にあたっては、岩宿博物館から日本考古学協会と日本旧石器学会に後援依頼があり、両学会がその趣旨に賛同し後援をした。また、博物館側からは、2010年2月14日に実施された企画展解説講座への講師派遣の依頼もあり、委員会の委員である大竹幸恵が「歴史教育と考古学―教科書から消えた旧石器・縄文時代の記述―」というテーマで講演をした。
岩宿遺跡は、旧石器時代という日本列島の黎明期の歴史を解明する契機となった学史的な遺跡である。講座には、その岩宿遺跡を大切に保存し活用するみどり市の市民が参加されていたが、現在の小学校6年生社会科(歴史)の在り方に対する驚きと、なぜ旧石器・縄文を小学生に教えないのか、その不思議さを指摘する声が多かった。
d)日本旧石器学会との懇談そして共催ミニシンポへ
日本旧石器学会は、2005年3月22日に発足した学術団体である。日本考古学協会主催の公開講座(第2回公開講座「日本列島の旧石器時代を知る~岩宿遺跡の世界~」)において、日本旧石器学会に協力を求め、当時の会長であった稲田孝司氏に旧石器時代を学ぶ意義について基調講演をいただいた経緯がある。その日本旧石器学会でも教科書問題を取り扱っていきたいとの方向性が示され、2009年12月27日に委員会と日本旧石器学会の担当窓口である広報委員会との懇談会が実現した。懇談会では、今後も情報交換だけでなく、両学会が合同の事業を企画する方向性も合意された。第76回総会時におけるミニシンポジウム「子ども達に旧石器・縄文時代をどう伝えるか―小学校の教科書で教えたい旧石器・縄文時代―」は、その活動の一環として委員会と広報委員会とが共催で実施し、日本旧石器学会からは白石浩之会長にパネラーをお願いし、歴史教育における旧石器時代の取り扱いとその意義について発言していただくことになった。
2010年度(平成22年度)活動 ミニシンポジウム
「子ども達に旧石器・縄文時代をどう伝えるか―小学校の教科書で教えたい旧石器・縄文時代―」を開催
日本考古学協会第76回総会第5会場
2010年5月23日(日)午後2時より
このシンポジウムは、日本旧石器学会広報委員会と共催で開催するものである。発表は、まず、考古資料を活かした郷土の歴史学習について、地域の博物館や学校の教育現場から報告をいただき、旧石器や縄文時代の研究者、教育学の研究者を交え、現状と課題、今後の方向性について議論する。
Ⅰ.事例報告
①野尻湖ナウマンゾウ博物館学芸員:中村由克氏
地域博物館における、児童や生徒を対象とした歴史学習の実践例を紹介していただく。また、教科書問題の影響や、その対策として学校側と取り組んでいる地域学習支援事業の内容等について紹介し、地域博物館としての今後の活動目標や、歴史学習の意義付けなどについて報告していただく。
②(元)川越市立西小学校長:松尾鉄城氏(東京国際大学教授)
学校の授業で、地域教材としての旧石器・縄文をどのように扱ってきたか、その実践例を紹介。また、学校の体制や社会科教育の現状と問題点を整理する中で、今後、考古学の成果を活かすために、どのような条件整備や連携の手法があるのか、その可能性や実践にあたっての歴史教育における視点について提言していただく。
Ⅱ.パネルディスカッション
事例報告者:中村由克氏、松尾鉄城氏
旧石器時代研究者:白石浩之氏
(日本旧石器学会会長・愛知学院大学教授)
縄文時代研究者:渡辺誠氏
(日本考古学協会副会長・社会科・歴史教科書等検討委員会委員長・名古屋大学名誉教授)
教育学関係者:木村茂光氏(東京学芸大学教授)
パネルディスカッションでは、
①教科書の影響とその問題について、
②旧石器・縄文時代を学ぶ意義について―教科書の課題と改善点について―、
③これからの歴史教育における考古学の課題
を議論の骨子として課題を整理し、今後の方向性として歴史教育に果たす考古学の役割や意義を導き出したい。
※今回のシンポジウムやポスターセッション等についてのご感想やご意見を、ぜひお寄せください。多くの方々の意見で、子ども達によりよい歴史教科書や、考古学的成果を生かした教育指導ができるような提言をしたいと考えています。
<情報>
社会科教科書の動向
2011年度(平成23年度)採択始まる
果たして旧石器時代・縄文時代の記述は
・・・新たなる提言と提案の必要性
2011年度から使用される新しい社会科(歴史)の教科書が文部科学省の検定を経て、現在、各市町村等でその見本本が陳列・閲覧されており、この6月に採択に向けての会議が持たれ、それぞれの地域で使用される教科書が決定される。
2011年度から採用される教科書は、2008年3月28日に告示された「小学校学習指導要領」の改訂を受けて、教科書会社が編纂したもので、今回の社会科教科書は、東京書籍・光村図書・日本文教出版の3社が編纂にあたっており、日本文教出版が一社で2冊の検定本を刊行し、計4冊の教科書が採択の対象とされている。
その具体的な内容の分析・検討については、今後の課題となるが、概観すると、縄文時代の復活に伴って、その扱い方に教科書間で格差が認められるようである。また、旧石器時代についての取り扱いについても、掲載している教科書と全く扱われていないもの、そして、その内容の位置づけが明確にされていないためか、内容の再検討が求められる表現も見受けられる。いずれも検定済みの教科書であるが、早急に分析を進めたい。
考古学の研究や調査成果が、教科書ならびに学校教育の現場において適切に取り扱われるよう働きかけや発信を恒常的にしていくことは、「社会科・歴史教科書等検討委員会」の大きな目的のひとつである。しかし、こうした働きかけは、委員会だけではその目標を達成し得ないことも多い。全国に4,000人を超す日本考古学協会員の方々に、それぞれの地域資料の情報提供と活用方法の提案を学校現場にして頂きたいと思う。また、委員会では、アンケートにおいて、多くの活用事例の情報提供を求めているが、そこで得られた情報を全国の教育現場に発信し、子供たちによりよい歴史学習を提供する、そのヒントになればと考えている。各方面に対する具体的な提言が、今後の委員会活動の大きな目標となろう。
<寄稿>
岩宿博物館企画展「岩宿遺跡を学ぶ」の開催について
岩宿博物館 今村 和昭
平成21(2009)年度は、岩宿遺跡発掘から60周年となり、還暦を迎える年度であった。
岩宿遺跡をメインとした岩宿時代専門の博物館である岩宿博物館では、年間を通してさまざまな岩宿遺跡発掘60周年イベントを実施した。「相沢忠洋資料特別展示」や「相沢忠洋、その人となり」という岩宿遺跡60周年記念特別展示や、例年秋季と冬季の2回開催される企画展も岩宿遺跡60周年を記念した企画展であった。
秋季企画展は岩宿遺跡そのものの実態を概観する展示であり、「岩宿遺跡はどのような遺跡だったのか」のテーマで実施した。
冬季の企画展は「岩宿遺跡を学ぶ」というテーマのもと、平成22年1月30日から3月7日まで開催した。明治初期の学制発布から、現在までの学校教育で使用された日本史の教科書を展示した。岩宿遺跡の取り扱い、大きくは学校教育における日本史教育のなかで、考古学的分野の取り扱いはどのような変遷をしてきて現在どのような問題が発生しているのかを考え直す機会を提供する展示を試みた。
岩宿遺跡の発見は、戦後の新しい教育観のもと、戦前の皇国史観のしがらみから歴史を自由にし、科学的根拠に基づいた歴史へと目を開かせる一つの原動力になった。その歴史的役割と学校における歴史教育における岩宿遺跡の意味の変遷をたどるのが本企画展のテーマであった。それと同時に、現在、小学校6年生で学習する歴史の中で、歴史教科書の記述が「弥生時代」からはじまるものが一般的となっており、岩宿時代(日本の旧石器時代)、縄文時代が削除され、日本列島における人類史が農耕社会から教えられているという現実の問題があり、広く観覧者に知ってもらうという意図があった。
日本考古学協会・日本旧石器学会等の学術団体でも現在の歴史教科書のあり方に危惧を示し、日本考古学協会では、常置委員会として「社会科・歴史教科書等検討委員会」を設置し、教科書の分析を通して、歴史教育における考古学の果たす役割について検討を重ね、考古学の成果が適切に活用されるよう広く提言していく活動を展開している。そこで、今回の企画展では、日本考古学協会・日本旧石器学会の両団体に後援していただき、様々な協力をいただいた。
また、特別に平成22年2月14日には、企画展解説講座を開催した。講師には、両学会のご協力により勅使河原彰先生・大竹幸恵先生にご依頼することができた。勅使河原先生は『歴史教科書は古代をどう描いてきたか』という著書を公表されているが、同テーマでそのエッセンスを講義していただいた。大竹先生には「歴史教育と考古学―教科書から消えた旧石器・縄文時代の記述―」というテーマで日本考古学協会の社会科・歴史教科書等検討委員会の活動状況と博物館と学校教育の取り組みを現場の学芸員の立場から講義していただいた。
講座には、37名の参加があり、両先生の講義を真剣に受講していた。参加者は一般市民であり、現行の教科書の実態を初めて知る参加者がほとんどで大きな驚きをもって講義に聞き入っていた。