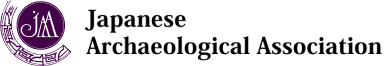第2回シンポジウム「小・中学校段階における歴史学習と考古学の役割」
歴史教科書を考える 第11号
2014.5.18 日本考古学協会 社会科・歴史教科書等検討委員会
テーマ 「小・中学校段階における歴史学習と考古学の役割り」
~日本列鳥における旧石器時代の取り扱いについて考える~
期日:2014年5月18日(日)14:00~16:55
会場:日本大学文理学部キャンパス(東京都世田谷区桜上水3-25-40)
第6会場:3号館4階3407教室
総合司会 :釼持輝久・宮原俊一(教科書委員会)
開会の挨拶・趣旨説明 14:00 佐々木和博(教科書委員会副委員長)
基調講演 14:05-14:35 (30分)
「日本考古学協会の歩みと歴史教育」 大塚初重氏(明治大学名誉教授)
・戦後の登呂遺跡発掘を契機として発足した日本考古学協会の歩みから、歴史教育における考古学の果たす役割を考える。
基調報告 14: 40-14: 55 (15分)
「義務教育における社会科歴史教育の現状と課題」大下 明(教科書委員会)
・教科書の記述と学習指導要領について、これまでの委員会活動による分析の結果から現状と課題を報告。
パネルディスカッション 15 : 05-16 : 50
司 会 :岡内三眞・大竹幸恵 (教科書委員会)
パネラー:大塚初重(明治大学名誉教授)、小野昭(日本旧石器学会会長)
近藤英夫・佐藤 誠・大下明(教科書委員会)
1) 戦後の歴史教育と考古学の役割り
2) 学習指導要領と教科書における課題の所在
3) 旧石時代の取り扱いについて
4) これからの歴史教育における考古学の課題
閉会の挨拶 16: 50 渡辺誠(教科書委員会委員長)
現行小学校6年生社会科教科書の出版社別採択地区数一覧表 (平成23~26年度)
※旧石器時代の記述を全く含まない2社(東書・教出)の地区別採択率は、約77%
| 採択地区数 | 東京書籍 | 教育出版 | 光村図書 | 日本文教A | 日本文教B |
東書601・2 | 教出603・4 | 光村605 | 日文607・8 | 日文609 | ||
北海道 | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
青森県 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩手県 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋田県 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
宮城県 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山形県 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島県 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京都 | 54 | 25 | 25 | 2 | 0 | 2 |
神奈川県 | 27 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 |
埼玉県 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
千葉県 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
栃木県 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
群馬県 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
茨城県 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山梨県 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
新潟県 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長野県 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
富山県 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
石川県 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
福井県 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知県 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
岐阜県 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
静岡県 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
三重県 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
大阪府 | 45 | 9 | 11 | 1 | 0 | 24 |
兵庫県 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 |
京都府 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
滋賀県 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
奈良県 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
和歌山県 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
鳥取県 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島根県 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡山県 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
広島県 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
山口県 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
徳島県 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
香川県 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛媛県 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高知県 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
福岡県 | 16 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 |
佐賀県 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
長崎県 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
熊本県 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
大分県 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
宮崎県 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島県 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
沖縄県 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 589 | 304 | 150 | 12 | 20 | 104 |
※(株)学書HPと各都道府県教委・教科書会社のデータをクロスチェックして作成
小学校学習指導要領の改訂に対する声明
日本考古学協会は、1998年の小学校学習指導要領改訂によって、第6学年の歴史教科書から旧石器・縄文時代が削除され、歴史学習が弥生時代からはじまるという不自然な教育がおこなわれていることに対して、繰り返し改善要望を提示してきました。2008年の改訂において、歴史学習のはじまりが「狩猟・採集や農耕の生活」と改められ、小学校の歴史教科書に縄文時代の記述が復活したことは大きく評価されます。
しかし、『小学校学習指導要領解説社会編』では、その具体的な内容として「貝塚や集落跡などの遺跡、土器などの遺物」について調べるという表記にとどまり、狩猟・採集の生活を営んだ日本における人類史のはじまりについての説明がありません。そのため旧石器時代について、本文で明確に位置づけられた教科書はなく、年表でも旧石器時代の名称が記載されていないという状況にあります。
旧石器時代の研究については、1949年の群馬県岩宿遺跡の調査以降、全国で1万ヶ所を超える遺跡の発見と調査事例の蓄積があります。そして、半世紀を超える研究によって、今日に連なる生活の技術や多様な環境を克服してきた社会の仕組みが具体的に解明されています。我が国の歴史を学ぶ上で、旧石器時代からはじまる歴史の推移と長く厳しい環境を克服してきた先人の営みが教科書の記述で取り扱われない現状は、学問の成果を教育に活かすという考えに逆行するものです。
また、旧石器時代の人々の生活・文化は、世界や東アジアとつながりをもちながら発展しつつ、次第に日本列島独自の地城性を形成してきたことも明らかにされています。これまでも中学校の社会科(歴史的分野)においては、世界史的視野で人類の出現と旧石器時代の生活・文化について扱っていますが、歴史を最初に学ぶ小学校段階で旧石器時代について学習することで、小・中・高等学校の学習内容の連続性を意識した学習が進み、「伝統と文化の尊重、それらをはぐくんできた我が国と郷士を愛し、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与」するとした教育基本法の理念を具現化するものと考えます。
私たちは、人々の生活や社会の営みをより具体的に復元することのできる考古学の成果が歴史教育に活用されるよう、今後ともこの問題への取り組みを継続し、改善に向けての協力を惜しまない所存です。考古学を通じて、子ども達がわが国の歴史や先人の知恵を学び、よりよい未来に向けて逞しく育ってくれることを願ってやみません。
日本考古学協会は、次期の小学校学習指導要領改訂に際し、小学校第6学年の歴史学習に旧石器時代の取り扱いを明確に位置付けた改訂を強く望みます。
以上、日本考古学協会総会の名において、ここに声明する。
2014年5月17日
一般社団法人日本考古学協会第80回総会
学習指導要領と教科書について
1 学習指導要領の法的根拠(上法優先の原則)
学校教育は、教職員の勤務から教育活動まで、法に基づいて行われている。
日本国憲法 26条
↓
法律 教育基本法(平成18年改正)
(法令) ・教育の根本的な理念や原則
学校教育法一部改正
↓ ・「教育課程に関する事項」
・教科に関する事項(教育課程※)
省令 学校教育法施行規則
(法令) ・「教育課程の編成」
↓
告示 学習指導要領の告示
・教育課程の基準(すべての子どもに対して指導すぺき内容の基準(基準性))
・小・中・高校などで教えるべき標準的な学習内容を示している
・昭和22年に最初の試案が発表されて以来、約1 0年ごとに改訂
※ 教育課程・・・学校が策定する指導計画(学校が編成し、実施する)
授業は教育課程を実施すること(授業は公権力の行使)
2 学習指導要領のできるまで
H15.5 中央教育審議会 現行学習指導要領の検証
H17.2 文部科学大臣 教育課程の基準見直しを指示
H17.4 第1回中央教育審議会(~39回)小・中・高校部会(11回)教科部会(89回)
H18.2 審議経過報告
Hl9. 1 「第3期教育課程部会の審議の状況について」をまとめる
H19.11 教育課程部会におけるこれまでの「審議のまとめ」公表
関係団体からのヒアリング並びに国民の意見募集(パプリックコメント)
H20.3 告示(高校はH2l.3)
H23.4 小学校学習指導要領実施
H24.4 中学校学習指導要領実施
H25.4 高等学校学習指導要領実施
3 学習指導要領の基本的な考え方
〇改正教育基本法等を踏まえた学習指導要領改訂
学校教育法第30条2項
「(前略)生涯にわたり学習する基盤が培われるよう,基礎的な知識及び技能を習得させるとともに,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力その他の能力をはぐくみ,主体的に学習に取り組む態度を養うことに,特に意を用いなければならない。」
基礎礎的な知識及び技能 →技能、知識・理解
課題を解決するために必要な思考カ・判断カ・表現力 →思考・判断・表現
主体的に学習に取り組む態度 →関心・意欲・態度
4 教育内容の主な改善事項(社会科に関わる事項を抜粋)
〇 言語活動の充実
・社会的な事柄について,資料を読み取って解釈し,考えたことについて根拠を示しながら説明したり自分の意見をまとめた上で,お互いに意見交換をしたりする活動を行う。
〇 伝統・文化に関する教育の充実
・世界文化遺産や国宝などの文化遺産を取り上げる歴史学習(小学校6年)
・身近な地域の歴史や各時代の文化の学習(中学校・歴史分野)
5 教科書の使用について
〇 教育課程の実施上、教科書の使用は義務
〇 教科書の種類
・文部科学省著作教科書
・文部科学省検定済教科書(民間出版社による著作・編集)80%以上
〇 教科書の選定・採択の周期(4年毎に改訂の機会)
年度 学校種別等 | H21 2009 | H22 2010 | H23 2011 | H24 2012 | H25 2013 | H26 2014 | H27 2015 | ||
小学校 | 検 定 | ◎ | ◎ | ||||||
| 採 択 | △ | △ | |||||||
| 使用開始 | 〇 | 〇 | |||||||
中学校
| 検 定 | ◎ | ◎ | ||||||
| 採 択 | △ | △ | △ | ||||||
| 使用開始 | 〇 | 〇 | |||||||
高 等 学 校
| 主として 低学年用
| 検 定 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 採 択 | △ | △ | |||||||
| 使用開始 | 〇 | 〇 | |||||||
主として 中学年用 | 検 定 | ◎ | ◎ | ||||||
| 採 択 | △ | △ | |||||||
| 使用開始 | 〇 | 〇 | |||||||
主として 高学年用 | 検 定 | ◎ | ◎ | ||||||
| 採 択 | △ | △ | |||||||
| 使用開始 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◎:検定年度
△:前年度の検定で合格した教科書の初めての採択が行われる年度
〇:使用開始年度(小・中学校は原則として4年ごと、高校は毎年採択替え)
〇教科書が使用されるまで(文部科学省HPより一部改編)
1年目(4月~3月)・・・1 編集 教科書発行者
2年目(4月~3月)・・・2 検定 文部科学大臣
3年目(4月~3月)・・・3 採択 所管の教育委員会等
4 発行 教科書発行者
4年目(4月~3月)・・・5 使用 児童生徒