第9回日本考古学協会賞
「第9回日本考古学協会賞」には、締切日までに14件の応募と2件の推薦がありました。2019年3月6日(水)に選考委員会が開催され、大賞には宮本一夫氏、奨励賞に高橋信武氏と中久保辰夫氏、優秀論文賞に黒須亜希子氏と田中 裕氏がそれぞれ推薦され、3月23日(土)の理事会で承認されました。各賞は、5月18日(土)の第85回総会(駒澤大学)において発表され、谷川章雄会長から賞状と記念品が授与されました。
受賞理由並びに講評は、次のとおりです。
第9回日本考古学協会賞 大賞
宮本一夫 著
『東北アジアの初期農耕と弥生の起原』 同成社 2017年2月発行
推薦文
本書の本文は15章からなり、そのうち12章は2003年から2016年に書いた13の論文を基にする論考、残りの3章は本書のために書き下した論文である。著者が、日本や韓国を含む東北アジアにおける初期農耕文化の伝播と人間の移動・移住に係わる研究を息長く緻密に続けた成果と、新たな研究の展開にチャレンジする内容となっている。
著者が論ずる前提は、東北アジア初期農耕化4段階説である。この仮説を第2章から第13章で詳細に実証する。第1段階はおおよそ紀元前3300年ごろの沿海州南部や韓半島南部へのアワ・キビ農耕伝播の時期で、土器様式の変化、華北型磨製石器、栽培植物で説明される補助的農耕段階であるという。第2段階はおおよそ紀元前2400年ごろ偏堡文化が遼東へと文化領域を広げると同時に、山東半島から遼東半島へ稲作農耕文化が伝播する時期であるとする。土器製作技法から見て、この偏堡文化の広がりこそが、韓半島における無文土器文化成立の直接の起原であると論じる。第3段階は紀元前1500年ごろ、山東半島東部から遼東半島・韓半島へ大陸系磨製石器などの農耕石器とともに、水田など本格的な灌漑農耕社会が波及する段階で、韓半島無文土器文化の時期とする。第4段階は紀元前8世紀ごろ、無文土器文化との接触の中、北部九州に灌漑農耕の弥生文化が成立する段階である。この成立過程を土器、石器、水田、墓葬、集落など考古学的で多面的な要素の分析から、実年代問題も加え実証的に研究している。
この実証的研究は、北部九州における文化伝播の要因と変容過程の実態だけでなく、福岡平野に生まれた板付土器様式の拡散による西日本の弥生文化の成立過程を明らかにし、その上で当初の東北アジア初期農耕化4段階説の実証から発展させ、理論的な展開を試みている。土器様式の拡散過程という考古学的事実が当時の社会のどの側面を示しているかを検討し、言語の拡散に対比することが可能であるかを第14章と第15章で論じている。
このように、日本考古学の重要な課題である弥生文化の起原、灌漑農耕文化・社会の起原と伝播についての関心を基層にして、考古学的な証拠に基づく東北アジア先史社会での農耕の伝播過程と拡散が、地域社会の変容に果たした役割を明らかにした成果と、それに基づく理論的な検討は、日本考古学協会大賞にふさわしい研究業績と評価できる。最終章の副題となっている「農耕の拡散と言語の拡散」は分野を超えてさらなる研究の深化が期待されるところである。
第9回日本考古学協会賞 奨励賞
高橋信武 著
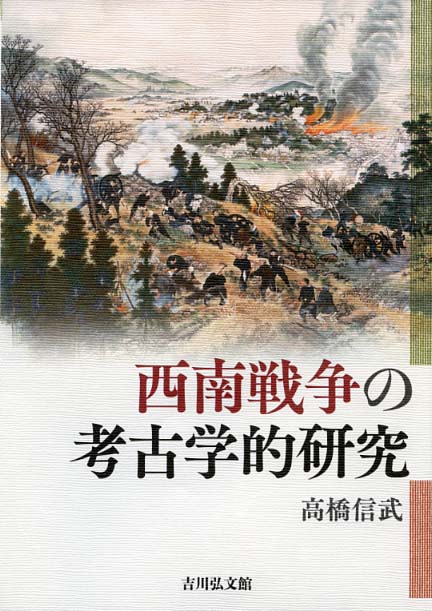 『西南戦争の考古学的研究』 吉川弘文館 2017年1月発行
『西南戦争の考古学的研究』 吉川弘文館 2017年1月発行
推薦文
本研究は、明治10年(1877)に熊本・宮崎・大分・鹿児島を戦場として西郷隆盛率いる薩摩軍(薩軍)と明治政府軍(官軍)が戦闘を繰り広げたわが国最後の内戦である西南戦争に関して、台場・塹壕などの戦跡(遺跡・遺構)や銃弾・薬莢・砲弾などの遺物による考古学的研究と史料(記録)との対比に基づき、実態を解明することを目的とする。
西南戦争は陸地戦であり、熊本鎮台が置かれた熊本城を巡る攻防を除けば、戦闘の大半は小銃類によって戦われた野戦であった。高橋氏は、大分県内を中心に野戦用に薩軍・官軍両陣営が築いた台場跡の踏査と略測を重ねるとともに、出土する小銃類の銃弾や薬莢類を検討することにより、実践的・簡易的台場周辺で行われた戦闘の具体的な姿と使われた小銃類の種類や銃弾の材質を明らかにすることに成功した。
特に発掘調査がなされた熊本県玉東町半高山では、先込め式のエンフィールド銃から発射された銃弾や捨てられた雷管、元込め式のスナイドル銃から発射された銃弾の出土位置から、両軍の配置と繰り広げられた戦闘の具体像を浮かび上がらせた。また大分と宮崎の県境に位置する椎葉山でも地形・遺構の測量と金属探知機による銃弾・薬莢類の検出により薩軍が大勝した戦闘に関して考古学的検討が行われた。こうした分析手法は、西南戦争の前年にカスター中佐率いる第七騎兵隊がインディアン部族同盟に大敗したモンタナ州リトル・ビックホーンの戦いに関するDouglas D. Scottの考古学的研究を彷彿とさせる。
本研究でもう一つ注目されるのが、戦跡や官軍墓地の出土資料に基づき、薩軍の使用した銃弾の製造法と材質の時間的変化を解明した点にある。薩軍も戦闘当初の2~4月には官軍と同じく鉛製銃弾を使用していたが、次第に鉛が不足し、5月以降は錫と鉛の合金弾、次いで錫・鉛・銅の合金弾、さらに7月頃には銅製銃弾、鉄製銃弾へと変化した。また、鉛弾や鉛の合金弾にはペンチ状の鋳造器が使われ、銅製や鉄製銃弾は枝銭状の鋳型造りであった。このような考古学的に導き出された事実は、薩軍が制海権を持っていなかったため鉛を輸入できなかったことや、西南戦争直前に明治政府によって行われた鹿児島属廠の弾薬製造機械解体・弾薬搬出という記録とうまく符合する。
近年、わが国でも近現代考古学が各地で試みられるようになり、そのなかでも戦跡考古学は大きなウエイトを占めている。本研究は、考古学が遺跡・遺構・遺物の分析を通して戦争そのものの本質や歴史的評価にせまることができることを示した点で、これまでの戦跡考古学とは一線を画するものと高く評価できよう。
本研究が戦跡考古学や近現代考古学の飛躍に繋がり、それによって改めて考古学の有効性が広く市民に認知されることを願うものである。
第9回日本考古学協会賞 奨励賞
中久保辰夫 著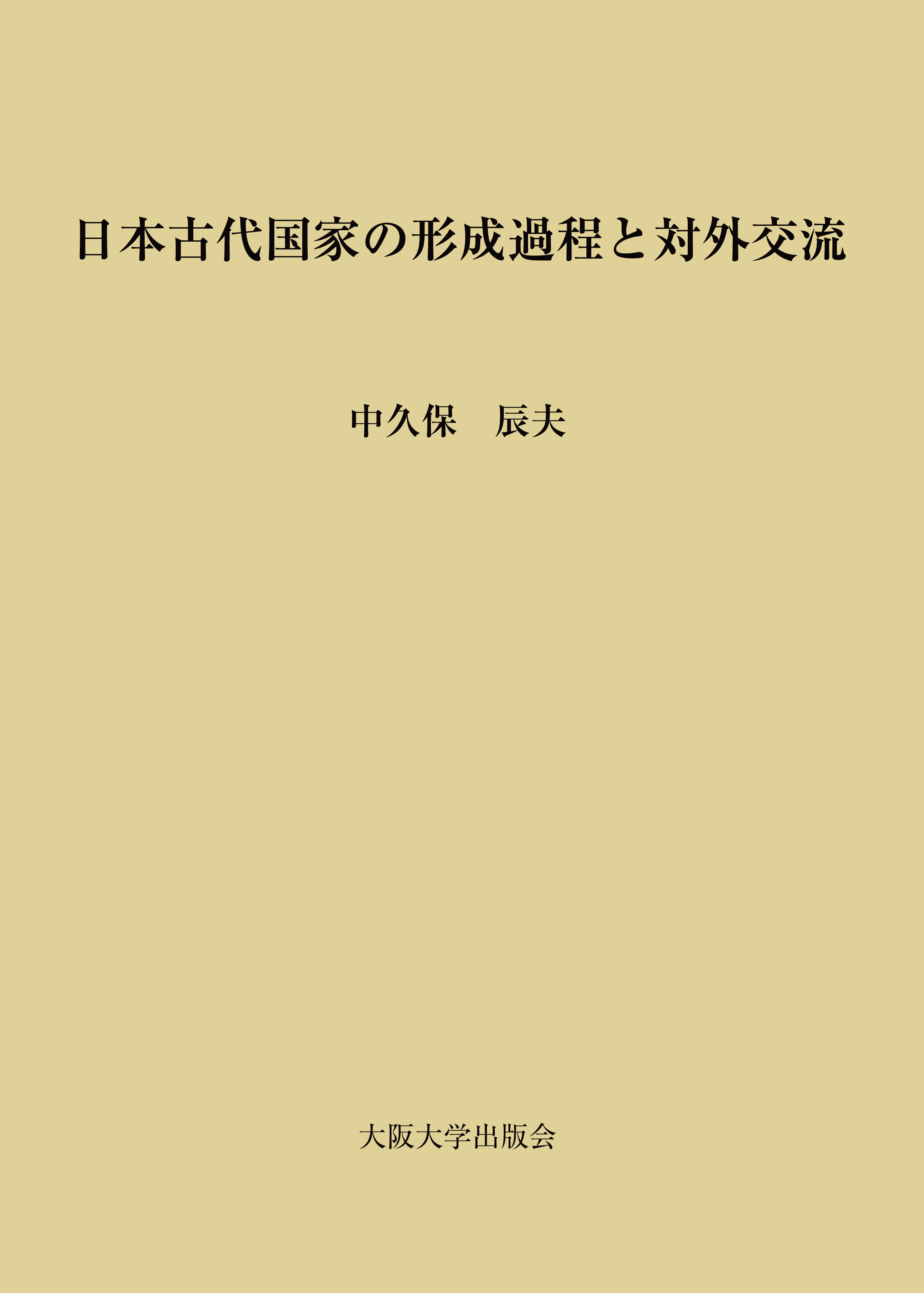
『日本古代国家の形成過程と対外交流』 大阪大学出版会 2017年3月発行
推薦文
古墳時代研究においては遺物論が優勢であり、これまでに青銅鏡、金銅製の装身具、刀剣・鉄鏃などの武器、甲冑・盛矢具などの武具、馬具、須恵器、埴輪などからアプローチが行われ、国家形成に論及する良質の業績が提示されてきた。それぞれの資料について、精緻な型式学的研究ならびに分布論を踏まえた議論が尽くされた観があるのが現状である。
しかしこうしたなかで、もっとも多量に出土し、各地に普遍的な遺物である「土師器」についての研究は、大きく立ち遅れた状況にあるといえる。実態的に各地の編年研究は進められているが、古式土師器研究が突出しており、須恵器出現期以降については土師器は2次的な位置づけに終始し、統合化が試行されているとは到底いえないのが実態である。本書は、そうした土師器の研究を基本にして、国家形成に関する所見をつみあげた労作であるといえる。
第1章では、土師器と、4世紀後半以降に土師器の様式構造に大きな影響を与えた韓式系軟質土器とを加えて、容量・使用痕跡の検討を行い、それぞれの機能差を論証するとともに、軟質土器の土師器化のプロセスから渡来人の在地への融合現象を説明した。第2章では、4世紀の西日本全体の集落変動から、交易ネットワークの転換を示唆し、北部九州の博多湾貿易から、漢城期百済との交渉開始にともなう軍事・産業・交通に関わる渡来人招致に推移したことを論じた。ここでは、土師器の小型丸底壺が全羅道地域の小型広口壺に影響を与え、日韓で有孔広口壺(ハゾウ)が連動して成立したことを漢城期百済と倭の関係形成の証拠として採用している。第3章では、韓式系土器の器種セットの在り方、その受容と型式変化から、渡来人の居住と存在形態を分析し、渡来系集団定着型集落と、在来集団主体型集落の存在を明確化した。第4章では、5世紀における渡来系技術を保持した複合工房群の開始や群集墳の展開を踏まえて、開発型新興勢力の台頭や初源的官僚層の出現を説き、河内政権の権力基盤を考察した。そして終章では、各章の成果を組み込みつつ、日本古代国家形成論の理論的展望に及んでいる。
このように本書は、最も基礎的でありながら等閑視されてきた土師器研究を、型式学のみならず機能論的視点から深化させ、粗削りな部分がありながらも古墳時代社会システム研究に高めた点が大いに評価される。また、今後の進展も大いに期待されることから、日本考古学協会奨励賞に推薦するものである。
第9回日本考古学協会賞 優秀論文賞
黒須亜希子 著
「木製『泥除』の再検討-弥生時代・古墳時の出土事例を中心として-」
『日本考古学』第43号 日本考古学協会 2017年5月発行
推薦文
弥生・古墳時代の木製品のなかでも複数の部位を組み合わせて使用する農具類は、いまだその機能や用法が不明なものが多い。そのような現状に対して、本論文は、直柄広鍬に組み合わせて使用する柄通し孔を有する板材、いわゆる泥除を類型化し、時代と地域ごとの基礎的整理をおこない、装着方法と使用状況を検討することを通して、近世以降にみられる民具とは異なる機能を有していた可能性を論じている。
まず、広鍬を11種、泥除を6種に細分し、それぞれの組み合わせを復原し、その初現期から紐緊縛による強固な結束がはかられていたことを指摘する。次に、その形態的変遷を辿り、強固な結合に加えて、広鍬刃先と泥除刃先の距離を縮めること、泥除の破損を防ぐことを理想として形態や固定方法が発展していったことを明らかにした。そして、弥生・古墳時代の泥除とは、単に泥飛散を回避するための防具ではなく、耕土を掻き取り、一律にまくばるという機能を有した部位であり、その役割は鉄製刃先が導入される過程で鉄刃付きナスビ形曲柄鋤と泥除付き横鍬に継承されていったと論じた。
以上の分析は、丁寧な遺物観察に基づく説得力のある復原案に立脚しており、木器研究のみならず、農具鉄器化や水田農耕の変遷にかんしても寄与する重要な成果を有する。これらの点をふまえ、本論文を優秀論文賞に相応しい研究として推薦するものである。
第9回日本考古学協会賞 優秀論文賞
田中 裕 著
「Progress in Land Transportation System as a Factor of the State Formation in Japan」
『Japanese Journal of Archaeology』第5巻第1号 日本考古学協会 2017年9月発行
推薦文
国家形成過程に関する従来の研究は、古墳の調査に基づいた社会関係からアプローチする論文が主流である。本論文は、交通システムの時間的変化に注目した初めての研究であり、それを国家形成過程論に絡めた点で大きな前進である。すなわち、弥生・古墳時代において、鉄器ないし鉄素材の入手が社会の死活問題であり続け、それは朝鮮半島南部から輸入しないといけなかったから、交通の確保に社会的関心が向いていた、とする。鉄素材等の重量物運搬においては、家畜と車の欠如という日本列島の文化的条件が、運搬経路を規定した。人力の「担ぐ」、「引きずる」という手段しか選択できない陸上と、「舟」を使用できる水上とでは、運搬力の差が歴然である。4世紀までの列島では、地域社会の組織化と地域間のネットワークが水上交通を重視する文化的環境の中で、複雑化・広域化が起こった。集落は水上交通に適した立地に集中し、首長墓である大型古墳は、中継点の中でも「交通手段の転換地点」に集中する。とりわけ4世紀の大型古墳は「最低限の陸越え」を必要とする地点、すなわち、緩やかな河川の最上流に多く立地するのが特徴である。一方、海上経由の場合、隣接地域を飛び越えた地点どうしが結合し、結果的に線状につながる点も、水上交通重視型ネットワークの特徴である。4世紀までの水上交通重視型ネットワークでは、鉄素材供給地に近く、島に囲まれた瀬戸内海を有する地勢条件の西日本に対し、供給地に遠く、高い山岳と広大な陸地からなる東日本では、運搬負荷が格段に高いため、ネットワークも限定的で、弱く間接的であった。この状況は、5世紀にヤマト王権が進めた馬の導入と普及によって大きく変化する。馬の運搬利用による陸上交通の革命的変化は、飛躍的な鉄素材の流入とともに地域社会の急速な変質をもたらしながら、山岳地帯の両側の地域社会や、分水嶺を挟んだ隣接する地域社会を急速に近づけ、ネットワークの面的発達を促す。加えて、「交通手段の転換地点」の移動に伴い、首長権の基盤と拠点も変わり、河川下流や平野の結節点を拠点とした新たな秩序のもとに、比較的広域で面的に束ねられた組織が生じる。陸上交通革命を主導したヤマト王権は、とりわけ内陸や遠隔地の熱烈な支持の元に、結果として東西1000kmにも及ぶ列島の東と西の各組織を結びつけることのできる、唯一の地位をほぼ確立したと結論付ける。
【第9回日本考古学協会賞選考委員会講評】
第9回協会賞の応募の業績についてみていくと、日本列島の考古学的課題を扱ったもの5件、列島外を扱ったもの5件、文化財関連の法律を扱ったもの1件であった。
列島を扱ったものの時代は、縄文時代、弥生時代、古墳時代、古代および近現代であり、旧石器時代、中世は、今回は応募がなかった。
列島外の具体的地域は、それぞれ東アジア、東南アジア、オセアニアであり、西アジア・エジプトや南北アメリカは0件である。西アジアについては、近年の政情不安が影響していると推察される。
応募の業績であるが、研究対象が列島内・外を問わず、はじめにグローバルな地域設定をし、それを絞り込んでコアな問題に迫る手法が共通している。具体的には、東アジア初期農耕社会のうちに日本列島を考える、同じく東アジアの初期農耕段階の石器を考える、さらに、東アジアの中での日本の国家形成期を検討する、東南アジアの交易圏の中での個別遺跡の役割を位置づける、などである。このことは、東アジアや東南アジアを対象とした研究において、研究者間交流を含むインターナショナルな研究状況が、我が国で醸成されていることの証左であると考える。
その他の研究であるが、日本近代における戦争を扱った研究は、精緻な遺物研究に基づいて展開されており、考古学の可能性を示すものと高い評価であった。
最後になるが、応募の業績には、「法」を扱ったものもあったことにも言及しておきたい。文化財保護法以下の関連法規を整理、さらに諸外国の法規を紹介したものである。考古学研究を推進する立場からも、遺跡・遺構・遺物を保護し活用する観点からも、「法」のありかたを議論することは必要である。その議論がここから始まればいいと考える。


