第15回日本考古学協会賞
第15回日本考古学協会賞
「第15回日本考古学協会賞」には、締切日までに7件の応募と1件の推薦がありました。2025年3月4日(火)に選考委員会が開催され、大賞には忍澤成視氏、奨励賞に青木 弘氏と古閑正浩氏、優秀論文賞にRoderick CAMPBELL氏がそれぞれ推薦され、3月22日(土)の理事会で承認されました。各賞は、5月24日(土)の第91回総会(筑波大学)において発表され、石川日出志会長から賞状と記念品が授与されました。なお、古閑正浩氏とRoderick CAMPBELL氏は当日欠席となったため、賞状と記念品は後日、個別送付させていただきました。
受賞理由並びに講評は、次のとおりです。
大賞
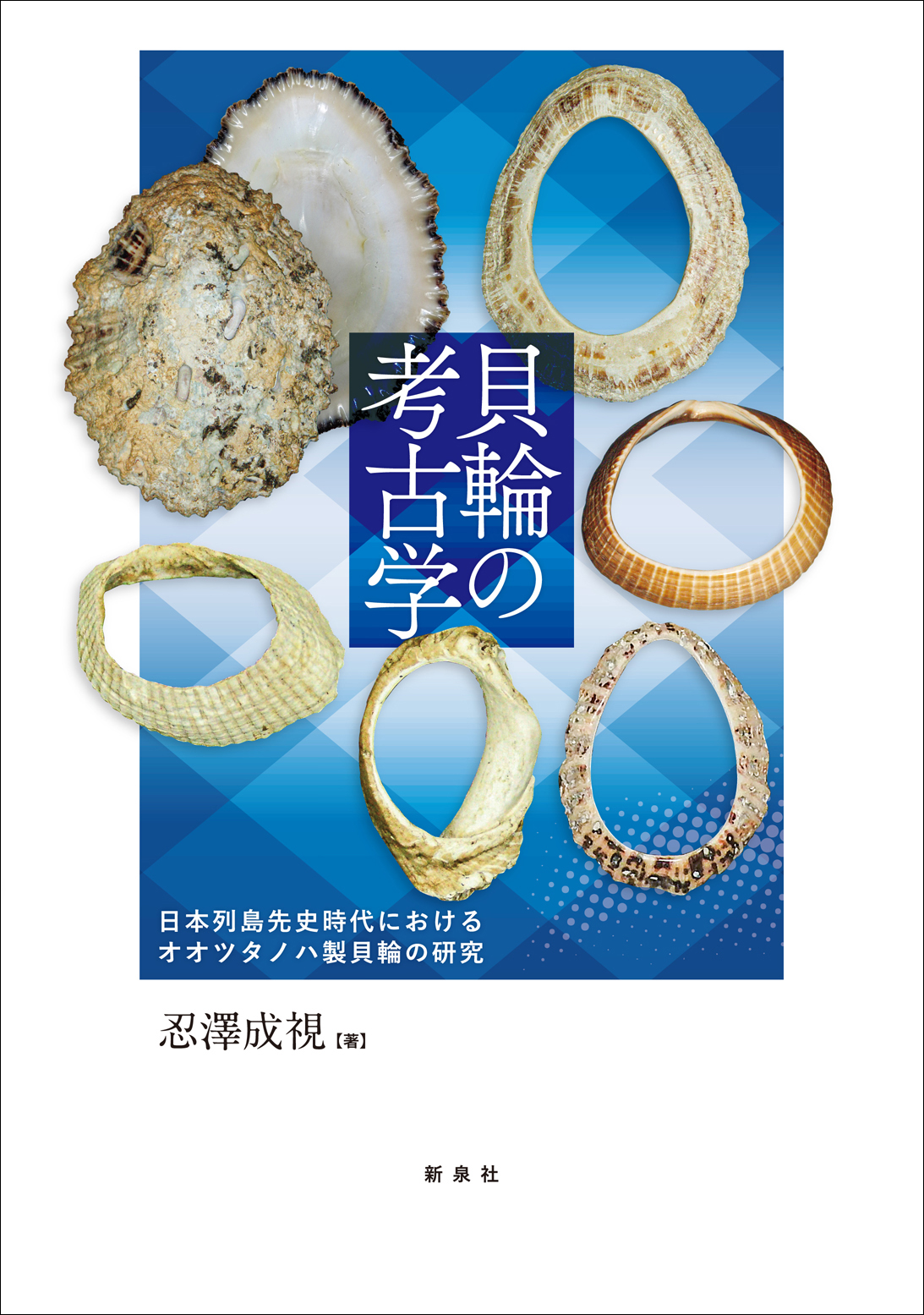
本書は、日本列島の縄文時代から古墳時代にかけての貝輪の生産と流通について、膨大な考古資料の丹念な検討と素材となる貝の入手方法について多角的な調査研究から明らかにした、著者の長年にわたる研究の集大成といえる著書である。
東日本の縄文から弥生時代、そして九州から南西諸島にかけての縄文時代から弥生・古墳時代の貝輪というほぼ日本全域の貝輪を対象としており、丹念な資料収集と詳細な分析が行われている。ベンケイガイについては、現生の打ち上げ貝を徹底的に採集し、貝輪と比較することで製作地と交易の実態を明らかにした点、オオツタノハについては島嶼部での時に危険を伴う採集活動や経年調査を通じて生産の実態を明らかにした点が、実証的かつ独創的な研究として際立っている。列島各所の島嶼部を20年以上にわたって単独調査した産地同定の記録は、臨場感があり圧巻である。実験考古学的手法による製作技法の復元も秀逸である。
縄文時代から古墳時代にかけて、長期にわたって威信財として用いられたオオツタノハについて、素材を得るには生きた貝を捕獲することが必要であることを実証し、その困難さから貝輪の価値生成の根幹に迫る議論はエキサイティングである。文章は平易で明快であり、多くの写真と図により理解が助けられる。これから考古学の道へと進もうとする後進たちへの羅針盤ともなるような一冊である。今後の基礎文献として学界に裨益するところが大きく、大賞にふさわしいと評価する。
奨励賞
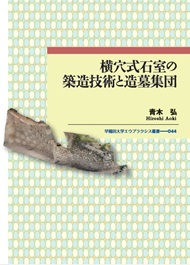
本書は、東国において展開した古墳時代後期から終末期の横穴式石室の構造分析による造墓集団の実態把握を目的としている。具体的には、従来の「実測」という手段では困難であった横穴式石室の立体構造を把握するために三次元計測とSfM/MVSという新たな調査方法、分析手法を用いて精密な情報にもとづいて立論し、主に北関東地域の特定石材を共有する横穴式石室の事例分析から、造営に携わった石工集団の動態について論じている。
特に本書で立論の根拠として用いられた三次元計測、SfM/MVSは、新たな記録保存手法として自治体で推進されてきたが、研究での実践例は限られている。その中で本書は、著者自身の調査で蓄積した基礎データの定量的分析によって企画諭や尺度論を独創的に展開し、先学による技術論、企画論の実証的な検証に成功している。その意味で、本書で三次元計測技術を採り入れた研究方法の利点や課題が示されたことは、今後のこの分野での研究実践に少なからず影響を与え、その活用、普及に大きな期待が寄せられる。
また、このようなデータ分析による成果を踏まえたうえで、実験考古学や民俗学の周辺学問領域の支援による中範囲理論にもとづく技術論的な事例分析も加味しながら、横穴式石室墳を造営した「造墓集団」とその「技術体系」や上位階層との関係性を含む「築造体制」を結論として論じた意欲作であった。ただし、本書での言及は利根川中流域に留まっており、列島規模での調査研究が望まれるなど、さらなる研究の進展が期待された。
以上、本書は三次元計測を基調とした新たな調査研究法を実践し、さらに石材を共有する石室構築集団の実態を地域社会のなかで位置づける新たな視点での事例分析に挑み、結論として東国での古墳時代後期から終末期における造墓集団の具体像を提示しており、その新規性、独創性とも次世代の研究を先導、牽引する業績として、奨励賞にふさわしい。
奨励賞
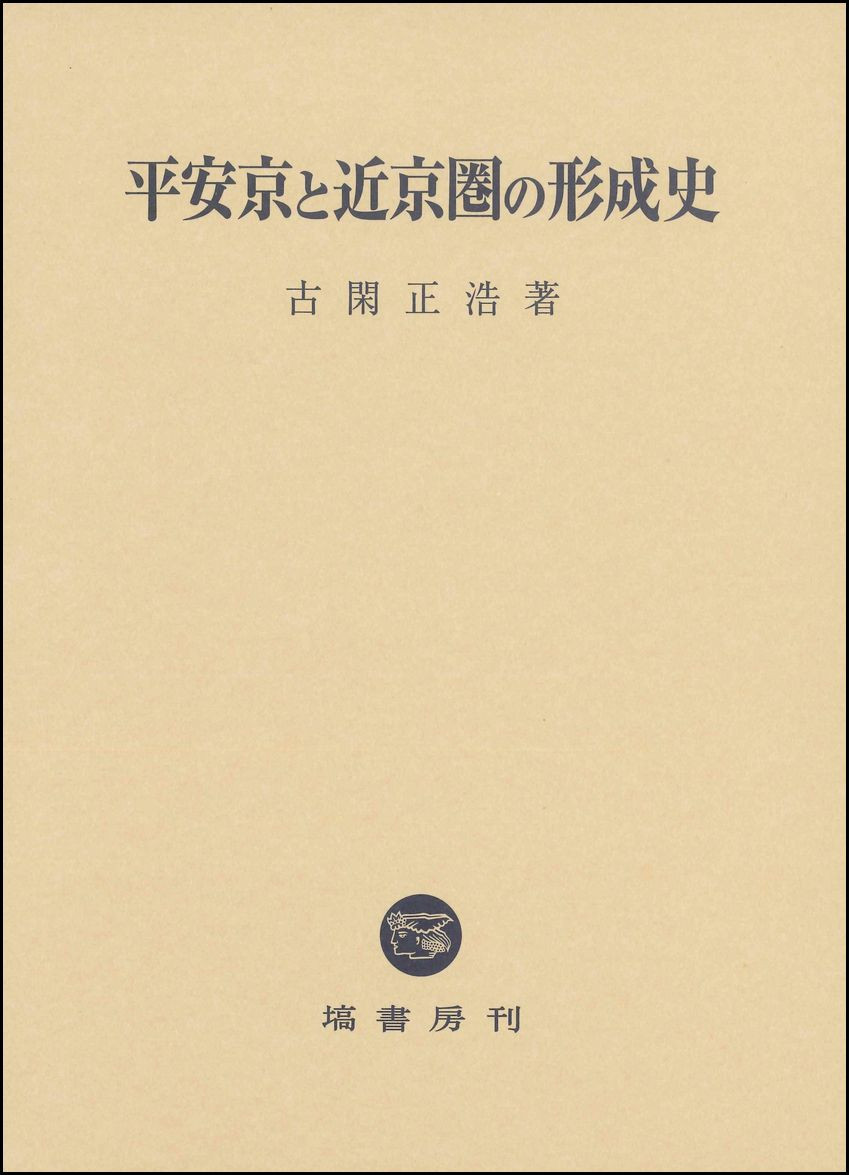
本書は、京都府立大学に提出された著者の博士学位請求論文を元とし、それに加筆修正を加えたものであり、A5版450ページの著書となっている。
古代都城の考古学的研究というとしばしば飛鳥・藤原の都や平城京が主体となるのと異なり、本書は長岡京と平安京を主に据えつつも、大きな視点からまとめあげていることに特質がある。
特に、長岡京と平安京の瓦について、瓦当文様の緻密で実証的な分析を中心に造瓦体制が質的に異なる点を明らかにしたことは注目されよう。さらに、長岡京から平安京の造瓦体制の変化を、都の造営目的や政治的課題を反映したものとの解釈は説得性に富んでいる。
本書が魅力的なのは、都城そのものだけでなく、その周囲の地域圏(「近京圏」)をも含めたダイナミックな都市論を展開している点である。例えば、長岡京や平安京の周辺の寺院群、京の外部に営まれた離宮と国府、都城から四方に向けて網の目のように張り巡らされた水陸の交通網、京の郊外の遊猟の地である「野」や「園」、さらには歴代天皇の山陵など多種多様の要素に着目した点は、著者の都城研究に独特の厚みを与えている。また、長岡京から平安京への遷都を、桓武朝の王権の永続性を求めたとする解釈は、独創的である。こうした桓武朝の造都が都城と近京圏を一体的に整備する事業であったことを明らかにした点も重要であろう。そして最終的には、著者のフィールドである「大山崎」(現・京都府乙訓郡大山崎町)に論をおよぼすことによって、中世都市としての京都とその近京圏への発展というところまで視野を広げている。
本書は今後も長岡京・平安京研究のみならず、日本古代都城史の基本的な業績として残るであろう。こうした点で、日本考古学協会の奨励賞に値すると評価したい。
優秀論文賞
Beyond State Formation: Mass Production and Commercialization in Shang China
『Japanese Journal of Archaeology』第11巻第1号 日本考古学協会
2023年11月発行 本論文は、従来の商代の政治経済や都市化、国家形成に関する理解を根本から再考し、新たな視点を提示する画期的な研究である。従来、商代の経済は国家による中央集権的な再分配モデルに基づくものとされてきた。しかし、キャンベル氏は、安陽を中心とする商代の経済が高度に商業化されており、大量生産や産業の専門化、地域間の経済ネットワークが政治経済と都市化の発展に密接に関連していたことを明らかにした。
特に注目すべきは、安陽における大規模な骨器製作工房に関する研究である。これらの工房では、髪留めなどの高付加価値製品が大量生産され、安陽を超えて広範囲に流通していた。この事実は、商代において市場や商人が存在し、水平的な経済交流が広がっていた可能性を示唆している。また、青銅器の生産が複数の工房で行われていたことや、原材料の供給元が分散していたことからも、経済活動が必ずしも中央集権的ではなかったことが分かる。これらの発見は、政治的支配層による消費にとどまらず、商業的利益を追求する行動が経済発展の主要な要因であった可能性を示している。
本論文ではまた、商代の都市化が、政治的・儀礼的機能だけでなく、工芸品の生産や経済活動の中心地としての役割を果たしていたことを強調している。このような都市と商業化、工芸生産の相互関係が発展することで、政治権力や産業基盤が強化され、都市規模の拡大や経済の深化がもたらされた。これらの過程は、後の東周時代や初期帝国の経済繁栄の基盤となるものである。
キャンベル氏の研究は、これまでの国家形成論や経済モデルを超えた新たな視座を提示し、商代の政治経済と都市化、商業化の複雑な相互作用を解明している。その独創的で精緻な分析は、後続の研究に大きな影響を与えることが期待されるものであり、このような論考が日本考古学協会の英文機関誌に掲載されたことは、その意義を顕著に高らしめるものである。
日本考古学協会賞選考委員会講評
第15回協会賞選考委員会を2025年3月4日(火)にオンライン形式で開催した。本年度の応募は7本であった。一昨年度の応募が3本、昨年度が6本であったので引き続き微増傾向にあるが、それ以前は10本ほどの応募数が常態であったことを考えれば、推移を見守るとともに、場合によってはなんらかの対策が必要であろう。
応募者は、60歳代が1名、50歳代が3名、40歳代が1名、30歳代が2名であり、大学准教授1名、大学非常勤講師1名、公的研究所職員1名、行政職員4名であった。若い方の応募が多いのは望ましいが、研究を専門の職業とするアカデミズムに籍を置く研究者のさらなる奮闘を期待したい。
応募の対象となった業績は、朝鮮半島をも対象にした1本を含めていずれも日本を主たる対象としたものである。時代別では、旧石器時代1本、縄文時代1本、縄文~古墳時代1本、弥生~古墳時代1本、古墳時代1本、律令期2本であった。幅広い時代に及ぶ領域の広がりと、近年乏しかった律令期の業績が2本提出されたのは喜ばしいが、国際的な視野からの研究による応募が乏しかったのは残念である。
とはいえ、候補作はいずれも大著・力作であり、努力のほどが偲ばれるものばかりであった。型式学的な研究を徹底的に推し進めた研究、新規の分析手法をベースにしたもの、長年の地道な研究をまとめたもの、特定の遺物を通時的かつ汎列島的に分析したものや地域史の労作など、アプローチの方法や視点は多彩であり甲乙をつけがたく、選考に苦労した。
今回の大賞候補の業績は、日本の先史時代を中心とした貝輪の研究である。東日本における縄文時代から弥生時代、九州から南西諸島における縄文時代から弥生・古墳時代という広域にわたり、貝輪の生産と流通を研究した。ベンケイガイなどの現生の打ち上げ貝を徹底的に採集して原材獲得の実態を解明したことや、これまで不明瞭であったオオツタノハの南西諸島以外の原産地を求めて、時に非常な困難を伴う島嶼部での採集活動を通じて生産の実態を明らかにしようという試みは、実証的で独創的な研究としてすぐれている。縄文時代の貝輪についての体系的な書籍は初めてであり、学界に裨益するところ大である。方法論の妥当性や実証的で緻密かつ明晰な分析、よどみのない文章などが評価され、委員全員が大賞候補に推薦した。
今回の奨励賞候補は、横穴式石室の研究と平安京の研究の2本である。横穴式石室の研究で優れているのは、三次元計測とSfM/MVSという新たな調査方法を用いた実測調査によって、精密な情報を立論の基礎データにしている新規性と正確性である。規格論や尺度論という定量的な分析も独創的で、横穴式石室古墳の「造墓集団」とその「技術体系」や上位階層との関係性を含む「築造体制」を明らかにしようとした意欲作である。平安京の研究は、瓦当の精緻な型式学的研究により長岡京から平安京への造瓦体制の変化を跡づけ、それを基礎にして平安京への遷都が桓武朝の王権永続の追求にあるとの独創的な見解を導いた。また、平安京の整備が周辺の近京圏と一体的におこなわれたことを明らかにした点ですぐれている。いずれも今後に研究の発展が期待できる業績であることから、委員全員が奨励賞に推薦した。
なお、邦文誌の優秀論文賞に関しては、『日本考古学』編集委員会の推薦は見送られ、英文誌の優秀論文賞についてはJJA編集委員会の推薦により1件の受賞候補を決めた。継続的な論文賞対象者確保のために、会員には奮って機関誌への論文投稿をお願いしたい。