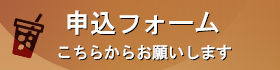カフェ de 考古学 2023「考古学 今とこれから」
「カフェ de 考古学」は、市民のみなさんと考古学の研究者が、カフェでコーヒーを飲みながらおしゃべりするような雰囲気で考古学のさまざまな話題について気軽に語り合う場です。どなたでも参加できますので、この機会にふるってご参加ください。
日 時:2023年4月~2024年2月 偶数月の第2土曜日 14:00~16:00
会 場:Zoomによるオンライン開催
主 催:一般社団法人日本考古学協会
対 象:どなたでも
定 員:各回ごとに異なります。なお、当協会賛助会員の方は定員とは別枠でご参加いただけます。
参加費:無料
参加方法:新型コロナウイルス感染症の流行に配慮して、当面はZoomアプリを使ってオンラインで行います。Zoomアプリが使えるように準備しておいてください。
プログラム:話題提供1時間+フリートーク1時間程度ですが、各回ごとに異なります。
お申込み:下部の申込みフォームから各回ごとにお申し込みください。おってZoomのURLをお知らせいたします。
*各回、開催日1ヶ月程度前にお申込みを開始します。
第6回 2024年2月10日(土) 定員100名に拡大
「近年の災害と埋蔵文化財について」 講師:杉井 健(熊本大学)・菊地芳朗(福島大学)
近年は災害が多発しており、人命だけでなく様々なインフラが被害を受けています。その被害の中には、遺跡や遺物をはじめとする埋蔵文化財も被災しています。今回は、東日本大震災や、熊本地震、各地の豪雨災害をはじめとする様々な近年の災害と埋蔵文化財の被災状況をご報告しながら、参加者との意見交換を行います。(災害対応委員会担当)
【速報:能登半島地震】
*石川県下の会員のご協力を得て、2024年1月1日に発生した令和6年(2024年)能登半島地震における文化財被害の状況を広く共有し、現状の課題や今後何をすべきなのかなどについて、意見交換をいたします。
◆2023年度開催予定◆
第1回 4月8日(土) 定員100名
「近現代遺跡をどう守り伝えるのか」 埋蔵文化財保護対策委員会ミニシンポジウム
終了しました。
第2回 6月10日(土) 定員100名
「オリエント考古学の現在」 講師:足立拓朗・小髙敬寛・河合 望(金沢大学) 進行:小澤正人(成城大学)
協力:金沢大学古代文明・文化資源学研究所
終了しました
第3回 8月12日(土) 定員100名
「三角縁神獣鏡の研究とその意義」 講師:岩本 崇(島根大学) 進行:澤田秀実(くらしき作陽大学)
終了しました
第4回 10月14日(土) 定員100名
「考古学の仕事場から パート2博物館編」 進行:森原明廣(山梨県立博物館)・日高 慎(東京学芸大学)
終了しました
第5回 12月9日(土) 定員100名
「みんなで巡る旧石器時代全国遺跡ツアー」 進行:大竹幸恵(黒耀石体験ミュージアム)・小菅将夫(岩宿博物館)
終了しました