埋文委 第7号
2013年1月28日
文化庁長官 近 藤 誠 一 様
和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 様
和歌山県教育長 西 下 博 通 様
岩出市長 中 芝 正 幸 様
岩出市教育長 松 永 宣 詔 様
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 矢島國雄
国史跡根来寺遺跡関連遺構の保存に関する要望について
標記の件について、2012年2月2日付埋文委第6号におきまして、旧和歌山県会議事堂である一乗閣移築予定地内で検出された坊院遺構の保存と活用に係る再要望を提出いたしましたが、これに対するご回答を未だに頂戴いたしておりません。
日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会といたしましては、遺跡の重要性に鑑みて、別添書類の如く、国史跡である根来寺遺跡の保護・活用と歴史的環境の保護・保全対策を速やかに講ぜられますよう改めて要望いたします。
なお、恐縮ですが、当件の具体的な措置等については2月15日(金)までに、ご回答を下さるようお願いいたします。
記
一、別添書類 一通
以上
埋文委 第7号
2013年1月28日
文化庁長官 近藤 誠一 様
和歌山県知事 仁坂 吉伸 様
和歌山県教育長 西下 博通 様
岩出市長 中芝 正幸 様
岩出市教育長 松永 宣詔 様
和歌山県議会議長 山下 直也 様(参考送付)
新義真言宗総本山根来寺 座主 関根 眞教 様(参考送付)
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 矢島 國雄
国史跡根来寺遺跡関連遺構の保存に関する要望書
2011年に一乗閣移転予定地において実施された根来寺遺跡の発掘調査については、石階や井戸、石組排水溝、地下式倉庫など、戦国時代の根来寺に関わる遺構が多数検出されています。これらの遺構は、調査地が根来寺寺域内への西側の導線に位置する点を勘案した場合、非常に重要な意味を持つと考えられます。
また、隣接する大規模農道の調査では、根来寺の子院に関わる遺構が三段の造成面から検出されており、調査地周辺には根来寺関係の遺構が稠密に遺存する可能性が強いものといえます。なお、この点は和歌山県文化財センターが「遺構の残存は想定できない」とした蓮華谷川西の丘陵上も同様であり(試掘Aトレンチ配置部分)、当委員会では当該部分についても地下遺構が存在する可能性があるという認識を有しております。
こうした状況に鑑み、当委員会では2011年8月3日付け埋文委第2号で検出遺構の保存措置などに関わる要望書を提出し、同年8月26日付け文第382号で和歌山県教育委員会よりご回答いただいたところです。
当委員会では回答文書の内容を検討した上で、2012年2月2日付け埋文委第6号で再度要望書を提出し、一乗閣移転の中止、もしくは地下遺構保全の具体的方法等についての回答を要望いたしましたが、2013年1月26日現在、未だ貴委員会からの文書でのご回答をいただいておりません。
この間、昨年6月には当委員会による現地視察および面談が実施され、発掘調査報告書も刊行されました。当委員会では、それらの検討結果を踏まえ、埋蔵文化財保護の理念から改めて以下の要望を行います。
本件につき、貴委員会からの誠意あるご回答をお願い申し上げます。
記
一乗閣の移築は根来寺遺跡に関わる地下遺構を破壊する恐れが強いので、中止することを強く要望する。また、移転を実施する場合には、地下遺構の具体的な保全方法について示すこと。
当該地を含めた根来寺遺跡全体について、史跡範囲の拡大など包括的展望に立った保存・整備・活用方針を示すこと。
以上
4つのテーマからみる研究環境の問題点
埋文委 第6号
2012年12月21日
文化庁長官 近藤 誠一 様
青森県知事 三村 申吾 様
青森県教育長 橋本 都 様
五所川原市長 平山 誠敏 様
五所川原市教育長 長尾 孝紀 様
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 矢島 國雄
五所川原市五月女萢遺跡の保存に関する要望について
標記の件について、別添書類の如く、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容をもつものでありますので、貴殿において、適切な保存の対策が速やかに講じられることを要望いたします。
なお、当件の具体的な措置、対策については、2013年1月18日(金)までに、ご回答をくださるようお願いいたします。
埋文委 第6号
2012年12月21日
文化庁長官 近藤 誠一 様
青森県知事 三村 申吾 様
青森県教育長 橋本 都 様
五所川原市長 平山 誠敏 様
五所川原市教育長 長尾 孝紀 様
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 矢島 國雄
五所川原市五月女萢遺跡の保存に関する要望書
青森県五所川原市の五月女萢遺跡は、土砂採取事業にともない、平成22年度から五所川原市教育委員会により発掘調査が行われ、縄文時代後期後葉から晩期の大規模な集団墓地や平安時代の畑跡が、砂丘砂に保護され非常に良好な状態で発見されました。
縄文時代の大型環状土坑墓群は、その多くに盛土(マウンド)が良好な状態で残る全国でも稀有な遺構で、縄文時代の墓地景観を考える上で重要な発見といえます。そのほかにも、貝塚をともなう大規模な捨て場をはじめ、大型掘立柱建物跡、柵木列、道路状遺構、祭祀場と考えられる集石遺構などが発見されており、縄文時代の集落構造が良くわかる遺跡です。捨て場からは土器や土偶をはじめ縄文晩期(亀ヶ岡文化期)の遺物が、層位的に多量に出土しており、その量や内容の豊かさは、目を見張るものがあります。墓からは人骨やベンガラ(赤色顔料)に加え、ヒスイをはじめとする玉類・サメの歯の装飾品・土製耳飾といった死者が身につけていた装身具が多数発見されており、今後それらを分析することで、縄文時代の社会組織の解明が期待できます。
また、白頭山火山灰の直上から発見された大規模な平安時代の畑跡は、古代の蝦夷の生業を知る重要な手がかりとなるものです。
北海道・北東北3県に所在する「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」がユネスコの暫定リストに記載され世界遺産登録を目指した活動が行われている現在、特別史跡三内丸山遺跡のある青森県は、縄文に対する市民の関心がとりわけ高い地域といえます。さらに全国的に有名なつがる市亀ヶ岡遺跡とは同時代の遺跡であり、距離も近いことから、両遺跡の保存・活用を連携させることも考えられます。
以上のように、五月女萢遺跡の学術的重要性に鑑み、日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、下記のとおり要望いたします。
記
五月女萢遺跡を土砂採取事業から守り保存するための措置を早急に講じるとともに、既に調査で検出された遺構群については、損壊することのないよう保全に万全を期すること。
本遺跡の史跡指定を含めた、保存のための態勢を整備していくこと。
将来に向けての本遺跡の活用のあり方について、周辺の遺跡との一体的な取り組みを含め、包括的な検討を行うこと。
以上
埋文委 第5号
2012年11月5日
文化庁長官 近藤 誠一 様
静岡県知事 川勝 平太 様
静岡県教育長 安倍 徹 様
沼津市長 栗原 裕康 様
沼津市教育長 工藤 達朗 様
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 矢島 國雄
沼津市高尾山古墳の保存に関する要望について
標記の件について、別添書類の如く、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容をもつものでありますので、貴殿において、その保存の対策を速やかに講ぜられることを要望いたします。
なお、当件の具体的な措置、対策については2012年11月22日(木)までに、ご回答をくださるようお願いいたします。
記
一、別添書類 一通
以上
埋文委 第5号
2012年11月5日
文化庁長官 近藤 誠一 様
静岡県知事 川勝 平太 様
静岡県教育長 安倍 徹 様
沼津市長 栗原 裕康 様
沼津市教育長 工藤 達朗 様
沼津市議会議長 城内 務 様(参考送付)
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 矢島 國雄
沼津市高尾山古墳の保存に関する要望書
静岡県沼津市に所在する高尾山古墳は、駿河湾東岸の愛鷹山裾野の丘陵上にあり、その西側に浮島ヶ原と呼ばれる広大な沼地が広がり、南に駿河湾を見下ろす場所にあります。近年実施された沼津市の発掘調査により、3世紀前半に築造された日本最古級の前方後方墳であることが判明しました。古墳の規模は、墳丘長62mを超え、古墳が創出された段階にいちはやく大型古墳の築かれていたことがわかります。また、古墳に伴う主体部は朱の敷かれた木棺で、内部から青銅器、鉄槍、鉄鏃、ヤリガンナ、勾玉などの比較的豊富な遺物が出土しています。
このように、古墳の規模や出土品から、駿河地域では、すでに3世紀前半代に王としての権力者の存在が窺われます。とくに、注目されるのは弥生時代の社会構造を一変させる出土品の登場であり、社会の大きな変動を反映しています。同時に、出土した土器から北陸、近江、東海西部の各地域の勢力の関与が窺われ、被葬者との同盟関係も想定されます。
当時の政治の中心地として考えられている北九州や畿内だけではなく、東海地方の駿河においても強大な権力をもつ地域首長の誕生が想定され、各地域が関連する国家出現の実態をよく表しています。また、日本における国家の形成を解明する上でも、貴重な古墳であると言えます。さらに、古墳の立地が水路と陸路を繋ぐ交通の要衝に存在することから、水上交通等に関わる地域首長の性格を窺わせるものとなっており、高尾山古墳の学術的な重要性の高さを物語っています。
ところが、高尾山古墳の全域が沼津市の計画する都市計画道路沼津一色線道路の改良工事の事業地内にあることから、今後、道路工事が予定通り実施された場合、当該古墳の消滅が危惧されます。この古墳が消失することは、沼津市民ばかりでなく日本国民にとっても大きな損失であり、私たちは国民共有の財産として、学術的にも高く評価される歴史的遺産としての高尾山古墳を恒久的に残していかなければなりません。
以上のことから、日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は埋蔵文化財の保護と活用の観点から、下記の通り要望いたします。
記
- 地域のかけがえのない文化財である高尾山古墳を都市整備計画の文化的側面を担うおおきな要素と位置づけ、国民の歴史的・文化的遺産として保護し、将来に向けてその保存と活用を図ること。
- 高尾山古墳に係る道路工事計画を抜本的に見直し、古墳を現状保存するための早急な保全対策等を講じること。
高尾山古墳から出土した貴重な出土品については、古墳の年代と古墳に埋葬された者の性格を規定するものであることから、その学術的な調査成果を含めて、広く公開するよう適切な措置を講じること。
以上
歴史教科書を考える 第8号
2012.5.26 日本考古学協会 社会科・歴史教科書等検討委員会
1.中学校社会科(歴史)教科書を考える
社会科・歴史教科書等検討委員会は、主に学校教育現場の歴史教育において、考古学研究の成果が十分に活用されるよう、その基礎となる教科書の内容や、教科書の編集方針を大きく左右する学習指導要領の動向について分析を行っている。これまで委員会発足の契機となった、小学校第6学年の教科書から、その取り扱いが消えた旧石器・縄文時代の記述の復活を目指し、2008年度の学習指導要領改訂に向けて、文部科学省に声明文を提出し、あわせてテーマセッションやポスターセッションの場を通じて、教科書に反映されている歴史教育の現状と課題を学会や広く社会に伝えてきた。
こうした取り組みは小学校の教育現場に限らず、歴史教育全体の問題として位置づけ、中学校から高等学校へと分析・研究の対象を広げていく必要があり、2011年総大会のテーマセッションで行った高等学校の事例報告、パネルディスカッションにおける討論では、今後の委員会活動として対象を中・高に拡大し、一貫した歴史教育のあり方について検討していく必要性を再確認した。
そこで、2012年度は、中学校の学習指導要領と改訂された教科書の内容について分析を続け、様々な課題の改善に向けて活動を継続していく考えである。
○中学校学習指導要領の改訂と問題点
中学校の学習指導要領は、2012年度からの全面的実施を目標として2008年に改訂版が告示された。各教科とも授業時間数が大幅に増えるため、移行措置として2009年度から授業時間数の調整や教科書にまだ記載されていない内容を補うなどの段階的な先行実施がなされている。
授業時間数に関わる改訂内容としては、これまで1・2年生が地理と歴史を並行して学び、歴史の時間数が105時間であったのに対し、新しい学習指導要領では130時間となり、1・2年生が地理と歴史を並行して学ぶ点は同じであるが、3年生の選択社会科が廃止となり近・現代史の歴史と公民を学習することとなった。
中学校における歴史学習の授業時間数は、1969年版の学習指導要領で175時間、1977年度版が140時間、そして、1998年度版が105時間と削減され続けてきたが、各教科とも基礎的な学力の低下が問題とされ、今回の授業時間数の増加になったといわれている。
では、社会科全体、および歴史的分野の学習目標に掲げられている内容についてはどうであろうか。
今回の新しい学習指導要領の記載内容と1998年版を比較した場合、全体の目標内容に大きな差は認められない。しかし、取り扱う内容においては、「(2)古代までの日本」に「日本列島で狩猟・採集を行っていた人々の生活が農耕の広まりとともに変化していったことを理解させる。」とあったのが、改訂版では「日本列島における農耕の広まりと生活の変化や当時の信仰、…」と変わっており、小学校の学習指導要領で改善が図られたことと逆行した記述になっていることなどが懸念される。詳細については、この二つの学習指導要領のみで判断するのではなく、過去の学習指導要領の全てを比較検討し、その課題の所在について精査していくべきであると考えている。
○中学校の教科書について
新しい学習指導要領にむけて、現在7社から検定済みの歴史教科書が発行されている。各教科書の分析に着手したばかりであるが、小学校との比較では、教科の専門が授業に当たることもあり、学習指導要領において課題とされる点を補う配慮がみられる。
例えば、学習指導要領では、その取り扱いが位置づけられていない続縄文文化や擦文文化の時代、貝塚文化の時代について、7社の教科書の内4社にその記載が認められる。また、小・中ともに学習指導要領では「大和朝廷」となっている用語に対し、中学校の教科書では、5社の教科書が「大和政権」「大和(ヤマト)王権」という名称を用いている点などである。この用語については、学問的に後者が妥当であり、各教科の専門家が授業を行うという制度の違いが、教科書の編集にも大きく反映されているといえよう。
取り扱う内容も、段階的により豊富となっているが、その反面で新たな課題も認められる。中学校では、世界史の部分ではじめて子ども達が旧石器時代について学習するようになる。しかし、その内容としては、小学校の段階での位置づけがないまま導入されていることもあり、内容も乏しく、世界と日本列島との関係は明確に示されているとはいえない。また、縄文時代以降の記述の内容に関しても、依然として社会や生活史としての全体像を捉えるものではなく、取り扱い方や情報量、そして先に上げた用語の不統一など、教科書間で大きな偏りが認められる。おなじ検定本として教科書の内容が大きく異なる点については、学習指導要領の改訂に伴って同様な問題が生じている小学校の教科書と共に検討を重ねる必要がある。
「新学習指導要領」は、小・中学校ともに「脱ゆとり教育」「教科書・教える内容の増」といった面だけが注目されている。しかし、本委員会では、より具体的に検証を重ねながらその課題の所在を明確にし、義務教育全体を通しての改善の方向性について提案をしていきたいと考えている。
2.今後の活動目標
教科書等検討委員会では、2013年度第79回総会の参加に向けて、取り組む主なテーマを次の①~④とし、短期活動目標とする。
①中学校の新しい教科書問題について
2012年以降、本格的に取り組む中学校教科書の分析を通して、委員会としての取り扱いの方向性を探る。このたびのポスターセッションでは、2012年度4月から本格的に実施される中学校教育の新学習指導要領の内容、および、改訂に伴う中学校の新しい社会科(歴史)教科書7社分の内容について分析し、現状と課題を提示する。
②古代以降における考古学の取り扱いについて
これまで、旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代を対象として教科書の分析を行ってきたが、今後は古代以降の内容についても小・中学校の教科書で分析を進めていく。
③義務教育段階における歴史教育の課題
小学校から中学校へと、これまでの分析を通して、どの様な一貫性をもって義務教育段階の歴史教育が行われているかを検証し、その課題について考える。
④教科書における旧石器時代の掲載に向けて
学習指導要領改訂に向けて、再度、文部科学省に声明・要望等を提出する。とくに、旧石器時代の取り扱いについては、継続的に働きかけることが重要であり、2012年度からその方法等について検討する。
これら①から④の活動目標を達成し、中期活動目標とスケジュールとして、小委員会発足から2013年度まで取り組んできた教科書委員会活動の成果をまとめ、2014年度に対外的なシンポジウムの開催や記録冊子の刊行を行う。
また、短期目標の④で掲げた、旧石器時代の取り扱いについては、中期的目標としても活動を継続していく予定である。
3.教科書委員会の新体制について
日本考古学協会における各委員会は、2年3期内が委員の継続任期となっている。2008(平成20)年度より常置委員会として再スタートした教科書等検討委員会では、3期目を迎えるに当たって、これまでの活動や情報を継承するために、任期内における各委員の退任時期と委員の交替について検討・調整し、2012年度からの新規委員を公募することとした(会報№175)。
その結果、学校教育に造詣の深い6名の協会員の申し込みをいただき、申請者全員の委員会参入を教科書委員会の要望として理事会に提案することとした。
この委員会要望は、5月の理事会において承認を得ることができたが、2012年度以降は、委員長1名、副委員長1名、事務局2名、担当理事2名を含む委員8名の計12名による新体制で活動を進めていく予定である。
教科書委員会としては、例年の総・大会において継続的に活動内容や教科書問題の課題について広く公開することを活動の基本目標としている。予算上、全体会議の開催は年4回程度に限定されるため、教科書の分析や情報の収集等については、各委員が分担する形で地道な活動を続けている。
今後の委員会体制としては、より多くの方々と情報を共有するためのネットワークづくりが活動方法の課題とされるが、協会員各位の協力と支援を求めていきたい。
第3回日本考古学協会賞は、昨年の10件に対して4件の応募と少数でした。2013年2月14日(木)に選考委員会が開催されて、日本考古学協会大賞に東村純子氏の『考古学からみた古代日本の紡織』、奨励賞に小畑弘己氏の『東北アジア古民族植物学と縄文農耕』が推薦され、2014年3月23日の理事会において報告、第79回総会において承認され、田中良之会長から各受賞に賞状と記念品が授与されました。
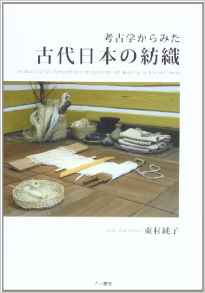
本書は、糸づくりから布が織り上がるまでに必要となる各種の紡織具について、出土遺物によりながらその用途や機能を明らかにし、その分析にもとづいて弥生時代~律令時代にいたる紡織技術の変化、律令国家成立期の生産体制の特徴について検討したものである。これまで弥生~古墳時代の直状式原始機の経巻具ないし布巻具とされていた木製品を、形態的特徴と出土状況や民族資料との比較によって輪状式原始機を構成する布送り具であることを突き止め、さらに輪状式原始機の系譜を広く東アジアに求めて、弥生文化の紡織技術の復元に一石を投じた。また、律令体制下における織物生産の具体相について、地方官衙と一般集落を基軸に検討をくわえ、製糸と製織の分業体制の成立や実態の解明、糸の流通形態の復元といった実証的な研究成果を導いた。
本書は、日本古代紡織技術の復元的研究として完成度の高い一書であり、当該期の生活と文化を考えるうえで不可欠の書物である。選考委員会は、本書を日本考古学協会大賞候補として推薦する。

本書は、縄文時代にみられる非栽培植物のドングリを扱っている部分もあるが、多くは栽培植物としてのオオムギ・コムギ・ダイズ・アズキなどについて、フローテーション法と土器圧痕レプリカ法で得た資料を活用し、詳細に検討している。ことにダイズとアズキについて、その起源地の1つとして縄文時代中期の中部地方や西関東である可能性を提唱している。その提唱に当って、琉球を含めた日本国内の資料にとどまらず、中国・朝鮮・モンゴル・シベリアなど、東アジアの全体およびその周辺に視野を広げて調査を実践し、それを実証している。また、直接植物資料を論ずるのみではなく、縄文時代のコクゾウムシを取り上げ、それがクリや堅果類でも繁殖することを明らかにして、コクゾウムシ遺存体の存在をもって縄文時代の稲作を論ずることの危険性に警鐘を鳴らしている点は、稲作伝来期の考察に関する重要な指摘である。このような小畑氏の研究法は、ロシア極東の沿海州における農耕化の過程を論じるなど、地域性や時代にとらわれるところがなく、今後の植生や植物質食材の研究に大きく貢献すると評価できる。
本書は著述のスタイルにも特徴がある。普通、本文の補足として付けたり的に書かれたコラムを冒頭に置き、その軽妙な語りでまず読み手の関心を惹きつける努力がされている。そこにこの著書への親しみが生じ、実際、少なくとも九州の発掘現場では植物質遺物の検出および分析においてバイブル的な扱いを受けている。今後の考古学研究の発展への寄与が日本考古学協会賞の大きな目的であり、本書はすでにその効果を発揮してきている。
ただ、研究の現段階ではダイズ・アズキなどのマメ類やムギ類を中心にしているため、東アジアに広くみられるアワ・ヒエの検討など重要な課題が残されている。その点が今後の課題であるとともに、今後の研究に大きな進展が望めるところから、本書を日本考古学協会奨励賞として推薦する。
第2回日本考古学協会賞は、昨年度の5件に対して10件の応募がありました。2012年2月25日(土)に選考委員会が開催されて、日本考古学協会大賞に舟橋京子氏の『抜歯風習と社会集団』、奨励賞に樋上昇氏の『木製品から考える地域社会-弥生から古墳へ-』が推薦され、3月24日(土)の理事会において報告、承認されました。
この経緯を受けて、5月26日(土)の第78回総会で承認を受け、菊池徹夫会長から各受賞者に賞状と記念品が贈られました。
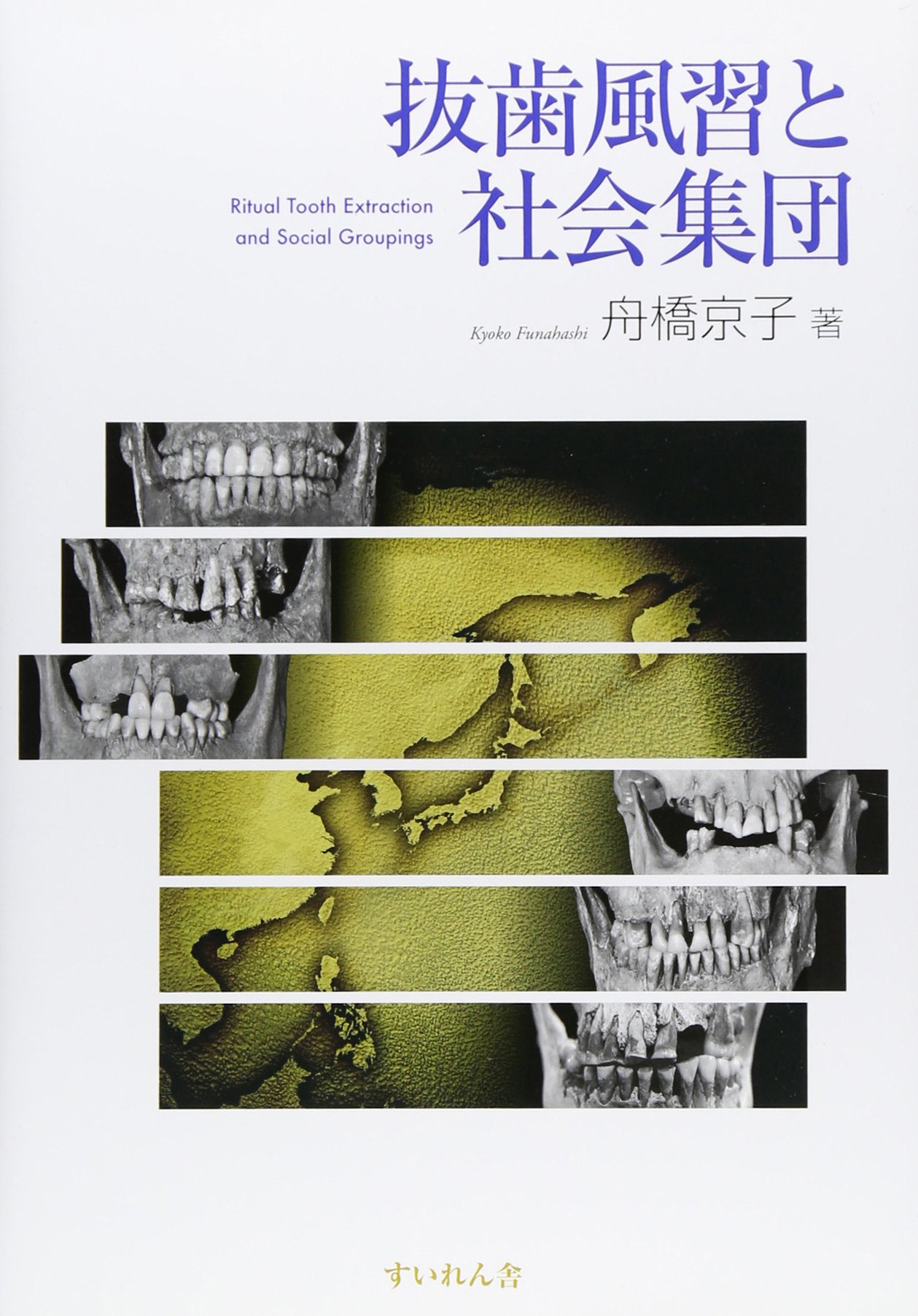
本書は、縄文時代から古墳時代にかけての抜歯風習について、東アジア各地との比較を行いながら総合的に考察し、抜歯風習とその背後にある社会集団の解明へと迫った研究である。詳細な研究史の検討から問題の所在を明らかにしたうえで、抜歯鑑定の基礎となる歯科学的方法から検討し、考古学・自然人類学の方法を駆使して抜歯型式の再検討、遺跡での出土状況および抜歯の施工年齢・順序、血縁関係や出産経験の有無等の基礎的事実を明らかにし、起源・系統論、社会的機能に関する考察を行い、抜歯がソダリティ表示の成人儀礼として盛行することなど従来の抜歯学説を大きく塗り替える成果をもたらした。
このように、歯科学、自然人類学、文化人類学の知見と方法を考古学の枠組みの中で融合させた本書は、抜歯研究や骨考古学の分野のみならず、先史社会研究において今後避けて通れない一書であることから、選考委員会は本書の著者、舟橋京子氏を第2回日本考古学協会大賞候補として推薦する。
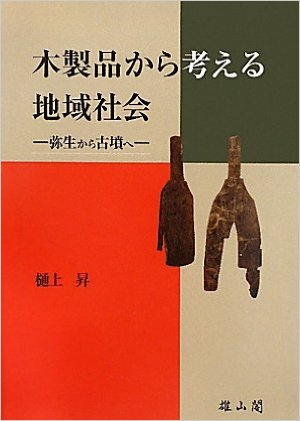
本書は、当該期の木器資料を広く集成し、用材、製作技術、使用などに関する基礎的研究を行い、さらに木器流通システムや、木器専業工人の成立過程など意欲的な社会的考察を行ったものである。その基礎的研究は緻密であり、主要用材が広葉樹から針葉樹へ移行するプロセスや農具形態変化の意味の解明のほか、多くの新知見をもたらした。また遺物論と集落論を有機的に関わらせることによって、弥生中期から後期にかけて鉄製工具の普及にともない完成品が木器流通の主体となること、また弥生中期以後に精製木製容器が中核集落で専業的に製作されだし、弥生後期には超精製容器が首長の空間で製作されるようになったことを解明している。木器は非常に多様な用途に用いた重要な器物であり、本書は今後の当該期の生活と社会を考えるうえで不可欠のものになるであろう。以上の理由から選考委員会は、樋上氏の著作を日本考古学協会奨励賞にふさわしいものと一致して判断した。
歴史教科書を考える 第7号
2010.5.23 日本考古学協会 社会科・歴史教科書等検討委員
新学習指導要領に基づく教科書の改訂と教科書委員会の取り組み
社会科・歴史教科書等検討委員会
平成20年度「小学校学習指導要領」改正とその後の動向
文部科学省から「小学校学習指導要領」の改訂が平成20(2008)年3月28日付で告示され、日本考古学協会が問題としてきた小学校第6学年社会科についても、取り扱う「内容(1)ア」に「狩猟・採集や農耕の生活、…」が明記され、学習対象を弥生時代以降に限るという制限がはずされた。しかし、取り扱う時代は、その後、文科省から発行された『学習指導要領解説・社会科』に、大和朝廷による国の統一を理解させるため、「狩猟・採集や農耕の生活について調べるとは、例えば、貝塚や集落跡などの遺跡、土器などの遺物を取り上げて調べ、日本列島では長い期間、豊かな自然の中で狩猟や採集の生活が営まれていたことが分かるようにするとともに、水田跡の遺跡や農具などの遺物を取り上げて調べ、農耕が始まったころの人々の生活や社会の様子が分かるようにすることである。」と明示され、あくまでも復活した「狩猟・採集の生活」は、日本列島の伝統や文化の基層として歴史的に位置づけるものではなく、弥生時代や古墳時代を理解させるためのコントラストとして扱うに過ぎない内容にとどめられていることが判明した。一方、1998年改定の際に厳格に「…の事項は扱わないものとする」とした、所謂「歯止め規定」が極めて少なくなっていることと、各学年における創意工夫や選択の枠を広げた形となっていることは、少しの救いと受け止められた。
また、文科省は、2009年の12月に、教科書編纂への新たな方針を打ち出した。従来の教科書の記述に対する量的な制限を緩和し、「網羅的にならないように、厳選して…」という前提条件を付し参考となる事例を充実させることを教科書編纂の新方針として打ち出した。これまでの方針と比べ、大きな方向転換にもみえる。具体的にどの程度の内容を補うことができるのか、動向を注意するとともに、この機に学会側からも、具体的な提言や情報の提供が必要と考えられた。
2009年度(平成21年度)「社会科・歴史教科書等検討委員会」活動
こうした状況を受け、社会科・歴史教科書等検討委員会(以下、「委員会」とする。)では、2001年度以降に使用する新しい教科書の編纂事業に対して、考古学の側からの提案を進めることとし、2009年度の活動を行ってきた。
a)75回総会時「小学校6年社会科(歴史)教科書を考える―教科書改訂への提言」
2009年度段階において、委員会では、各時代を通し、子ども達に伝えたい内容や、現行教科書の記述内容分析と再検討を行った。その結果、旧石器・縄文時代問題に限らず、弥生時代以降に関しても、今日の考古学的成果が十分に生かされているとはいえず、事実誤認も多く危惧された。
そうした状況を鑑み、第75回総会時の研究発表においては、検討・協議の途上の段階ではあったが、これまでの各時代を通しての分析作業を踏まえて具体的な提言を試みた。
研究発表の全体テーマは「小学校6年社会科(歴史)教科書を考える―教科書改訂への提言」とし、「学習指導要領の改訂とその後の動向」(松本)、「教科書改訂への提言 旧石器時代」(佐藤)、「教科書改訂への提言 縄文時代」(大竹)、「教科書改訂への提言 弥生時代」(岡山)、「教科書改訂への提言 古墳時代」(富山)、により、現行の教科書への提言と、新学習指導要領に基づいた教科書編纂に対するアピールを行った。小学校社会科教科書を発行する教科書会社にも開催の旨を通知し、出席を要請した。会場には、考古学協会会員の他にも、教科書や学校教育に関心のある方々の参加を多く得た。「列島の歴史をはじめから教えられない」という学校現場からの不安、「考古学的な成果が生かされていない不自然さや、身近な地域教材こそ児童にとっては馴染みやすい教材で社会科ひいては歴史に興味を持つきっかけになるはず」、旧石器・縄文時代の遺跡を多く持つ博物館関係者や自治体文化財保護担当者からは、「地域教材が活用されにくい状況への不安」などが意見やアンケートに寄せられた。残念ながら、教科書会社の方々からの見解やコメントはなかった。
また、総会2日目に行われたポスターセッションにおいても「小学校6学年 社会科(歴史)教科書を考える―現状と課題」をテーマに、これまでの経緯と現行の教科書の不自然さを指摘した。
b)2009年山形工科大学大会ポスターセッション
2009年10月17日・18日に開催された「日本考古学協会2009年度大会」ポスターセッションで、総会時に実施した内容を紹介した。大会の研究発表分科会では「分科会1:石器製作技術と石材」、「分科会Ⅱ:東北縄文社会と生態系史―押出遺跡をめぐる縄文前期研究の新たな枠組み」というテーマを持つほどに、山形をはじめ東北地域は、旧石器・縄文時代の遺跡が多く、研究も進んでいる地域であるが、現行教科書では、そうした成果すら児童に伝えることが困難である。こうした不自然な状況を、我々委員もあらためて痛感したが、会場を訪れポスターを読まれた方々の中には、「東北の文化の大事な部分をないがしろにした教育の在り方」と憤りを覚えるという方もあった。
c)岩宿博物館企画展「岩宿遺跡を学ぶ」
―日本考古学協会後援と展示解説講座への講師派遣―
詳細は、別稿に譲るが、群馬県の岩宿博物館が開催した企画展「岩宿遺跡を学ぶ」では、岩宿遺跡の歴史的役割と共に、明治から現在に至る教科書が展示された。この企画展開催にあたっては、岩宿博物館から日本考古学協会と日本旧石器学会に後援依頼があり、両学会がその趣旨に賛同し後援をした。また、博物館側からは、2010年2月14日に実施された企画展解説講座への講師派遣の依頼もあり、委員会の委員である大竹幸恵が「歴史教育と考古学―教科書から消えた旧石器・縄文時代の記述―」というテーマで講演をした。
岩宿遺跡は、旧石器時代という日本列島の黎明期の歴史を解明する契機となった学史的な遺跡である。講座には、その岩宿遺跡を大切に保存し活用するみどり市の市民が参加されていたが、現在の小学校6年生社会科(歴史)の在り方に対する驚きと、なぜ旧石器・縄文を小学生に教えないのか、その不思議さを指摘する声が多かった。
d)日本旧石器学会との懇談そして共催ミニシンポへ
日本旧石器学会は、2005年3月22日に発足した学術団体である。日本考古学協会主催の公開講座(第2回公開講座「日本列島の旧石器時代を知る~岩宿遺跡の世界~」)において、日本旧石器学会に協力を求め、当時の会長であった稲田孝司氏に旧石器時代を学ぶ意義について基調講演をいただいた経緯がある。その日本旧石器学会でも教科書問題を取り扱っていきたいとの方向性が示され、2009年12月27日に委員会と日本旧石器学会の担当窓口である広報委員会との懇談会が実現した。懇談会では、今後も情報交換だけでなく、両学会が合同の事業を企画する方向性も合意された。第76回総会時におけるミニシンポジウム「子ども達に旧石器・縄文時代をどう伝えるか―小学校の教科書で教えたい旧石器・縄文時代―」は、その活動の一環として委員会と広報委員会とが共催で実施し、日本旧石器学会からは白石浩之会長にパネラーをお願いし、歴史教育における旧石器時代の取り扱いとその意義について発言していただくことになった。
2010年度(平成22年度)活動 ミニシンポジウム
「子ども達に旧石器・縄文時代をどう伝えるか―小学校の教科書で教えたい旧石器・縄文時代―」を開催
日本考古学協会第76回総会第5会場
2010年5月23日(日)午後2時より
このシンポジウムは、日本旧石器学会広報委員会と共催で開催するものである。発表は、まず、考古資料を活かした郷土の歴史学習について、地域の博物館や学校の教育現場から報告をいただき、旧石器や縄文時代の研究者、教育学の研究者を交え、現状と課題、今後の方向性について議論する。
Ⅰ.事例報告
①野尻湖ナウマンゾウ博物館学芸員:中村由克氏
地域博物館における、児童や生徒を対象とした歴史学習の実践例を紹介していただく。また、教科書問題の影響や、その対策として学校側と取り組んでいる地域学習支援事業の内容等について紹介し、地域博物館としての今後の活動目標や、歴史学習の意義付けなどについて報告していただく。
②(元)川越市立西小学校長:松尾鉄城氏(東京国際大学教授)
学校の授業で、地域教材としての旧石器・縄文をどのように扱ってきたか、その実践例を紹介。また、学校の体制や社会科教育の現状と問題点を整理する中で、今後、考古学の成果を活かすために、どのような条件整備や連携の手法があるのか、その可能性や実践にあたっての歴史教育における視点について提言していただく。
Ⅱ.パネルディスカッション
事例報告者:中村由克氏、松尾鉄城氏
旧石器時代研究者:白石浩之氏
(日本旧石器学会会長・愛知学院大学教授)
縄文時代研究者:渡辺誠氏
(日本考古学協会副会長・社会科・歴史教科書等検討委員会委員長・名古屋大学名誉教授)
教育学関係者:木村茂光氏(東京学芸大学教授)
パネルディスカッションでは、
①教科書の影響とその問題について、
②旧石器・縄文時代を学ぶ意義について―教科書の課題と改善点について―、
③これからの歴史教育における考古学の課題
を議論の骨子として課題を整理し、今後の方向性として歴史教育に果たす考古学の役割や意義を導き出したい。
※今回のシンポジウムやポスターセッション等についてのご感想やご意見を、ぜひお寄せください。多くの方々の意見で、子ども達によりよい歴史教科書や、考古学的成果を生かした教育指導ができるような提言をしたいと考えています。
<情報>
社会科教科書の動向
2011年度(平成23年度)採択始まる
果たして旧石器時代・縄文時代の記述は
・・・新たなる提言と提案の必要性
2011年度から使用される新しい社会科(歴史)の教科書が文部科学省の検定を経て、現在、各市町村等でその見本本が陳列・閲覧されており、この6月に採択に向けての会議が持たれ、それぞれの地域で使用される教科書が決定される。
2011年度から採用される教科書は、2008年3月28日に告示された「小学校学習指導要領」の改訂を受けて、教科書会社が編纂したもので、今回の社会科教科書は、東京書籍・光村図書・日本文教出版の3社が編纂にあたっており、日本文教出版が一社で2冊の検定本を刊行し、計4冊の教科書が採択の対象とされている。
その具体的な内容の分析・検討については、今後の課題となるが、概観すると、縄文時代の復活に伴って、その扱い方に教科書間で格差が認められるようである。また、旧石器時代についての取り扱いについても、掲載している教科書と全く扱われていないもの、そして、その内容の位置づけが明確にされていないためか、内容の再検討が求められる表現も見受けられる。いずれも検定済みの教科書であるが、早急に分析を進めたい。
考古学の研究や調査成果が、教科書ならびに学校教育の現場において適切に取り扱われるよう働きかけや発信を恒常的にしていくことは、「社会科・歴史教科書等検討委員会」の大きな目的のひとつである。しかし、こうした働きかけは、委員会だけではその目標を達成し得ないことも多い。全国に4,000人を超す日本考古学協会員の方々に、それぞれの地域資料の情報提供と活用方法の提案を学校現場にして頂きたいと思う。また、委員会では、アンケートにおいて、多くの活用事例の情報提供を求めているが、そこで得られた情報を全国の教育現場に発信し、子供たちによりよい歴史学習を提供する、そのヒントになればと考えている。各方面に対する具体的な提言が、今後の委員会活動の大きな目標となろう。
<寄稿>
岩宿博物館企画展「岩宿遺跡を学ぶ」の開催について
岩宿博物館 今村 和昭
平成21(2009)年度は、岩宿遺跡発掘から60周年となり、還暦を迎える年度であった。
岩宿遺跡をメインとした岩宿時代専門の博物館である岩宿博物館では、年間を通してさまざまな岩宿遺跡発掘60周年イベントを実施した。「相沢忠洋資料特別展示」や「相沢忠洋、その人となり」という岩宿遺跡60周年記念特別展示や、例年秋季と冬季の2回開催される企画展も岩宿遺跡60周年を記念した企画展であった。
秋季企画展は岩宿遺跡そのものの実態を概観する展示であり、「岩宿遺跡はどのような遺跡だったのか」のテーマで実施した。
冬季の企画展は「岩宿遺跡を学ぶ」というテーマのもと、平成22年1月30日から3月7日まで開催した。明治初期の学制発布から、現在までの学校教育で使用された日本史の教科書を展示した。岩宿遺跡の取り扱い、大きくは学校教育における日本史教育のなかで、考古学的分野の取り扱いはどのような変遷をしてきて現在どのような問題が発生しているのかを考え直す機会を提供する展示を試みた。
岩宿遺跡の発見は、戦後の新しい教育観のもと、戦前の皇国史観のしがらみから歴史を自由にし、科学的根拠に基づいた歴史へと目を開かせる一つの原動力になった。その歴史的役割と学校における歴史教育における岩宿遺跡の意味の変遷をたどるのが本企画展のテーマであった。それと同時に、現在、小学校6年生で学習する歴史の中で、歴史教科書の記述が「弥生時代」からはじまるものが一般的となっており、岩宿時代(日本の旧石器時代)、縄文時代が削除され、日本列島における人類史が農耕社会から教えられているという現実の問題があり、広く観覧者に知ってもらうという意図があった。
日本考古学協会・日本旧石器学会等の学術団体でも現在の歴史教科書のあり方に危惧を示し、日本考古学協会では、常置委員会として「社会科・歴史教科書等検討委員会」を設置し、教科書の分析を通して、歴史教育における考古学の果たす役割について検討を重ね、考古学の成果が適切に活用されるよう広く提言していく活動を展開している。そこで、今回の企画展では、日本考古学協会・日本旧石器学会の両団体に後援していただき、様々な協力をいただいた。
また、特別に平成22年2月14日には、企画展解説講座を開催した。講師には、両学会のご協力により勅使河原彰先生・大竹幸恵先生にご依頼することができた。勅使河原先生は『歴史教科書は古代をどう描いてきたか』という著書を公表されているが、同テーマでそのエッセンスを講義していただいた。大竹先生には「歴史教育と考古学―教科書から消えた旧石器・縄文時代の記述―」というテーマで日本考古学協会の社会科・歴史教科書等検討委員会の活動状況と博物館と学校教育の取り組みを現場の学芸員の立場から講義していただいた。
講座には、37名の参加があり、両先生の講義を真剣に受講していた。参加者は一般市民であり、現行の教科書の実態を初めて知る参加者がほとんどで大きな驚きをもって講義に聞き入っていた。
日本考古学協会賞の設立は、第76回(2010年)総会で承認され、「日本考古学協会賞規定」が制定され、第1回日本考古学協会賞の推薦を行われました。2010年11月30日(火)の締切日までに5件の応募があり、2011年2月26日(土)に選考委員会が開催されて、日本考古学協会大賞に池谷信之氏の『黒曜石考古学-原産地推定が明らかにする社会構造とその変化-』、奨励賞に水澤幸一氏の『日本海流通の考古学-中世武士団の消費生活-』が推薦されました。特別賞は3月26日(土)の理事会で、坪井清足氏を永年の考古学分野での業績を評価し推薦されました。この結果は、第77回(2011年)総会で報告され承認を受け、各受賞者に賞状と記念品が贈られました。
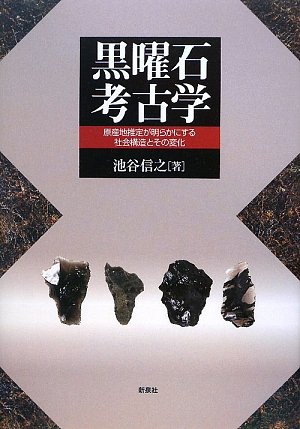
著者はこれまで、関東~中部地方の主要遺跡から出土した黒曜石製石器を蛍光X線分析によって原産地を同定するという方法で、石材採取・製作・流通・消費のプロセスから社会構造へとアプローチしてきた。本書はその成果であるが、出土黒曜石の全点分析という膨大な作業がその基礎をなしている。方法論の整理と学説史的検討を踏まえて、旧石器時代から縄文化過程、狩猟採集社会の終焉と弥生時代の石器利用など長いスパンを扱っている点も一つの特長で、例えば旧石器時代における環状ブロック群の分析から複数集団の存在を考察し、小集団の一時的集合によるブロック群形成の実態へと迫って従来の仮説の検証を行っている。著者はこれらの成果を踏まえて「黒曜石考古学」の確立を目指しており、今後その展開が期待されよう。
以上により、選考委員会は本書の著者、池谷信之氏を第1回日本考古学協会大賞として推薦する。

著者はこれまで、中世の北東日本海沿岸地域の遺跡・遺物の調査研究を進めるなかで、おもに中国陶磁食膳具や国内産の瓦器・土器・漆器などの物資流通史に加え、城館跡の実相を通して中世武士団の消費生活の実態解明を目指してきた。本書はその10年来の成果をまとめた意欲作であり、考古学の堅実な手法に基づいた実証的な研究に拠っている。
序章では中世考古学の視点や位置付け、年代観を説く。そして本論第1部では、貿易陶磁に関わる国際情勢、時期別出土量の比較検討、当該地域の優位性、搬入ルート、越後国衙との連関、鎌倉遺跡群の遺物諸相、個々の器種の搬入時期、在地越前陶の変遷、茶道具の保有、漆器へのシフトなどを論じる。
第2部では、瓦器の器種と性格、中世在地・搬入土器の消長、漆器の器形変遷などに言及する。さらに第3部では切り離せない遺構論として、室町期国人領主館への移動や戦国期山城への移動のほか、京からの井戸構築技術の移入などにも触れている。このように出土資料を駆使し、当域中世の流通の実態を総合的に描き出そうとした貴重な試みと言えよう。
以上により、選考委員会は本書の著者、水澤幸一氏を第1回日本考古学協会奨励賞として推薦する。
永年の考古学分野での業績を評価
-
受賞理由
永年にわたる考古学分野での業績並びに平成11年度の文化功労者受賞に対して、特別賞の授与を決定した。
歴史教科書を考える 第6号
2009.5.26 日本考古学協会 社会科・歴史教科書等検討委員会
『小学校学習指導要領』改訂を受けて
社会科・歴史教科書等検討委員会
1.『小学校学習指導要領』改訂の課題とその後の動向
文部科学省から『小学校学習指導要領』の改訂が平成20(2008)年3月28日付で告示された。改訂内容の特徴については、『歴史教科書第4号』でも紹介したが、各教科ともに、1998年の改訂の際に消えた内容の復活が示された。また、「…の事項は扱わないものとする」とした、所謂「歯止め規定」が極めて少なくなっており、各学校における創意工夫や選択の枠を広げた形となっている。
日本考古学協会が問題としてきた小学校第6学年社会科についても、取り扱う「内容(1)ア」に「狩猟・採集や農耕の生活、…」が明記され、学習対象を弥生時代以降に限るという制限がはずされたが、取り扱う時代については、「我が国の代表的な文化遺産や縄文時代の生活など、我が国の伝統や文化についての学習を充実」するとしており、相変わらず、旧石器時代の取り扱いは明記されていない。
さらに、その後、文科省から発行された『学習指導要領解説・社会科』によれば、大和朝廷による国の統一を理解させるために、「狩猟・採集や農耕の生活について調べるとは、例えば、貝塚や集落跡などの遺跡、土器などの遺物を取り上げて調べ、日本列島では長い期間、豊かな自然の中で狩猟や採集の生活が営まれていたことが分かるようにするとともに、水田跡の遺跡や農具などの遺物を取り上げて調べ、農耕が始まったころの人々の生活や社会の様子が分かるようにすることである。」としている。つまり、復活した「狩猟・採集の生活」は、それ自体が日本列島の伝統や文化の基層として歴史的に位置づけられたものではない。あくまでも弥生時代の「前史」として、網羅的にならない範囲でふれる事象の一つに過ぎないことがうかがえる。
現在、各教科書会社では、学習指導要領の改訂を受けて、2011年度以降に使用する新しい教科書の編纂事業が進められている。こうした中で文科省は、昨年の12月に、教科書編纂への新たな方針を打ち出した。従来の教科書の記述に対する量的な制限を緩和し、参考となる事例を充実させるというものである。網羅的にならないように、厳選して…というこれまでの方針と比べ、大きな方向転換にもみえるが、具体的にどの程度の内容を補うことができるのか、なお動向を注意するとともに、この機に学会側からも、具体的な提言や情報の提供が必要と考えられる。
2.教科書改訂に向けての委員会の活動
常置委員会として新たなスタートを切った、社会科・歴史教科書等検討委員会では、この新たな教科書の編纂を念頭に、各時代を通して、子ども達に伝えたい内容や、現行の教科書の記述内容の分析と再検討を併せて行っている。
その経過については、昨年、南山大学で開催された日本考古学協会の秋季大会でも、ポスターセッションとして公開してきたが、旧石器・縄文時代の問題に限らず、弥生時代以降に関しても、今日の考古学的な成果が十分に活かされているとはいえず、事実の誤認が多いことも危惧された。
各時代を通しての分析作業や、具体的な提言内容については、まだまだ、検討・協議の途上ではある。しかし、長期的な取り組みを前提として、今後、近いうちに教科書出版社をはじめとする各関係機関に、委員会の中で問題となった現行教科書の現状と課題を整理し、今後の展望含めて改善要望を伝え、併せて、今後の協力関係を提言する予定である。
考古学の研究や調査成果が教科書ならびに学校教育の現場において適切に取り扱われるよう働きかけや発信を恒常的にしていくことは、『社会科・歴史教科書等検討委員会』の大きな目的のひとつである。しかし、教科書ならびに学校教育の現場において適切に取り扱われるよう働きかけは、委員会だけでは成し得ないことも多い。全国に4,000人を超す日本考古学会員の方々に、自らの地域資料の情報提供と活用方法の提案を学校現場にして頂きたいというのが、委員会の願いである。
新学習指導要領の改訂に伴う中高校現場の
取り組み現状について
社会科・歴史教科書等検討委員会 委員 山岸良二
(東邦大学付属東邦中高等学校教諭)
本校の沿革と紹介
東邦大学付属東邦中高等学校は1952年(昭和27年)に習志野市泉町に開校された。校地は戦前まで、習志野騎兵旅団の駐屯地として「軍都習志野」といわれた日本陸軍中枢地の1つであった。中でも、本校地
はかつては「騎兵第15旅団」、終戦間際は「陸軍中央研究所」が置かれていた場所にあたる。戦後、これらの軍用地が学校用地として払い下げされ、西から東邦大学、日本大学、本校、千葉大学と「文教都市習志野」へと変身した。
本校の設立趣旨は法人本部のある東京大森に戦前より設置されていた医学部(帝国女子医科専門学校)、戦後習志野に設置された薬学部関係の師弟を対象に、その後継者を育成するための附属高校としての創立であった。そのため、開校初期の段階から多くの生徒が「医学部、薬学部、歯学部」方面を志望する傾向が強い特色をもつ学校であった。この傾向は、現在でも継続され今でも高校三年生の約3割が同様の志望指向性をもつ学校となっている。
現行の社会科カリキュラム
現在の本校は中学1学年定員約270名、高校1学年定員350名で構成されている。つまり、高校で新たに80名を募集する形態(一般に鏡餅型6ケ年一貫私立中高校)である。また、県内の進学高校の一翼を担っていることもあり、週6日制35時限体制を堅持している。このため、中学での社会科時間配当は〔中1歴史分野2時間、地理分野2時間、中2歴史分野2時間、地理分野2時間、中3公民分野3時間〕となっている。いわゆる標準時間数でみると、公民分野が1時間少ない形である。一方、高等学校は先に挙げた本校生徒の志望動向から〔高1世界史B3時間、倫理3時間共に必修、高2日本史Bか地理のどちらかを選択しての必修3時間、政治経済2時間必修、高3文系は世界史B、日本史B、地理b、政治経済、倫理から最高2科目を選択しての必修6時間、理系は先の5科目から完全に選択で1科目3時間、さらに文系では自分の志望大学受験科目を考慮してさらに自由選択で6時間まで〕というカリキュラムとなっている。
公表されている新教育課程の内容
現在まで文部科学省から公表されている「新教育課程」中学社会科、高等学校地歴・公民科に関係する変更点の主なる点は次の通りである。
中学では平成21年度入学生から「移行期間」に入り、平成22年度入学生から「新学習指導要項」に定める授業時間数を漸次実施していくことになる。平成21年度入学生は中学で「地理105時間、歴史105時間、公民85時間」を履修、これが平成22年度入学生以降になると「地理120時間、歴史130時間、公民100時間」となる。ここで問題となるのが、歴史分野は一部中学3年生での展開が認められているのに、地理分野は15時間増加にもかかわらず現行と同じ2年間での履修となっているため、どのように指導計画をたてるかが現場にとって重要な問題点となっている。
一方、高等学校では標準単位数の大きな変更が予定されていないが、改善事項の中に「必履修科目である世界史Bにおいて地理や日本史の内容も充実」させるようにとの指摘がある。また、旧来必要がある場合には「その標準単位数の一部を減ずることが可能」であったものがなくなるとの指摘もある。
現時点での本校の対応状況
本年3月に「新教育課程への対応協議」が進路指導部(部長山岸)から提案された。その背景には、センター試験科目で地歴・公民科目の一部に変更が予定されている旨の情報が入ったためである。4月には教務部からも各教科に対応策の検討に入るようにとの指示があり、本教科では既に3回(5月2日現在)教科所属教員全員で検討議論を進めている。