考古学における後継者育成の現状Ⅲ
賛助会員入会申込み受付けのお知らせ
一般社団法人日本考古学協会は、賛助会員の入会申込みを受付けています。賛助会員は、法人会員、フレンドシップ会員、学生会員からなる制度です。2025年度入会については、下記のとおり2024年11月30日(土)申込み締切(当日消印有効)です。入会希望者にお心当たりの方がありましたら、ご案内下さるようお願いします。
記
1 提出書類
(1)入会申込書 ※A4判で作成して下さい。
法人会員 フレンドシップ会員 学生会員
(該当項目をクリックし、ダウンロードしてください。)
(2)法人会員は法人に関する資料(全部事項証明書もしくは一部事項証明書、ほか)
2 送付先
一般社団法人日本考古学協会 事務局
(〒132-0035 東京都江戸川区平井5-15-5 平井駅前協同ビル4階)
※封筒に「賛助会員申込」と朱書きして下さい。
3 2025年度入会申込み締切日
2024年11月30日(土)当日の消印のものは有効。その後に到着したものは、次年度送りになりますので、ご注意下さい。
4 注意事項
申込みにあたっては、別記の「賛助会員に関する規定・内規」をご参照いただくとともに、以下の点にも十分ご留意下さい。
① 入会申込書は別記様式を使用し、フレンドシップ会員・学生会員においては、氏名部分は必ず自筆・捺印して下さい。ただし、外国人については自署のみでも結構です。
② 学生会員は、推薦者として、指導教員や共同に研究を実施する者などの研究を熟知している正会員の氏名(自署)・所属・連絡先、及び推薦文が必要です。
③ 2025年度入会については、フレンドシップ会員については2000年(平成12年)4月1日以前に生まれた方、学生会員については1997年(平成9年)4月2日~2007年(平成19年)4月1日に生まれた方が有資格者となります。
賛助会員に関する規定
(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人日本考古学協会(以下「協会」という。)規則第13条の定めに基づき、賛助会員の種別、入会資格と手続き及び権利・義務について必要な事項を定めるものである。
(種別及び要件)
第2条 協会の目的に賛同し、賛助会員になろうとする者は審査を経て入会することができる。その種別及び要件は次のとおりとする。
(1)法人会員 各種法人で、協会の事業を現在及び将来にわたって継続的に援助する団体
(2)フレンドシップ会員 入会年度の4月1日の時点において年齢満25歳以上の個人で、協会の総・大会等、諸事業に積極的に参加し、協会の活動を継続的に援助する者。ただし、正会員であった者はフレンドシップ会員になることができない。
(3)学生会員 入会年度の4月1日の時点において年齢満18歳以上の個人で、大学の学部または大学院の学籍を有し、考古学を研究する者
(入会の手続き)
第3条 入会を希望する者は、所定の手続きを経て、定款第5条第1項第2号の賛助会員になることができる。
(入会申請)
第4条 入会申請書には賛助会員の種別ごとに定めた申込書(様式3から様式5)をもって理事会に申請する。
2 法人会員は法人に関する資料を添付する。
3 学生会員は、研究を熟知している協会正会員(指導教員や共同に研究を実施する者など)の推薦を要する。
4 入会申請は年間を通じて受付ける。
5 入会申請は当該年度の11月末に締切り、審査対象とする。
(入会資格審査及び承認)
第5条 入会資格審査は、新入会員資格審査委員会の意見に基づいて理事会で行う。
2 法人会員にあっては、理事会における一次審査を経た入会希望者のリストを正会員に通知し、正会員からの意見を受付ける。
3 入会の承認は、定款第6条第2項の定めにより、理事会及び次年度の総会において承認を得る。
(権利・義務)
第6条 協会の賛助会員は、次の各号の事項が適用されるものとする。
(1)賛助会員は、定款第7条第2項に基づき、別に定める会費を支払う義務を負う。
(2)日本考古学協会賛助会員の名称の使用を認める。
(3)賛助会員のうち学生会員は、研究発表(口頭・ポスター)及び機関誌への論考投稿については正会員と同等の扱いとするが、研究を熟知している協会正会員(指導教員や共同に研究を実施する者など)による指導を経た証明を必要とする。また、法人会員・学生会員は図書交換会において優遇措置が適用される。
(4)各賛助会員には、協会の刊行物のうち、総・大会の『研究発表要旨』と『会報』(年3回発行)を配布する。
(賛助会員資格の喪失)
第7条 賛助会員のうち学生会員は、年齢満28歳を迎えた年度の末日をもってその資格を喪失する。
2 学生会員は、学籍を失った場合はその年度の末日をもって資格を喪失する。学籍を失った場合は該当者が協会に書面をもって報告する義務を負い、入会申込書の推薦者がこれを補佐する。
3 賛助会員は定款に定める定款第8条、第10条、第11条に該当すると認められた場合賛助会員資格を喪失する。
(任意退会)
第8条 賛助会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
附 則
1 2017年7月22日に制定し、同日から施行する。
2 2023年1月28日に一部改正し、同日から施行する。
賛助会員に関する内規
(目的)
第1条 この内規において、賛助会員の会費及び入会手続きに関する事項を定める。
(法人会員の実務責任者)
第2条 法人会員は、実務責任者1名を設け、法人会員としての実務を担当する。
2 法人会員で、実務責任者が交替した時はすみやかに協会に書面をもって届け出る。
(入会申込書)
第3条 入会申込書には、賛助会員の種別ごとの様式に必要事項を記載する。
(年会費の額)
第4条 賛助会員の会費は、次のとおりとする。
(1)法人会員 30,000円
(2)フレンドシップ会員 5,000円
(3)学生会員 3,000円
(会費の納入)
第5条 会費は、前納するものとする。
(会費未納による会員資格の喪失)
第6条 会費を3年以上滞納した者は、定款第11条第1項第1号により、賛助会員の資格を喪失する。
附 則
1 2017年7月22日に制定し、同日から施行する。
日考協第56号
2016年10月5日
文部科学省 初等中等教育局教育課程課 様
一般社団法人日本考古学協会
会 長 谷 川 章 雄
平成28年9月9日に公表されました次期学習指導要頷等に向けたこれまでの審議のまとめに対するパプリックコメントの実施について、一般社団法人日本考古学協会としての意見を申し述べることにいたします。学習指導要領の改訂にあたり、歴史教育に考古学の成果が適切に活かされるよう、以下の点について強く要望します。なお、一般社団法人日本考古学協会といたしましては、次期学習指導要領改訂に係る協力は惜しまない所存です.
記
1.134頁4行目 「博物館や資料館、図書館などの公共施設についても引き続き積極的に活用すること」について
2.185頁 社会科、地理歴史科、公民科における教育のイメージ 別添
3- 1【高等学校】①、【中学校】社会科③、【小学校】社会科(第3~6学年)③について
3.141頁 小学校社会 考えられる視点例 5~6行目 「時代、起源、由来」について
件名:【次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめへの意見】
氏名:一般社団法人日本考古学協会
職業:団体
住所:東京都江戸川区平井5-15-5-4F
電話番号:03-3618-6608
意見:分類番号⑨第2部2.(2)社会、地理歴史、公民
•134頁4行目 「博物煎や資料館、図書館などの公共施設についても引き続き積極的に活用すること」について
博物館や資料館、図書館などの公共施設の活用については、これまでも行なわれてきたことですが、引き続き積極的な活用を促していることは極めて重要かつ評価できると考えます。そのためには、日本列島全域に普遍的に存在する考古資料を保管する地域の博物館・資料館の充分な活用や、それらの館における子供たちの発達段階を踏まえた体験学習プログラムの活用が不可欠です。博物館・資料館を積極的かつ具体的に活用する方法を次期学習指導要領・学習指導要領解説に明示すぺきと考えます。社会科教育からの視点のみならず、この審議のまとめの眼目である「主体的・対話的で深い学び」の実現にも大きく寄与すると考えます。
件名:【次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめへの意見】
氏名:一般社団法人日本考古学協会
職業:団体
住所:東京都江戸川区平井5-15-5-4F
電話番号:03-3618-6608
意見:分類番号⑨第2部2.(2)社会、地理歴史、公民
•135頁 社会科、地理歴史科、公民科における教育のイメージ 別添
3 – I【高等学校】①、【中学校】社会科③、【小学校】社会科(第3~6学年) ③について
日本列島における弥生文化以降の歴史の流れは一律ではなく、北海道には続縄文文化・擦文文化・オホーツク文化・アイヌ文化、沖縄には貝塚文化・グスク時代の文化があり、それぞれ独自の文化が存在します。これらの文化について、子供たちが学習できるよう、次期学習指導要領に位置づけられることを要望します。
件名:【次期学習指導要領等に向けたこれまでの寄儀のまとめへの意見】
氏名:一般社団法人日本考古学協会
職業:団体
住所:東京祁江戸川区平井5-15-6-4F
電話番号:03-3618-6608
意見:分類番号⑨第2部2.(2)社会、地理歴史、公民
•141頁 小学校社会 考えられる視点例 5~6行目 「時代、起源、由来」について
今回の審議のまとめにおいて、新たに「起源」という視点が示されたということは、極めて重要かつ評価できると考えます。その点について、人類の発生から始まる歴史を明確に位置づけ、グローバルな視点から人類の歩みを考える視点を育むことを次期小学校学習指導要領に盛り込むことを要望します。具体的には、日本列島における人類の出現、すなわち旧石器時代を是非とも明示すべきであると考えます。現生人類は10~7万年前にアフリカ大陸を出て何世代もかけて世界各地へと拡散し、遅くとも4~3万年前には日本列島に人類が出現することは定説です。日本列島における人類の出現を学ぶことは、グローパル社会に生きる子供たちの国際理解を深めることは間違いないと確信します。
埋文委 第2号
2016年7月20日
文化庁長官 宮 田 亮 平 様
福岡県知事 小 川 洋 様
福岡県教育委員会教育長 城 戸 秀 明 様
北九州市長 北 橋 健 治 様
北九州市市民文化スポーツ局長 大 下 徳 裕 様
北九州市教育委員会教育長 垣 迫 裕 俊 様
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 藤 沢 敦
北九州市城野遺跡の保存と活用に関する再々要望について
標記の件について、別添書類の如く、当該遺跡は学術上極めて重要な内容をもつものでありますので、貴殿におかれましては、適切な保存と活用の対策が速やかに講じられることを再度要望いたします。
なお、まことに恐縮ですが、当件の具体的な措置、対策については2016年8月5日(金)までに、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。
記
一、別添書類 一通
以上
埋文委 第2号
2016年7月20日
文化庁長官 宮 田 亮 平 様
福岡県知事 小 川 洋 様
福岡県教育委員会教育長 城 戸 秀 明 様
北九州市長 北 橋 健 治 様
北九州市市民文化スポーツ局長 大 下 徳 裕 様
北九州市教育委員会教育長 垣 迫 裕 俊 様
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 藤 沢 敦
北九州市城野遺跡の保存と活用に関する再々要望について
日本考古学協会では、2011年2月25日付埋文委第12号において、城野遺跡の保存に関する要望書を提出しました。その後、現地での保存を市が断念したとの報に接し、2016年1月8日付埋文委第8号において、再要望書を提出しました。しかしながら、北九州市市民文化スポーツ局より2016年1月21日北九州市文文第2610号で寄せられたご回答では、方形周溝墓石棺の移築保存への方針変更と、玉作り工房の記録保存という、既定の方針が示されただけでした。
再三ご指摘させていただいておりますように、当該遺跡は九州最大規模の方形周溝墓や稀有な玉作り工房を伴う弥生時代中期~後期にわたる大規模集落跡であり、北部九州地域を代表する極めて重要な学術的意義を有する遺跡です。本年3月には城野遺跡のすぐ近くに所在する重留遺跡から出土した弥生時代後期の広形銅矛が、国の重要文化財に指定されました。重留遺跡のさらに東側に所在する重住遺跡では、同時代の竪穴住居跡から200点ものガラス玉が出土しております。これら3つの遺跡が、弥生時代後期に、この地域に繁栄した拠点集落と考えることに誰も異論はないはずです。城野遺跡と周辺の遺跡は、「魏志倭人伝」に記された九州北部の国々に匹敵する勢力が、この地域に存在した可能性を示すものであり、城野遺跡の学術的意義はこれら周辺の関係遺跡と併せて考えると一層重要なものとなります。
重留遺跡では、重要文化財に指定された広形銅矛を出土した竪穴住居跡は、当時の関係者の熱意と努力で今も地下に保存され、小規模ながら遺跡公園として一般公開されております。城野遺跡の土地は民間企業へ売却されておりますが、文化財保護に責任を持つべき行政機関として、当該企業への協力を求め、最後まで城野遺跡の保存と活用の方策を追求していただきたいと存じます。その際、周辺遺跡との関係を考慮し、総合的な保存と活用の方策を講じていくことが必要と考えます。以上のことから、日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会では、再々度、城野遺跡の保存と活用に関する下記の要望をいたします。
記
1 城野遺跡の現状を保存し、史跡として整備と活用を図ること。
2 周辺の関係する弥生時代遺跡を含めた、総合的な保存と活用の方策を講じること。
以上
埋文委 第10号
2016年2月19日
北九州市長 北 橋 健 治 様
北九州市市民文化スポーツ局長 大 下 徳 裕 様
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 矢 島 國 雄
北九州市城野遺跡の保存と活用に関する再要望書への回答について
平素より、日本考古学協会の活動に関しまして、ご理解とご協力をいただき感謝いたします。
さて、先般、貴市民文化スポーツ局長より、2016年1月21日付け北九市文文第2610号ならびに2月2日付け北九市文文第2752号により、城野遺跡の保存要望に係る当埋文委第8号に対する回答がありました。貴回答文を検討させていただきましたところ、その内容にはきわめて遺憾なところがあります。
貴回答文中の、「1 平成23年貴会要望後の経緯について」のなかに、「なお、移築保存への方針転換については、石棺を取り上げる前の平成26年1月に、貴会の田中良之元会長に説明を行っており、貴会には報告していると認識しております。」と記載されております。2011年2月の当委員会からの城野遺跡の現状保存の要望に対しては、同年3月に貴市教育委員会教育長から「城野遺跡内の重要遺構について、どのような保存が可能か検討していきます。」との回答が寄せられていました。しかし、その後の重大な方針変更に関しては、貴市からの正式な文書による通知は一切いただいておりません。にもかかわらず、今回の貴回答文の記載は、あたかも日本考古学協会が遺構の現地保存を断念することを了解していたかのような表現であります。さらに、故田中元会長個人に責任を負わせるかのような誤解を招く文言であり、故人の名誉に関わる問題であります。当委員会としましては、公的文書のなかに、経緯が不確かな元会長個人への通告に関する言及があることは、きわめて遺憾なことと考えます。
以上のことから、今回の貴市からの回答について強く抗議するとともに、その内容に関しては容認できないことを申し添えておきます。
以上
「第6回日本考古学協会賞」には、締切日までに10件の応募がありました。2016年2月16日(火)に選考委員会が開催されて、日本考古学協会大賞には関根達人氏の著書『中近世の蝦夷地と北方交易』、奨励賞に角田徳幸氏の著書『たたら吹製鉄の成立と展開』がそれぞれ推薦され、3月26日(土)の理事会で承認されました。各賞は、5月28日(土)の第82回総会において発表され、髙倉洋彰会長から賞状と記念品が授与されました。
受賞理由は、次のとおりです。
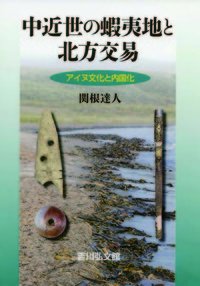
中・近世の北方史、北方交易史、蝦夷地の研究は、従来、考古学の成果を取り入れつつも、文献史学を中心に行われてきた。また、アイヌと和人の交易の推移や北海道島およびカラフト(サハリン島)への和人進出の実態を時空ごとに把握するために、アイヌ考古学と中・近世考古学が研究上、十分な接点をもってこなかった。これに対して本書は、まず編年の柱である出土陶磁器の精緻な調査と時期区分に基づきながら、アイヌ考古学と中・近世考古学の融合的研究を具体的に実践している。そして、その時期区分が蝦夷地の経済史と政治史の動向に連動することを明らかにし、融合研究の成果を陶磁史研究の枠組みに留まらず中・近世史学へ昇華させることを目指している点は、評価できる。つぎに、考古資料だけでなく、文献史料、絵画、墓標・社寺奉納物を含む石造物などのじつに多様な資料を導入して、総合的に蝦夷地の内国化の実態に迫ろうとする分析方法も高く評価できる。とくに、墓標を含む石造物の悉皆調査とその成果は、新境地を開拓し、文献史学へも大きな影響を与えている。本書におけるこのような分析方法は、じつは著者が前任地で近世城郭跡を発掘調査した際に、出土陶磁器や東北地方の近世墓の多様な副葬品の編年研究を実践する過程で培われたものである。
なお、既発表の論文を一冊の著書にまとめる際に、各節の「はじめに」を重複を避けてより整理された書き方にし、「序章」で簡単に触れられている研究史についてもう少し丁寧にまとめれば、より完成度の高い著書になったであろう。本書は、刊行からわずか1年余で出版元に在庫なし、という高い関心がもたれた好著であるので、その作業は重版に際して期待したい。また、考古学的に不明な部分が多いカラフト(サハリン)島への和人の進出については、著者に白主会所跡やアイヌ集落跡のロシアとの共同発掘をぜひ実現していただき、今後の解明を期待したい。
以上のように、学界に新たな中・近世の蝦夷地研究の方向性を示した本書は、高水準の著書であると評価できる。また著者は、「あとがき」で亀ヶ岡文化を中心とする縄文文化研究との二足の草鞋を履いていると述べているが、縄文文化の研究でも学際性を有する高い業績をあげながら、本書をまとめ上げた点も高く評価できる。推薦委員会は、本書を日本考古学協会大賞とする。

本書は、わが国における伝統的な製鉄の到達点である、たたら吹製鉄がどのような過程をへて成立・展開し、衰退するのか、また、東アジアの製鉄史の中において、どのように位置づけられるのかを詳細な考古学の発掘調査の実例をもとに実証的に検討した好著である。また、古文書や金属学的な所見なども、組み込んでおり、たたら吹製鉄という近世を対象とした考古学の分析と、それをもとにした歴史叙述に成功している。近世考古学のあるべき方法論のひとつを提示している。
たたら吹製鉄は、汎列島的な規模で鉄需要を賄えるほどの大規模な鉄生産であり、豊富な砂鉄を原料として、中国地方を中心に17世紀に成立した、わが国独自の製鉄法であった。
本書では、まず、箱形製鉄炉の成立から鉄鉱石の利用、日本の風土に適応した砂鉄利用のはじまりを整理し、中世の製鉄炉の形態や精錬鍛冶技術など、技術的な要素を検討して、その技術的な系譜から近世たたら吹製鉄が生まれることを検証する。
そして、たたら吹製鉄の具体的な様相について、その工程に沿って考古学の発掘調査の成果を基本としつつ、文献史料や金属学的な所見を縦横に使い、たたら吹製鉄の全体像を復元する。そして、高殿、製鉄炉を中心に、その地域的な特性を把握する。たたら吹製鉄の生産システムや鉄の流通などをもとに、「海の鈩」「川の鈩」「山の鈩」と地域による多様性を指摘する。考古学的な遺跡の分布や変遷と古文書や文献史料で明らかとなる操業の実態を照合することにより、地域ごとでのたたら吹製鉄の特性を示し、地域間での技術の移転を検討する。また、韓国の三国時代から高麗・朝鮮時代の製鉄遺跡と比較して、日本の製鉄が、朝鮮半島から技術移入によりはじまったが、その後は異なる展開をして、たたら吹製鉄が成立することを実証し、東アジアの製鉄でも、きわめて特異な存在であることを検証する。
本書は、具体的な調査例をもとに、日本独自のたたら吹製鉄の成立過程とその展開をあとづけるとともに、東アジアの中での独自性についても、その検証に成功している点が評価でき、日本考古学協会奨励賞とする。
鎌道路第177号
平成28年6月10日
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 矢島 國雄 様
鎌倉市長 松尾 崇
鎌倉市円覚寺西側結界遺構の保存に関する再要望について(回答)
鎌倉市円覚寺西側結界遺構の保存に関する再要望「円覚寺西側結界遺構開削計画を白紙に戻し、適切な保存と活用を図るための包括的な検討を行うこと。」について回答します。
北鎌倉隧道は、隧道の剥離等により「「利用者に対して影響を及ぼす可能性が高い」と判定できる。このため「緊急に対策を講じる必要がある状態」である」との診断結果を踏まえ、交通の危険を防止するため、鎌倉市が道路法第46条の規定に基づき平成27年4月28日から通行を禁止といたしました。
北鎌倉隧道の安全対策につきましては、一般社団法人トンネル技術協会に委託し、得られた提案を市として総合的に判断し、開削工法で実施することを決定したものです。
本市としましては、通学、通園及び一般の方が通行する道路であり、一日も早く安全対策工事を行い、安全を確保した上で通行が再開できるよう取り組を進めてまいります。
御理解をいただきますようお願い申し上げます。
【事務担当】
都市整備部 道路課
鎌教委文第453号
平成28年6月10日
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 矢島 國雄 様
鎌倉市教育委員会
教育長 安良岡 靖史
鎌倉市円覚寺西側結界遺構の保存に関する再要望について(回答)
鎌倉市円覚寺西側結界遺構の保存に関する再要望「円覚寺西側結界遺構開削計画を白紙に戻し、適切な保存と活用を図るための包括的な検討を行うこと。」について回答します。
北鎌倉隧道は、隧道の剥離等により「「利用者に対して影響を及ぼす可能性が高い」と判定できる。このため「緊急に対策を講じる必要がある状態」である」との診断結果を踏まえ、交通の危険を防止するため、道路法第46条の規定に基づき平成27年4月28日から通行を禁止といたしました。
北鎌倉隧道の安全対策につきましては、一般社団法人トンネル技術協会に委託し、得られた提案を市として総合的に判断し、開削工法で実施することを決定したものと聞いております。
鎌倉市では、通学、通園及び一般の方が通行する道路であり、一日も早く安全対策工事を行い、安全を確保した上で通行が再開できるよう取り組みを進めてまいるとのことです。
当委員会としましても、道路の通行機能の回復により、北鎌倉隧道の利用者が安全に通行できるようになることを望んでおります。
また、当該尾根につきましては、工事予定箇所において、等高線測量を実施し、尾根線の残存状況を確認したうえで、工法等については工事担当課と連携をとってまいります。
なお、貴協会の再要望書の内容は、「丘陵は横須賀線では切られていない」とする伊藤正義氏の見解を全面的に支持したものでありますが、これは別添資料に基づく当委員会の考え方とは異なることを申し添えます。
【事務担当】
文化財部 文化財課
鎌委文 第453号
平成28年6月10日
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 矢島 国雄様
鎌倉市教育委員会
教育長 安良岡 靖史
鎌倉市円覚寺西側結界遺構の保存に関する再要望書について(回答)
鎌倉市円覚寺西側結界遺構の保存に関する再要望「鎌倉市円覚寺西側結界遺構開削計画を白紙に戻し、適切な保存と活用を図るための包括的な検討を行うこと。」について回答します。
北鎌倉隧道は、隧道の剥離等により「「利用者に対して影響を及ぼす可能性が高い」と判定できる。このため「緊急に対策を講じる必要がある状態」である」との診断結果を踏まえ、交通の危険を防止するため、鎌倉市が道路法第46条の規定に基づき平成27年4月28日から通行を禁止といたしました。
北鎌倉隧道の安全対策につきましては、一般社団法人トンネル技術協会に委託し、得られた提案を市として総合的に判断し、開削工法で実施することを決定したものと聞いております。
鎌倉市では、通学、通園及び一般の方が通行する道路であり、一日も早く安全対策工事を行い、安全を確保したうえで通行が再開できるよう取り組みを進めてまいるとのことです。
当委員会としましても、道路の通行機能のかいふくにより、北鎌倉隧道の利用者が安全に通行できるようになることを望んでおります。
歴史教科書を考える 第14号
2016.5.19 日本考古学協会 社会科・歴史教科書等検討委員会
特集:社会科・歴史教科書等検討委員会発足10周年記念号
「社会科・歴史教科書等検討委員会」のこれまでの活動
1998(平成10)年の小学校学習指導要領改訂にともない、2002年より使用の小学校社会科教科書の本文から旧石器・縄文時代の記述が削除された。このことを受けて、我が国の歴史学習において、考古学の研究成果が適切に取り扱われるよう、国等に働きかけることを目的に、2006年に「社会科教科書問題検討小委員会」が発足した。2008年には常置委員会の「社会科・歴史教科書等検討委員会」となり、小・中学校の学習指導要領や社会科・歴史教科書の内容等について分析を行い、その成果を、文部科学省への声明文への提出、テーマセッション・ポスターセッションなどを通して広く社会に伝えてきた。
その結果、2008年改訂の小学校学習指導要領において、「狩猟・採集や農耕の生活」が示され、縄文時代を扱うことが明文化された。
しかし、『小学校学習指導要領解説 社会編』では「貝塚や集落跡などの遺跡、土器などの遺物」について調べるという表記にとどまり、人類史のはじまりについての説明は盛り込まれなかった。そこで、2014年日本考古学協会第80回総会では、次期学習指導要領の改訂に際し、小学校第6学年の歴史学習に旧石器時代の取り扱いを明確に位置付けることを目的として、「小学校学習指導要領の改訂に対する声明」を発表した。さらに、声明につづき「小学校学習指導要領の改訂に対する要望書」および「小学校指導要領等の改訂に対する改正案」を文部科学省に提出した。要望書では学習指導要領の修正事項をより具体的に明確化し、その改善を促すことを目的としており、①日本列島全域に普遍的に存在する考古資料を十分に活用し、身近にある郷土の歴史を学ぶ態度を養うこと。②人類発生から始まる歴史を明確に位置づけ、世界的な視野から人類の歩みを考える視点を育むこと。以上の2点に主眼におき成文化した。
要望書および改正案は2015年2月2日付で文部科学省に送付したが、これに対する回答は現在まで得られていない。しかし、本委員会としては中央教育審議会教育課程部会での審議のまとめ公表後と、文部科学省の学習指導要領改訂案公表後のパブリックコメントへの準備等、常置委員会としてその設立の趣旨を全うすべく、今後もあらゆる形で活動内容を広げていく所存である。
| 年度 | 活動内容等の概要 | 国の動向 |
| 2006 (H18) 年度 | □「社会科教科書問題検討小委員会」発足(4月) <発足経緯> *1998(平成10)年の小学校学習指導要領改訂にともない、「旧石器・縄文 時代」について教科書に記述されていない *第71回日本考古学協会総会において、学校教育に携わる会員から、上記に関する問題点が指摘 *日本考古学協会(理事会)において小委員会の設置了承 <活動の方向性> *教科書記載内容の根拠となる「学習指導要領」の問題点の明確化とその改 訂を要望 *現況の歴史学習の実態を検証し、より適切な内容となるよう提言 *原始・古代はもとより中・近世以降においても、歴史学習の素材として考古学の研究成果が有効であることを提示 □現行の教科書・学習指導要領の内容についての分析作業着手 □教科書会社(東京書籍)訪問(教科書編集過程等を取材) □愛媛大会においてポスターセッション開催(11月) *テーマ「歴史教育と考古学『教科書から消えた旧石器・縄文時代…』」 *アンケート調査実施 □文部科学大臣・中央教育審議会会長宛「学習指導要領の改訂に対する声明」を提出(11月) *旧石器・縄文時代の取扱いと、「続縄文・後期貝塚文化」に見られる地域 性の取り扱いについて要望 □第2回「日本考古学協会公開講座」(2007年3月)において、一般市民・マスコミ対象のポスターセッション及びアンケート調査を実施(テーマ、内容は愛媛大会時と同じ) | ◇教育基本法改正(12月) ○伝統と文化の尊重、我が国と郷土を愛する態度の養成 ○国際社会の平和と発展に寄与する態度の養成、など |
| 2007 (H19) 年度 | □第73回総会(5月、明治大学)において、ポスターセッション及びアンケート調査を実施(テーマ、内容は愛媛大会時と同じ) □通信「歴史教科書を考える」第1・2号発行 □東京学芸大学図書館の協力を得て、戦後から今日までに発行された小学校社会科教科書の資料収集・調査を実施 □熊本大会(11月)において、ポスターセッション及びアンケート調査を実施 *テーマ「教科書から消えた旧石器・縄文時代の記述-学習指導要領と教科書 の変遷-」 □中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会「教育課程部会におけるこれまでの審議のまとめ」に対するパブリックコメント(12月) □第1回シンポジウム「歴史教育と考古学」開催(2008年2月、東京学芸学) □「新学習指導要領の改訂」に対するパブリックコメント(2008年3月) □文部科学大臣、中央教育審議会会長宛「学習指導要領の修正に関する要望書」を提出(2008年3月) *「郷土」「旧石器時代」の取扱いを明確に追記することを要望 | ◇小学校学習指導要領告示・中学校学習指導要領告示(2008年3月) ○小学校社会科学習指導要領で、これまでの「農耕の始まり」を「狩猟・採集や農耕の生活」と改訂 |
| 2008 (H20) 年度 | □第74回総会(5月、東海大学)において、「考古学をとりまく諸問題」 *教科書に旧石器・縄文時代を記載する必要性や考古資料を活用した授業例 と学習指導要領の問題点の発表 □ポスターセッション及びアンケート調査を実施 *テーマ「学習指導要領と教科書の変遷―小学校第6学年社会科教科書にお ける旧石器・縄文時代の記述―」 □理事会(5月)において「社会科教科書問題検討小委員会」の常置化が承認 □理事会(7月)において「社会科・歴史教科書等検討委員会」として承認 □通信「歴史教科書を考える」第3・4・5号を発行 | ◇高等学校学習指導要領告示 (2009年3月) |
| 2009 (H21) 年度 | □第75回総会(5月、早稲田大学)において、『小学校6年社会科(歴史)教科書を考える一教科書改訂への提言』 *教科書の記述内容の分析作業を踏まえた具体的提言 □第75回総会(5月、早稲田大学)及び山形大会(10月、東北芸術大学)において、ポスターセッション開催 *テーマ「歴史教科書を考える」 □岩宿博物館企画展 「岩宿遺跡を学ぶ」(2010年2月)における企画展解説講座 *「歴史教育と考古学―教科書から消えた旧石器。縄文時代の記述―」とい うテーマで講演 | |
| 2010 (H22) 年度 | 2010 (H22) 年度 □第76回総会(5月、国士舘大学)において、ミニシンポジウムを開催 *テーマ「子ども達に旧石器・縄文時代をどう伝えるか―小学校の教科書で教えたい旧石器・縄文時代―」 *博物館及び小学校教育現場の実情についての事例報告後、課題に対する具体的な対策、学会としての活動課題について討論 □第76回総会(5月、国士舘大学)において、ポスターセッションを開催 *教科書の記載内容についての課題の掲示 *学習指導要領改訂告示後の検定本の速報展示 □兵庫大会(10月)において、ポスターセッションを開催 *テーマ「子ども達に弥生・古墳時代をどう伝える―小学校の教科書で教え たい弥生・古墳時代―」 | |
| 2011 (H23) 年度 | □第77回総会(5月、國學院大學)おいて、テーマセッションを開催 *テーマ「子ども達に弥生・古墳時代をどう伝えるか―小学校の教科書で教 えたい弥生・古墳時代―」 □栃木大会(10月、國學院大學栃木学園教育センター)において、ポスタ^セッションを開催 *テーマ「社会科教科書を考える」 | ◇小学校学習指導要領実施 |
| 2012 (H24) 年度 | □2012年度4月実施の「中学校学習指導要領」と中学校社会科(歴史)教科書の内容について継続的に分析 □第78回総会(5月、立正大学)及び福岡大会(10月、西南学院大学)において、ポスターセッションを開催 *テーマ「中学校社会科(歴史)教科書を考える」 *現行の検定済中学校歴史教科書(7社)の内容を一部掲示 □公募による委員の改選 □ポスターセッションにおける意見の整理・集約、問題点の抽出と総合的な比較・検討 ◇中学校学習指導要領実施 | ◇中学校学習指導要領実施 |
| 2013 (H25) 年度 | □第79回総会(5月、駒澤大学)及び長野大会(10月、長野市若里市民ホール・長野市社会福祉総合センター)において、ポスターセッションを開催 *中学校社会科(歴史)教科書の分析結果及び学習指導要領と教科書の記述 との対応関係を客観的に掲示 □ポスターセッションにおける意見の整理・集約、各社の教科書を「人類の誕生」「旧石器時代」「縄文時代」「弥生時代」「古墳時代」に区分した上で、問題点の抽出と総合的な比較・検討 | ◇高等学校学習指導要領実施 |
| 2014 (H26) 年度 | □文部科学大臣・中央教育審議会会長宛「学習指導要領の改訂に対する声明」を提出(5月) *「旧石器時代」の取扱いを明確にする声明 □第80回総会(5月、日本大学)において、テーマセッションを開催 *テーマ「小・中学校段階における歴史学習と考古学の役割-日本列島にお ける旧石器時代の取り扱いについて考える-」 □伊達大会(10月、だて歴史の杜カルチャーセンター )において、ポ スターセッションを開催 *テーマ「小・中学校段階における歴史学習と考古学の役割」 □第2回シンポジウム(11月8日、東京学芸大学)を開催 *テーマ「小・中学校段階における歴史学習と考古学の役割」 □通信「歴史教科書を考える」第12号を発行 □文部科学大臣、中央教育審議会会長宛「小学校学習指導要領の改訂に対する要望書」を提出(2015年2月) *「地域に残る遺跡や文化財」「人類のはじまり」「石器」の取扱いを明確 に追記することを要望 | |
| 2015 (H27) 年度 | □第81回総会(5月、帝京大学)において、ポスターセッションを開催 *テーマ「小学校学習指導要領等の改訂に対する要望」 □2015年度検定済小学校社会科教科書(4社)の内容について継続的に分析 □奈良大会(10月、奈良大学)において、ポスターセッションを開催 *テーマ「小学校社会科(歴史)教科書における弥生・古墳時代について」 *現行の検定済小学校歴史教科書(4社)および前回検定済教科書の弥生時 代から古墳時代の内容を比較掲示 □通信「歴史教科書を考える」第13号を発行 □「社会科・歴史教科書等検討委員会に関するアンケート」を実施 |
協会員の皆様へのお願い
これまで、ポスターセッション開催時や2015年8月発行の会報等で社会科・歴史教科書等検討委員会の活動等に対するアンケートを実施してまいりましたが、必ずしも多くのご意見が寄せられたわけではありませんでした。本委員会は、社会科・歴史教科書等の諸問題について多くの協会員と共有していく必要があると考えています。社会科・歴史教科書は子どもたちにとって考古学への入り口であり、考古学の将来のためにも極めて重要であることは言うまでもありません。どのようなことでも構いませんので、ご意見がありましたら下記へ、郵便またはメールでご一報ください。今後の活動に生かしてまいりたいと存じます。
〒132-0035 東京都江戸川区平井5-15-5 平井駅前共同ビル4階
日本考古学協会 教科書委員会担当
eメールアドレス:kyoukasyo@archaeology.jp
埋文委 第1号
2016年4月28日
文化庁長官 宮 田 亮 平 様
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 矢 島 國 雄
鎌倉市円覚寺西側結界遺構の保存に関する再要望書の送付について
標記の件については、2015年1月に関係諸機関に対し、保存を求める要望書を提出いた
しましたが、未だ十分な理解が得られていない現状に鑑み、別添書類のとおり、再度、神
奈川県および鎌倉市に対して、遺構の保存等に係る対策を早急に講じるよう要望いたしま
した。
つきましては、貴殿におかれましても、当該遺構の保存等に関して、ご理解とご協力を
いただきますようよろしくお願いいたします。
記
一、別 添 書 類 一通
以上
埋文委 第1号
2016年4月28日
神奈川県知事 黒 岩 祐 治 様
神奈川県教育長 桐 谷 次 郎 様
鎌倉市長 松 尾 崇 様
鎌倉市教育長 安 良 岡 靖 史 様
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 矢 島 國 雄
鎌倉市円覚寺西側結界遺構の保存に関する再要望について
標記の件については、2015年1月に関係諸機関に対し、保存を求める要望書を提出いた
しましたが、未だ十分な理解が得られていない現状に鑑み、別添書類のとおり、再度、遺
構の保存等に係る対策を早急に講じるよう要望いたします。
なお、恐縮ですが、当件に関する具体的な措置については、2016年5月16日(月)まで
に、当協会埋蔵文化財保護対策委員会委員長宛にご回答を下さるようお願いいたします。
記
一、別 添 書 類 一通
以上
回答先
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会委員長
〒132-0035 東京都江戸川区平井5-15-5-4F
TEL:03-3618-6608 FAX:03-3618-6625
メールアドレス:jim@archaeology.jp
埋文委 第1号
2016年4月28日
文化庁長官 宮 田 亮 平 様
神奈川県知事 黒 岩 祐 治 様
神奈川県教育長 桐 谷 次 郎 様
鎌倉市長 松 尾 崇 様
鎌倉市教育長 安 良 岡 靖 史 様
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 矢 島 國 雄
鎌倉市円覚寺西側結界遺構の保存に関する再要望書
JR横須賀線北鎌倉駅に近接する岩塊は、中世都市鎌倉を代表する古刹の一つ、円覚寺
の西側結界遺構です。その歴史的重要性に鑑み、当委員会では同遺構の開削計画について、
2015年1月28日付で保存要望書(埋文委第6号)を関係諸機関に提出いたしました。さら
に、文書提出後に鎌倉市教育委員会を訪れ、直接に保存の申し入れも行なっています。
その後の報道によりますと、工法はすでに決定し、2016年度に上記遺構を削り込むこと
が必至とのことであります。遺構を削り込む根拠として、明治期の鉄道建設により上記遺
構はすでに大きく削られていることが、あげられています。
しかし最近、有識者による地形図の詳細な検討の結果、鉄道敷設でほとんど損傷を受け
ていないことが確実になりました。結界遺構は、中世的景観をよく保持していることが明
らかになったのです。
この景観、すなわち、馬蹄形の谷戸の中に神社仏閣のおさまった風景こそ、中世以来の
鎌倉の特色と言っていいでしょう。この景観を保全すること、まちづくりに活かすことこ
そが、今、求められていることと思量します。
以上の観点から、日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、次の事項を強く要望い
たします。
記
円覚寺西側結界遺構開削計画を白紙に戻し、適切な保存と活用を図るための包括的な検
討を行うこと。
以上