日考協 第 号
2014年5月17日
文部科学大臣 下 村 博 文 様
中央教育審議会会長 安 西 祐一郎 様
一般社団法人 日本考古学協会
会 長 田中 良之
学習指導要領の改訂に対する声明の送付について
当協会の事業・活動に対し、つねづね御理解と御支援をいただき感謝いたしております。
さて、一般社団法人日本考古学協会では、本年5月17日、日本大学文理学部キャンパスで開催された第80回総会において、別紙の声明を発表いたしましたので、送付させていただきます。
当協会は、今後とも社会科・歴史教科書等に関する取り組みを継続し、改善に向けての協力を惜しまない所存です。
意のあるところおくみとりのうえ、よろしくご高配賜りますようお願い申し上げます。
記
一、別 添 書 類 一通
以上
日本考古学協会は、1998年の小学校学習指導要領改訂によって、第6学年の歴史教科書から旧石器・縄文時代が削除され、歴史学習が弥生時代からはじまるという不自然な教育がおこなわれていることに対して、繰り返し改善要望を提示してきました。2008年の改訂において、歴史学習のはじまりが「狩猟・採集や農耕の生活」と改められ、小学校の歴史教科書に縄文時代の記述が復活したことは大きく評価されます。
しかし、『小学校学習指導要領解説社会編』では、その具体的な内容として「貝塚や集落跡などの遺跡、土器などの遺物」について調べるという表記にとどまり、狩猟・採集の生活を営んだ日本における人類史のはじまりについての説明がありません。そのため旧石器時代について、本文で明確に位置づけられた教科書はなく、年表でも旧石器時代の名称が記載されていないという状況にあります。
旧石器時代の研究については、1949年の群馬県岩宿遺跡の調査以降、全国で1万ヶ所を超える遺跡の発見と調査事例の蓄積があります。そして、半世紀を超える研究によって、今日に連なる生活の技術や多様な環境を克服してきた社会の仕組みが具体的に解明されています。我が国の歴史を学ぶ上で、旧石器時代からはじまる歴史の推移と長く厳しい環境を克服してきた先人の営みが教科書の記述で取り扱われない現状は、学問の成果を教育に活かすという考えに逆行するものです。
また、旧石器時代の人々の生活・文化は、世界や東アジアとつながりをもちながら発展しつつ、次第に日本列島独自の地城性を形成してきたことも明らかにされています。これまでも中学校の社会科(歴史的分野)においては、世界史的視野で人類の出現と旧石器時代の生活・文化について扱っていますが、歴史を最初に学ぶ小学校段階で旧石器時代について学習することで、小・中・高等学校の学習内容の連続性を意識した学習が進み、「伝統と文化の尊重、それらをはぐくんできた我が国と郷士を愛し、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与」するとした教育基本法の理念を具現化するものと考えます。
私たちは、人々の生活や社会の営みをより具体的に復元することのできる考古学の成果が歴史教育に活用されるよう、今後ともこの問題への取り組みを継続し、改善に向けての協力を惜しまない所存です。考古学を通じて、子ども達がわが国の歴史や先人の知恵を学び、よりよい未来に向けて逞しく育ってくれることを願ってやみません。
日本考古学協会は、次期の小学校学習指導要領改訂に際し、小学校第6学年の歴史学習に旧石器時代の取り扱いを明確に位置付けた改訂を強く望みます。
以上、日本考古学協会総会の名において、ここに声明する。
2014年5月17日
一般社団法人日本考古学協会第80回総会
第5回(2014年度)日本考古学協会賞は、6件の応募がありましたが、うち1件の辞退があり5件でとなりました。 2015年2月23日(月)に選考委員会が開催されて、日本考古学協会大賞に溝口孝司氏”The Archaeology of Japan: from the Earliest Rice Farming Villages to the Rise of the State”Cambridge University Press“、奨励賞には青野友哉氏の『墓の社会的機能の考古学』と長友朋子氏『弥生時代土器生産の展開』で推薦され、理事会の承認を経て、第81回総会において承認され、髙倉洋彰会長から賞状と記念品が授与されました。
受賞理由は、次のとおりです。
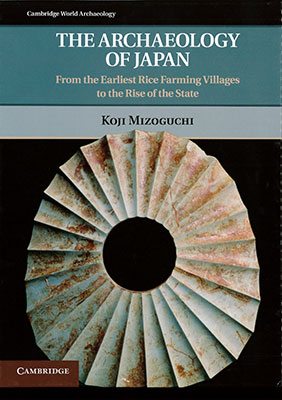
稲作導入から古代国家誕生までの過程を、資料を使いつつ理論的に著したことは、海外の研究者が日本考古学とくに初期農耕から国家形成過程の考古学を理解することを助ける。海外の研究者だけでなく国内の研究者にとっても有意義である。日本考古学の国際化が叫ばれる中、外国語での研究発表や論文発表が徐々に盛んとなってきているが、体系的な単著としては今村啓爾氏の”Prehistoric Japan”以来であり、溝口孝司氏が本書を出版した意義は大きい。
内容は概説的である部分もあるが、それはかえって海外の研究者が内容を理解するのをたすけるものであろう。弥生時代研究は氏のこれまでの研究をベースにした理論的枠組みが提示されており、そのオリジナリティは高い。
とくに第2部の、人口増大等に促された社会の複合性の増大が種々の調整機能の発達をもたらし、協同性に依拠した社会構造の再生産システムが血縁集団を単位とする成層秩序に依拠する社会に移行するプロセスの説明は、氏のこれまでの墓制研究に基づくところが大きく、この研究は新たな弥生時代像を造り出したと評価できる。さらに、社会的コミュニケーションの長期的変容過程として、初期農耕社会から国家形成を理解するという歴史的枠組みは日本考古学にとっては新たな視点であり、今後、国家成立におけるフレームワークの1つとなって議論が積み重ねられることが予想される。
”The Archaeology of Japan“というタイトルながら、旧石器時代と縄文時代がほとんど顧みられていないのは残念であるが、それは本書の価値を傷つけるものでない。初期農耕導入期から国家成立のまとまった体系の書として理解すべきである。
以上のように、本書は体系的で斬新な視点と豊富な内容を含み、海外に日本考古学の成果を発信するという点でも大きな意義を持つ。

一般に墓の調査・研究は、過去の社会の考古学的研究に必要なさまざまな情報をもたらす重要な研究分野となっており、それゆえ遺構としての墓に残る状況から埋葬時の行為や葬法を客観的に観察・記録するための方法論を確立することは、時代や地域を超越して墓の考古学全体の基本的な課題の一つと言える。本研究の優れた点は、このような問題意識に立ち、遺構としての墓が形成されていく過程の時間的な経過と変化の問題に焦点を当てたところにある。
第Ⅰ部では、埋葬環境を知る具体的な手がかりとして、墓坑覆土の土層断面の詳細な観察から、埋葬時に遺体の周りに空隙があったのか、土で充填されていたのかを判定する方法を検討し、その方法論の妥当性を近世アイヌ墓や弥生時代木棺墓を挙げて検証している。第Ⅱ部では、如上の研究法を縄文後期から続縄文期の墓の分析に適用し、当該期の葬法を独自の視点から再検討している。とくに注目されるのは、恵庭市カリンバ3遺跡の合葬墓が同時死亡・同時埋葬ではなく時間的経過を伴った順次の埋葬であった可能性を指摘したことであり、これが単純な複数遺体の合葬墓ではなく、各ムラの代表者が埋葬される共同墓として社会統合上の重要な機能があったと考察している。
カリンバ3遺跡の合葬墓に関するこの新解釈に対しては、同遺跡の発掘調査者から土層断面観察の判断をめぐって反論が提起されており、事実関係は決着していない。また、遺構形成に関する状況判断がそのとおりだとしても、墓の社会的機能の考察にはやや解釈の飛躍が認められる。しかしながら、遺構の形成過程を十分検討せずに誤った解釈がなされる危険性は常にあり、このような議論が提起されたこと自体、墓の考古学にとって好ましいことと考える。より多くの事例を用いての検証が課題として残るが、むしろ青野氏の問題提起を意義深いものと評価し、またカリンバ論争のような議論が他の分野にも拡大することを期待する。
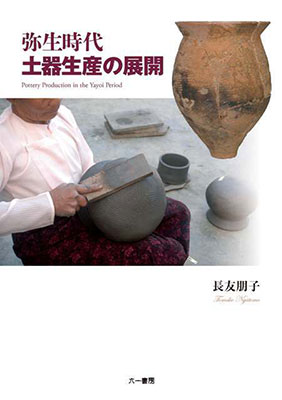
弥生時代の土器研究は、編年や製作技術と組成の変化、地域性と地域間交流、など各地で多くの蓄積がある。しかし、これまでは地域や時期、分析視角を限定したものが多く、初期の研究を除けば、通時的かつ広範囲を対象とする成果はいたって少なくなっている。その中にあって、本研究は、弥生時代前期から古墳時代前期までの畿内と北部九州の双方を取り上げて、土器の地域色、土器生産体制の変遷、外来食事様式の導入と食器組成の変化、東アジアの動向との関連など、弥生時代土器の生産を総合して論じる。また、土器の焼成痕跡の分析や、現代タイにおける野焼き土器生産の調査成果も加味する。個々の議論は、それぞれ一定の先行研究があるものの、それらを総合し、かつ詳細な分析に基づいて弥生土器生産体制の変遷や分業の問題まで論じる意欲的な論文と評価できよう。一部やや粗削りな部分があるとしても、近年、個別分散化する傾向が顕著な中にあって、今後の弥生土器研究に対して大きな刺戟となる力作であり、本書を日本考古学協会奨励賞に推薦する。
教生第 1435号
平成26年2月14日
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員長 矢島 國雄 殿
杵築市長 永 松 悟
杵築市教育委員会
教育長 清末陽一
杵築市杵築城遺跡の保存に関する要望書の回答について
2014年1月30日付、埋文委第11号で、送付されました要望書につきまして、下記のとおり回答いたします。
記
別紙回答書のとおり
回答書
1 藩主御殿跡の顕著な遺構の存在する現位置での中学校建設を中止し、全面的な遺構の保全を図ること。
回答:杵築市としましでも、今回の発掘調査の結果等につきまして、その重要性は十分認識しております。そもそも当初より杵築市並びに杵築市教育委員会は津波に対する安全性、埋蔵文化財調査が工期に与える影響、現在地の狭隘性の解消等で、代替地での建替えを提案していました。しかし利用者の立場から移転により生じる通学条件の変化、通学距離の延長、防犯・交通安全の確立を危倶する意見も強く、実質審議は平行線をたどることとなったため、平成23年1月に杵築中学校改築事業用地検討委員会を設置し、平成24年3月まで計7回 の委員会を開催し検討した結果、現地での建替えとする報告がされました。それを受けて杵築中学校建設検討委員会と杵築中学校改築に伴う杵築藩主御殿埋蔵文化財調査指導委員会をそれぞれ設置しました。各委員会での調査検討の結果を踏まえると、現地での中学校建設により遺跡空間としての価値が損なわれますが、発掘調査で出土した遺構については、その都度、建築担当課と協議し、設計変更などの措置をとってきており、発見された重要とされる遺構の大部分を残せるような状況です。今後も現地調査が続きますが、調査結果を踏まえ新たな遺構が最大限保存できるように建築担当課との協議を続けていきたいと思います。
2 御殿跡において今後保存を前提とした学術調査をおこない、遺跡全体の様相を明らかにすること。
回答:杵築中学校の建設スケジュール等を踏まえながら、可能な限り確認調査をおこない遺跡全体の全容解明に努めます。
3 調査成果を踏まえた城跡全域を史跡に指定し、将来に向けた整備と活用を図ること。回答:藩主御殿に関連した地域について、中学校が建設される「学校用地エリア」にある遺構については「活きた教材」となるように、その他の部分では市史跡 である「御殿の庭」 等を「歴史・文化エリア」として、それぞれについて整備・公開・活用を専門家の意見を取り入れながら検討していきます。
埋文委 第12号
2013年2月1日
埋蔵文化財保護対策委員会
委員各位
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 矢島國雄
2013年度埋蔵文化財保護をとりまく状況の調査について(依頼)
時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 日頃より、日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会の活動につきましては、ご理解とご尽力を賜りますこと、厚く感謝申し上げます。
さて、埋蔵文化財保護対策委員会では2013年度の活動の一環として、委員の皆様の協力を得て「2013年度埋蔵文化財保護をとりまく状況の調査」を実施することになりました。
年度末のご多忙な時節と存じますが、下記の要領でご記入の上、提出下さいますようお願い申し上げます。調査結果は総会前日の委員会で報告するとともに、今後の資料としても活用させていただく予定でおりますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1、提出期限 2014年3月31日(月)必着
期限を過ぎて到着した分につきましては、委員会の資料に掲載できませんので、早めのご提出をお願いいたします。
2、記入方法 別紙(doc file)参照
3、提出方法 別紙(doc file)参照
以上
.docファイル(記入用紙共)
教生第 1435号
平成26年2月14日
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員長 矢島 國雄 殿
杵築市長 永 松 悟
杵築市教育委員会
教育長 清末陽一
杵築市杵築城遺跡の保存に関する要望書の回答について
2014年1月30日付、埋文委第11号で、送付されました要望書につきまして、下記のとおり回答いたします。
記
別紙回答書のとおり
回答書
1 藩主御殿跡の顕著な遺構の存在する現位置での中学校建設を中止し、全面的な遺構の保全を図ること。
回答:杵築市としましでも、今回の発掘調査の結果等につきまして、その重要性は十分認識しております。そもそも当初より杵築市並びに杵築市教育委員会は津波に対する安全性、埋蔵文化財調査が工期に与える影響、現在地の狭隘性の解消等で、代替地での建替えを提案していました。しかし利用者の立場から移転により生じる通学条件の変化、通学距離の延長、防犯・交通安全の確立を危倶する意見も強く、実質審議は平行線をたどることとなったため、平成23年1月に杵築中学校改築事業用地検討委員会を設置し、平成24年3月まで計7回 の委員会を開催し検討した結果、現地での建替えとする報告がされました。それを受けて杵築中学校建設検討委員会と杵築中学校改築に伴う杵築藩主御殿埋蔵文化財調査指導委員会をそれぞれ設置しました。各委員会での調査検討の結果を踏まえると、現地での中学校建設により遺跡空間としての価値が損なわれますが、発掘調査で出土した遺構については、その都度、建築担当課と協議し、設計変更などの措置をとってきており、発見された重要とされる遺構の大部分を残せるような状況です。今後も現地調査が続きますが、調査結果を踏まえ新たな遺構が最大限保存できるように建築担当課との協議を続けていきたいと思います。
2 御殿跡において今後保存を前提とした学術調査をおこない、遺跡全体の様相を明らかにすること。
回答:杵築中学校の建設スケジュール等を踏まえながら、可能な限り確認調査をおこない遺跡全体の全容解明に努めます。
3 調査成果を踏まえた城跡全域を史跡に指定し、将来に向けた整備と活用を図ること。回答:藩主御殿に関連した地域について、中学校が建設される「学校用地エリア」にある遺構については「活きた教材」となるように、その他の部分では市史跡 である「御殿の庭」 等を「歴史・文化エリア」として、それぞれについて整備・公開・活用を専門家の意見を取り入れながら検討していきます。
厳しさを増す研究環境
歴史教科書を考える 第9号
2013.5.26 日本考古学協会 社会科・歴史教科書等検討委員会
1.教科書等検討委員会の活動目標
社会科・歴史教科書等検討委員会は、中学校歴史教育の改善を目的として、2012年度4月から実施された中学校教育の新学習指導要領の内容、そして中学校の新しい社会科(歴史)教科書の内容について継続的に分析を進めてきた。そして、検討委員会発足時より進めてきた小学校の社会教科書および学習指導要領の分析もあわせて、小・中一貫した歴史教育を対象としたテーマセッションを、日本考古学協会第80回総会において実施することを中期活動目標として掲げている。
2.2012年度の活動内容
こうした目標のもと、教科書等検討委員会では第78回総会(於立正大学)および2012年度大会(於西南学院大学)のポスターセッションにおいて、帝国書院、日本文教出版、教育出版、東京書籍、清水書院、育鵬社、自由社(順不同)7社の中学校検定済み教科書の内容を一部掲示した。これは会員の方々に中学校歴史教育の一端を知っていただくと同時に、教科書の内容について多くの意見・感想を募ることを目的としていた。
ポスターセッションで集まった意見を整理・集約した後、検討委員会では各社の教科書を「人類の誕生」「旧石器時代」「縄文時代」「弥生時代」「古墳時代」に区分し、各時代についてグループ検討会を行い、問題点の抽出と総合的な比較・検討を行った。
分析の結果、①明らかな間違い、②表現・情報の不足、および資料の考証不足等による誤認や曲解が危惧されるもの、③定説ではない学説への偏重、④教科書間での取り扱いの不統一性など、いくつかの問題点を抽出することができた。
3.今後の活動計画
①学習指導要領の分析
教科書の記述内容は、教育現場や教科書編纂側が学習指導要領をどのように解釈するかによって異なってくるが、学会として教科書に反映してほしい内容とは何か、小・中学生に伝えるべきことは何なのかを検討していく前提として、学習指導要領の解釈と教科書の記述内容の分析を進める。
そこで、このたびのポスターセッションでは、学習指導要領の内容がどのように中学校教科書に反映されているかを見極めることを目的として、学習指導要領と教科書の記述との対応関係を客観的に示すことで、学習指導要領の内容が教科書編纂者によってどのように解釈され、具体的な記述となっているかを明らかにする。学習指導要領とこれに則した教科書の分析を通し、義務教育の段階的な教育方針に沿った歴史教育の在り方について考えていく。
②日本考古学協会の提言
教科書等検討委員会がこれまで分析した教科書の記述内容について、明らかな間違いについては出版社に修正を促す努力をしていくべきであるが、資料の考証不足による誤認や曲解、定説となっていない学説への偏重といった問題については、現段階における考古学の研究・調査成果を踏まえた適切な解釈を反映させていかなければならない。こうしたことからも、日本考古学協会としては、教科書の内容不備を指摘するだけに留まらず、歴史教育の中で小学生や中学生に何を学ばせるべきか、ということ明確にし、文部科学省へ提言していく必要がある。
学習指導要領は、中央教育審議会が文部科学大臣の諮問を受けた後に、(初等中等教育分科会)教育課程部会での議論を経た上で審議のまとめが答申され、学習指導要領の改定案が公表されるが、日本考古学協会としては、教育課程部会での議論がはじまる以前に、学会としての明確な提言を準備しておく必要がある。そのためにも、中期活動目標である第80回総大会におけるテーマセッションでは、義務教育全体を対象としたテーマセッションを実施し、これに合わせて対外的なシンポジウムを開催する。なお、このテーマセッションとシンポジウムに向けて、第1期教科書検討委員会メンバーとの合同委員会を開催することで、小・中一貫した歴史教育の分析を進めていく。
学習指導要領ができるまで
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/idea/index.htm(文部科学省ホームページ参照)
③教科書における旧石器時代の掲載に向けて
現行の学習指導要領の改訂に伴い、小学校教科書から旧石器・縄文時代の記述が消えた問題については、その後、「狩猟・採集」として縄文時代に関わる記述は復活したものの、旧石器時代の取り扱いについては未だ問題が残されたままとなっている。教科書検討委員会発足の契機ともなったこの問題については、義務教育の中で旧石器・縄文時代を学ぶ意義とその必要性についてこれまでも議論を重ねてきており、今後も学習指導要領の改訂に向け、継続的に働きかけることが重要な課題となっている。上記テーマセッションにおいても再度この問題を取り上げ、問題解決の糸口を模索していきたいと考えている。
4.歴史教育のための補助教材
これまで教科書等検討委員会では、主に学習指導要領と検定教科書の内容について分析を進めてきたが、その一方で、小・中学校の歴史教育の現場で使用されている副読本などの補助教材についても活用事例を把握するべきであると考えてきた。また、学校教育に限らず、地域の博物館や学習館、埋蔵文化財関連機関等で行われている体験学習など、実践活動を導入した授業や講座のあり方についても、歴史教育の観点からその実態を把握したいと考えている。
しかし、単に活用事例を集めるだけでなく、歴史教育において実際にどのような学習効果をもたらしているのかについても明らかにするべきであり、教科書等検討委員会では今後、小・中学校における補助教材の活用や体験授業などの実践事例を集め分析することによって、教科書以外から得ることができる学習効果についても検討を進めていきたい。
埋文委 第11号
2013年3月21日
文化庁長官 近藤 誠一 様
神奈川県知事 黒岩 祐治 様
神奈川県教育長 藤井 良一 様
茅ヶ崎市長 服部 信明 様
茅ヶ崎市教育長 神原 聡 様
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 矢 島 國 雄
茅ヶ崎市下寺尾官衙遺跡群の保存と活用に関する要望について
標記の件について、別添書類の如く、当該遺跡は学術上きわめて重要な内容をもつものでありますので、貴殿において、適切な保存の対策が速やかに講じられることを要望いたします。
なお、当件の具体的な措置、対策については、2013年4月10日(水)までに、ご回答をくださるようお願いいたします。
記
一、別添書類 一通
埋文委 第11号
2013年3月21日
文化庁長官 近藤 誠一 様
神奈川県知事 黒岩 祐治 様
神奈川県教育長 藤井 良一 様
茅ヶ崎市長 服部 信明 様
茅ヶ崎市教育長 神原 聡 様
一般社団法人日本考古学協会
埋蔵文化財保護対策委員会
委員長 矢 島 國 雄
茅ヶ崎市下寺尾官衙遺跡群の保存と活用に関する要望書
茅ヶ崎市下寺尾に所在する西方A遺跡は、古代相模国高座郡衙跡に比定され、隣接地に現存する下寺尾古代寺院跡や津・祭祀遺跡等とともに茅ヶ崎市下寺尾官衙遺跡群を構成する重要な遺跡です。
西方A遺跡では、2002(平成14)年の北陵高校の建て替えに先行する調査で、郡庁や正倉を構成する掘立柱建物群が発見され、その所在が明らかにされています。さらにその後、今日までの10余年間に、茅ヶ崎市教育委員会による下寺尾古代寺院跡の確認調査等も継続的に実施され、古代の地方官衙を構成する様々な遺構群が揃って明確に確認されてきております。さらに、発掘調査の進展をうけて、全国の古代史研究者や考古学者による茅ヶ崎市下寺尾官衙遺跡群に関する研究も着実に積み重ねられてきています。
このような学術的な調査・研究成果の蓄積を基に、下寺尾官衙遺跡群が間もなく国指定史跡となるであろうことを、私たち日本考古学協会も強く期待していたところです。
そのようななか、神奈川県は、県立茅ヶ崎北陵高等学校の現校地内すなわち西方A遺跡内に新校舎を建設する方針が決定したという報道に接しました。しかし、残念ながら、新校舎建設については計画が語られているのに対して、肝心の下寺尾官衙遺跡群の利活用については全く議論がなされておりません。このことは、この10余年間の下寺尾官衙遺跡群の保護・整備・活用に向けて地道な努力を重ねてきた地元茅ヶ崎市や関係諸機関のこれまでの努力を無にするものであり、到底容認することができるものではありません。現地では、官衙域の発見後今日に至るまで、高校は仮設校舎で授業を行うなど、異例の事態が続いています。国指定史跡の実現には、問題の先送りを避けるべきで、県立北陵高校の移転も視野にいれた抜本的な対処をすることが望まれます。
日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、埋蔵文化財の保護と活用の観点より、下記のとおり、あらためて要望いたします。
記
高座郡衙跡をはじめとする茅ヶ崎市下寺尾官衙遺跡群を一体的に国指定史跡とし、本格的な保護と整備を実施して、国民共有の歴史的文化遺産として将来にわたり活用・公開できるようにすること。
以上
第4回日本考古学協会賞は、6件の応募があり、2014年2月26日(水)に開催された選考委員会によって、日本考古学協会大賞に田尻義了氏の『弥生時代の青銅器生産体制』、奨励賞に斎野裕彦氏の「仙台平野中北部における弥生時代・平安時代の津波痕跡と集落動態」と水ノ江和同氏の『九州縄文文化の研究-九州からみた縄文文化の枠組み-』が推薦され、理事会の承認を経て、第80回総会において承認され、田中良之会長よから賞状と記念品が授与されました。

弥生時代の青銅器生産は、製品の型式分類と時期的変遷の検討から、これまでも社会の発展段階に対応していることが明らかにされてきた。そこで、青銅器生産体制と社会の発展段階の対応関係をいっそう明らかにしようと、製品にくらべて等閑視されてきた観のある鋳型に視点を据え、その製作痕跡である加工痕を細緻に分析し、地域性や時期変遷を解明している。その分析に当って、日本列島に隣接する中国や朝鮮など東アジアの諸地域で知られている青銅器の生産体制を視野に入れ、比較対照している。また、資料の豊富な小形仿製鏡や巴形銅器の細緻な分析から、中期のピラミッド型(自立・分散型)から後期のネットワーク型へと製作や流通が変化していく様相を復元し、それが部族社会から首長制社会へと変化する社会の変化への対応であることを明らかにしている。このように、従来研究されてきた製品の検討に加え、鋳型の製作痕跡、地域性、時期変遷などを解明した実証性の高い内容は弥生時代青銅器研究に新たな境地を開拓した点で高く評価ができる。言い換えれば、生産体制を論ずるにあたって製品のみでは不十分であることを喝破している。生産体制であるから、たとえば工房や工人組織などの解明も重要であり、鋳型研究の開拓によって青銅器研究の新たな視点を提起した著者に今後を期待したい。
このように、学界に新たな青銅器研究の方向性を示した本書は、弥生時代青銅器生産体制の総合的研究書として高水準の著書であると評価できる。選考委員会は、本書を日本考古学協会大賞候補として推薦する。

縄文文化の研究は、遺跡の数や規模が圧倒的な東日本を中心に進められてきた。本書は九州から日本列島全体の縄文文化の性格や枠組みを相対化してとらえなおす、意欲的な著作である。本書の特徴は、土器編年を基軸に集落や遺物などの文化現象を丹念に掘り下げるという、オーソドックスであるが手堅い手法で分析を進めている点である。研究史も的確に整理されており、長い研究の蓄積を踏まえた渾身の一書といってよい。近年、縄文文化の一体性に疑問が提示されているが、サハリン、千島、伊豆諸島、南島、そして朝鮮半島と東アジア的な視点から縄文文化の枠組みをとらえ、言語という壁によって隔てられた文化であるという理解を示した。異論や意見もあろうが、あらたな理解として注目されよう。行政という研究に時間を割くことが困難な職場にあって、これだけの書物をまとめあげたことも高く評価され、ここに本書を推薦する。
「仙台平野中北部における弥生時代・平安時代の津波痕跡と集落動態」 『東北地方における環境・生業・技術に関する歴史動態的総合研究』
東北芸術工科大学東北文化研究センター
関連資料の考古学および地球科学の学際的な分析を基礎とし、記録資料も詳細に検討して、災害の実態と、それに対する人類社会の対応について解明したものである。弥生時代中期の津波が2011年3月11日の津波に匹敵する規模であり土地利用に大きな変化をもたらしたこと、貞観16年9月7日(西暦869年10月15日)の津波はそれより小規模であり影響も限定的であったことが示されている。その多角的な研究手法とそれによる成果の重要性、また社会への貢献度の高さから、選考委員会は本論文を日本考古学協会奨励賞にふさわしいものであると一致して推薦した。